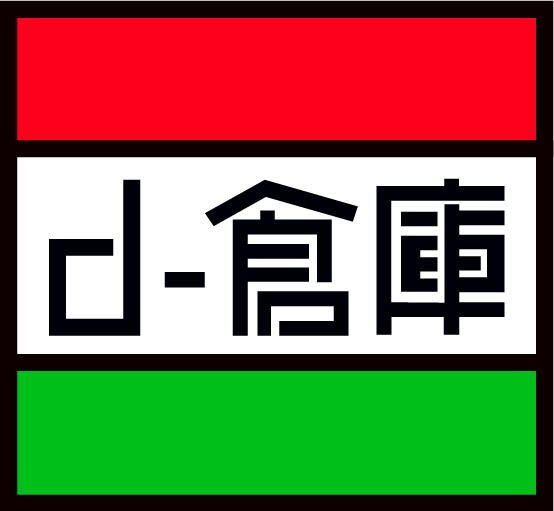聞き手:林慶一(d-倉庫)
――まず中川さんのダンスの来歴について教えてください。
最初に踊りを習ったのは、バレエで。習い始めた理由は、姉が習っていたからという、よくあるやつです。
――それは何歳からですか。
3歳ですね。そのあと、確か4歳くらいの時に日本舞踊を始めました。バレエより、日本舞踊を始めた理由をよく聞かれるんですけど、結構単純で。小さい頃時代劇が好きで、母に「時代劇に出たい!」って言ったら、数日後連れていかれたところが日本舞踊の稽古場だったんです。和装はするものの、刀は持たず、闘いもせず、途中で「これ踊りだよな?」と思いつつも何となく続けていました。身体を動かすのは好きだったので。日本舞踊とバレエをやっていたというと、小さい頃からこの道を目指していたみたいですけど、全然そんなことはなくて。保育園の先生と、心理カウンセラーの人になりたかったです。だから、中学では踊りと関係のないバスケ部に入ったり。
――その時もバレエ、日本舞踊は継続していた。
続けていました。部活もかなりハードだったので、踊りの稽古は休んだり、ふらっと復活したりして、細々と。高校に入り、もう少しダンスしたいなって思って、ダンス部に入りました。元々そんなに活動が盛んではない部活だったんですが、丁度顧問が変わり「全国大会を目指す部活にします」と言われまして。反発した先輩方はみんな辞めていったので、入って数か月でキャプテンになっていました。ダンス未経験の子ばっかりだったので、大会にはヒップホップ部門で出場していましたね。当時は、ストリート系のダンスで全国大会を目指す部活自体が少なかったので、可能性あるかなと。
――ヒップホップのダンスについてはどこから情報を得ていたんですか?
大学のサークルでダンスをやっている方がコーチにく来てれていました。といっても、来てくれる回数はかなり限られていたので、ストリートダンスのステップや身のこなしを教えてもらうというよりは、作品を1曲振付してもらって、大会までにそれをみんなでひたすら練習するって感じでしたね。ダンスに触れる時の感覚としては、現在の活動と遠からずかもしれません。既存のステップや技術を練習したり、応用するというより、もらった振付を通してダンスをしていくっていうか。だから、最初は、ターンやキックをすればバレエになって、手の振りは和風に、なんて具合にしっちゃかめっちゃかでした。バレエや日本舞踊とストリートダンスの違いはどこなんだ、と鏡の前でひたすら研究していましたね。使い分けられるようになれたらいいな、なんて。

――基礎や技術を教えてもらうんじゃなくて振付を貰うことが基本だったんですね。
そうですね。もらった振付をどう踊るかを探して、みんなで揃えていく。とにかく「揃える」「笑顔」が基本でした。そんなこんなで、1年生の終わりには、全国大会にも出場できて。
でも、このダンス部は途中でやめてしまったんですよ。色々と理由はあるんですけど、「この体育館で踊っている先に何が…」といいますか、何かに近づけている気がしないというか。「じゃあ、一体何に近づきたかったの?」って感じですけど。ただ、そんなことを考えていたら、なんで自分は踊ってるんだろう、って。自分で特に選んだつもりはないけど、ずっと隣にあって、当たり前になっていて、自然とダンス中心の自分がいて、なくてはならないと感じているけど、それは錯覚なのではなかろうかと。本当にダンスが必要なのか、ダンスを辞めた自分は何を求めるんだろう、みたいにふと思ったわけなんです。で、演劇に興味を持ちました。結局、舞台は舞台なんですけど。
――演劇の興味はどこから生じたのでしょうか。
舞台全般への興味は、認めたくはないですが、親の影響ですかね。昔からレストランより歌舞伎、遊園地よりミュージカルって感じの家だったので。別にこれといって、専門的な知識はないんですけど。ただ、演劇への興味に限っていうと“映像”とかの方が近いかなぁ…。かなりインドアな人間なので、暇さえあれば、というか、寧ろ学校をサボって、ドラマや映画を観ていました。だから、昔から“観ること”が唯一の娯楽であり、“創ること”はずっと興味の対象だったんだと思います。ただその興味が舞台の方に向かっていったのは、創作の過程が身近だったからということも大きいのでしょうが、家で一人で映像作品を貪るより、反対に劇場に足を運ぶってことが幼少時の私や、インドア派の私からしたら、非日常的で特別なこと、一大イベント、だという感覚があったからかもしれません。
それで、ダンス部を辞めた後、文化祭で一つ作品を創ったんですよ。終演後、拍手を頂いたときに、「この音が生で聞けるのって舞台のいいところだな」と思って、この道に進もうと決心しました。そのまま現場に...って思いもあったんですけど、母に「舞台を創るなら、仲間が必要でしょ?そういう人と出会える場にいきなさい。」と言われ、桜美林大学への進学を希望しました。
大学受験の面接で「映像が好きなのに舞台を選ぶ理由は?」と聞かれ、「表現方法としての舞台がなんたるかは分からないですけど、拍手をもらった時にすごく嬉しかったから。お客さんと創り手が直接伝えられる関係に今は興味を持っている。」と答えました。この感覚が、実は今回の作品(新人シリーズでの受賞作品『有効射程距離圏外』)にも繋がっているんですけど。
――やったことの反応を自分が直に体験できることがよかったと。
そうですね。受動的にならざるを得ない観客が、能動的になる瞬間が素敵だなって。まあ、惰性で拍手をしていることもあるかもしれないんですけど。
――刺激を受けたというコンテンポラリー・ダンスはありますか。
そもそも、大学には演劇専修として入学していて、入学前は、「モダンダンスとコンテンポラリーダンスって、ズボンがボトムスって言うようになった感じと一緒?」ぐらいの知識でしたので、何かを見て、刺激を受けて、始めたってわけではないかもしれません。逆に、入学してからは、同時多発的に色んなものに刺激を受けすぎて、挙げきれません。強いて挙げるなら、初めて“コンテンポラリーダンス”といわれるものを踊らせて頂いたのが、(同大学先輩の)水越朋さんと藤井友美さんのユニット「トマトーズ」の作品だったこと。大学でダンスを教えてくださった木佐貫邦子先生に出会えたこと。この二つはとても大きいです。 なんだか遊び方のわからない遊具を与えられた感じでした。一番驚いたのは、今までダンスをやってきていない方の身体が異様に面白かったことですね。同時に、自分の動きがとてもつまらなく思えて、私が十数年ダンスに費やした時間は何だったんだと、かなり落ち込みました。
――それは何年生の時に?
1年生のときです。その人達の身体は、膝やつま先は伸びないし、肩も上がったままなのに、なんでこんなに面白くて、愛おしくて、美しいんだと。小さい頃からダンスをしてきたことを後悔するくらいに、惹かれました。だから、その時の私の練習は専ら「下手に踊る」でした。バレエや日本舞踊での当たり前と全部反対のことをしてみたり、バスケをする時の身体で踊ってみる、みたいな作業を一人で黙々とやっていました。

――中川さんの活動というのは演劇とダンスの間を揺れながら遍歴してきたという感じがします。そこで中川さんの名義とされている「水中めがね∞」がどういうものか、立ち上げも含めて話してもらえないでしょうか?
「水中めがね∞」という名前自体、元々大した意味はなくて。全ては、後付けで、曖昧で。
「水中めがね∞」の立ち上げは、大学2年生の春です。とにかくなんか創ってみたい、単独公演をやりたいと思い、作品のコンセプトだけ決めて声をかけたんです。団体を立ち上げるというよりか、公演をやるのに団体名が必要だから付けたってだけで。活動が続いていくごとに、どんな団体でいたいか、何をしていきたいかみたいなものが自ずと決まっていったって感じです。やりたいのは、演劇なのか、ダンスなのか。なりたいのは、創作者なのか、演者なのか。まだわからないと後回しにして、すべてを曖昧にすることでしか始められなかったんだと思います。
――現在は「水中めがね∞」はどうなっているのでしょうか。
今は、たぶんダンスに偏っていますね。どこかに偏ることで、他を見つめ直すというか、何かを当たり前にしない作業が自分には必要だなって思って。ただ、今回の作品については違ったかもしれません。たぶん、作品を創り始めた当初の感覚に近いというか。ダンスを一つの象徴として扱い、それを利用して、観客に影響を与えたいなと考えていました。色々な意見をもらったので、再演はまたどうなるか分かりませんが。
――それでは受賞作品について聞いていきたいと思います。まず「有効射程距離圏外」というタイトルは何を示していたのか。
創作にあたって考えていたことは二つあって。一つ目は“作品ミサイル”の射程距離はいかほどか、っていう疑問と不安ですね。劇場という場所で上演される作品が“ミサイル”だったとしたら、その有効射程距離はどこまでなのかなって。 以前、d-倉庫で作品を観たときに舞台奥の扉が開いて、その先には、作品とは全然関係なく日常が流れていたんですよ。お金を払って席に着いている私たち観客の前に、作品の世界観に浸かったダンサーと、こちらをチラッとも見ないチャリンコをこいでいるおばさん。気付いてないのか、興味がないのか、無関係に通り過ぎていくその様を観て、この世界・この空間の小ささを感じずにはいられませんでした。あのおばさんと私はきっと影響し合えない関係であり、自分に影響を及ぼさない者には、人は無関心であることを再認識しました。自分自身、ミサイルだってなんだって、自分に危害が加わらなければ無いのと一緒で。もはや、ミサイルの有効射程距離圏内に自分がいても、実際飛んでこなければ何もしない。 今は、YouTubeやTwitterなど、様々なSNSを使うことで、誰もが簡単に世界に何かを発信することができる。簡単にLIVE配信者にもなれる。一つの映像で一躍有名にもなれる。そんな現代において、劇場という、限られた人数しか入れない箱の中で作品を上演すること、その有効射程距離について考えておくべきだと感じました。壁に囲まれ、外界を遮断したこの世界・この空間をどう捉え、どう活用していきたいのか。同時に、有効射程距離圏外にいる誰かと私はどう向き合いアプローチしていくべきか。
――あえて劇場という閉じられた空間の中でそういった危機感を感じながらパフォーマンスに取り組むというのは、どのような考えがあるのでしょうか?
2点あって、私が劇場を選んだのは最初は単純に観客との距離が近かったからとか、習い事やっていたから、ぐらいのことだったんだけど、やっていく間に劇場に人が集まることに関して、すごく大事にしたいことだなと思って。それは約束じゃないですか。約束した場所に約束した人たちが集まる。それは演者もスタッフもお客さんも。それがみんなにとってすごく特別なこと、良いこと、嬉しいことになってほしいなって思って。しかも劇場って外が見えない分、リーチは短いけれど、逆に秘密基地じゃないけど、うちらがあえて外に閉じているぐらいに思いたいなぁと。なんか会いに行けるアイドルがあんだけ売れるんだから。youtuberにもオフ会をやってほしいという声がすごいあるらしいんですよ。人が直接生で会いたいみたいなことって、変わらずにあるものなんだなぁみたいな。どんどん映像が進んでいく中でも少ないけど絶対的に残っている場所だから絶対廃れないだろう、劇場は、みたいなのがあって。それででもやっている本人、劇場でパフォーマンスしている側はそのリーチの短さをもっと感じるべきだと思って。
| |
|
|
予想もしていない影響を与えられることを人は嫌に感じることが多くて。それを避けるための状況がどんどんと整っていると思う。迷惑が掛けられなくなっているなと思って。 |
――つまり、限られた数の人が集い立ち会うことが出来る特別な場所と出来事を大事に思う。一方でそれを主催するアーティストはその狭さやリーチの短さということを自覚的にやるべきだろうと。もう1つはなんでしょうか。
もう一つは、今って、もしかしたら人に影響を与えることが難しくなっているのかなって。というのも、予想もしていないことを人は嫌がることが多いですよね。それを避けるための状況がどんどんと整って、迷惑が掛けられなくなっているのかな、と。もちろん私も迷惑は掛けられたくないんですけど。意見すれば、価値観を押し付けていると言われ、親しくなろうとすれば何かしらのハラスメントに引っかかる。でも、他人と影響を与え合わずとも、迷惑をかけずとも、生きていける世界になっていて。電車の遅れ、赤ちゃんの泣き声、隣の人の体臭ですら、自分の世界のリズムを崩されたと怒る人がいる。でも、どこかでその日常をぶっ壊してくれる何かを求めていたり…。こんなこと思っちゃいけないと思いつつも、地震とか、台風とか、テロでもいいから、この予定調和を崩してくれって心の片隅で願ってしまう日があったりして。そんなことを望むくらいなら、私たちがその「崩すもの」になれないかなって。そんな大それたことはできないけど、サプライズパーティーよりかは手が凝っていて、テロよりかははるかに素敵なことで。たぶん、分かりやすくカッコ良かったり、共感できるものじゃないから、見てて気持ちが悪いとか、何がしたいのか分からない、迷惑だって言われるかもしれないけど。でも、これは私たちがやるべきことなんじゃないかなと。だから、この劇場で外を遮断している場合ではないんじゃないかとも思ったり。それでも、今ここに集まるのであれば、集まっていただけたのならば、その人たちには迷惑かけてみたいなって。許してもらえるのかなって。これもまたちょっとした実験です。
――劇場という場所の特性を利用して、というか劇場をそういう場所にしたいと。
そうですね。迷惑かけられに、秘密基地に集まる、ってちょっと変かもしれないし、劇場での上演って、一度始まると簡単には停止もできないし、スマホみたいにすぐ閉じることはできないから、その環境自体を暴力的に感じる人もいるかもしれませんが、今どきそんな空間なかなかないから、ちゃんとそれを浮き彫りにしたいなって思いました。

| |
|
|
「「水中めがね∞」の活動目標に私が掲げているものが「人間社会においてのダンスの在り処と在り方を開拓していくこと」 |
――では「水中めがね∞」および中川さんとして、表現で何をしていこうとしているのか?そして何故表現をするのか?
あなたは表現者ですか?と聞かれたら、私は迷わず「はい」とは答えられないです。 ただ、「誰かにとっては当たり前で、直面している問題」だけど、「誰かにとっては、知らない、出会わない、こと・もの・感情」ってたくさんあるじゃないですか。それらを通して、人が感じたり、考えたりする、予感・予兆みたいなものを作れたらいいなって思います。何故それをやりたいのかはわからないですけど、それで、誰かの人生にちょっとでも影響を与えられたりしたら、嬉しいかもしれません。誰かと関わっていたいから、かな。 だから、「水中めがね∞」の活動目標に私が掲げているものが「人間社会においてのダンスの在り処と在り方を開拓していくこと」なんですけど、もしかしたらダンスじゃないかもって思ったりすることはよくあって。というか、私が創るべきなのか、とかもよく迷っちゃって。だから、ジャンルもスタイルもあまり決めすぎず、やっていきたいなと思っています。それが、ダンスじゃなくなっても、舞台じゃなくなっても、もはや作品創作とは言えなくなっても。
 |
中川絢音
幼少時より、クラシックバレエと日本舞踊を踊り育ち、トゥシューズと足袋の狭間で思春期を過ごす。桜美林大学にて木佐貫邦子に出会い、裸足で踊り始める。大学在学中に「水中めがね∞」を立ち上げ創作を開始する。過去に、木佐貫邦子、近藤良平(コンドルズ)、伊藤千枝(珍しいキノコ舞踊団)、「Baobab」、「TABATHA」等の作品に出演。
|
|