【1】序章
従来から、「何が語れるか」、「何を語るべきか」という私の命題は、演劇の未来形を問うひとつの試みなのである。その果敢な試みが、私にとっていわば難解といわれるメタシアターなのである。
現代音楽、現代詩、或いは現代哲学など、およそ「現代」と名のつく芸術や学問は、難解さの代名詞のようである。少なくともそれらの前衛性は、大衆性と相容れない。ここでは、現代のアヴァンギャルドな演劇で、最も難解といわれるハイナー・ミュラーの『ハムレットマシーン』を私的に解析していきたい。
ハイナー・ミュラーの思索の根茎には、「ジル・ドゥルーズ」や「ド・ガタリ」という現代フランスの哲学者の影響が大きい。つまり、古い皮袋に彼の新しい酒は盛りきれない、ということである。たとえば、ハイナー・ミュラーの演劇的根茎は、従来の政治や社会の意味的イメージをもつ「知のシステム」ではなく「メタ演劇の根茎」のような非有機性、非統一性、非全体性、異質性、鎖列性、そして意味の切断性などの特質をもった別次元の「知のシステム」を表すものである。それは、ある意味で、ハイナー・ミュラーの「知のシステム」はドゥルーズの哲学的思索の内部と同じである。つまり、彼の思想と演劇とが哲学的に融合していると言えるのである。
だからこそ、ハイナー・ミュラーの演劇には現代哲学と同様に、隠喩的(メタファー)表現が多い。しかしながら、それにはある批判もある。それはハイデガーの言う「隠喩的なものは、形而上学の内部でしか存在しない」とする形而上学の隠喩性を批判した。それは、ジャック・デリダも隠喩が消滅したところから形而上学が生起するのであり、摩滅した隠喩は、概念の産出によって交代されるとして、演劇における形而上学的隠喩や隠喩の形而上学性(これは、簡単に言うと、演劇を直観によって、純粋化すること)をともに批判しているのである。
しかしながら、哲学的言語における、ハイナー・ミュラーへの隠喩性批判は、摩滅したいわゆる「死んだ隠喩(簡潔に言えば、直観による経験現象)」にのみ妥当するものであり、かえって彼の「生きた隠喩」つまり、「実践的具象的現象」こそが、ミュラーの演劇的言語を蘇らせ、その意味を創造させるのである。
ちなみに、演劇と哲学における隠喩の問題を正面から取り上げて論究したのは、ポール・リクールの『生きた隠喩』である。彼がその「隠喩」を重視するのは、第一に、隠喩は意味論的革新をもたらし、第二に、隠喩はその存在論的効力によって、現実を記述し直し、新たな現実をつくりだすからである。反面、ハイナー・ミュラーは、演劇において、彼の「詩的隠喩(ここでは、演劇の言葉と時間のメタファー)」と「哲学的隠喩(ここでは、個の記憶と集団の記憶のメタファー)」を混同するのではなく、対決させ、呼応させようとしたのである。そのために、彼は晩年、ハイデガー哲学を重視し、彼の現実にある問題に深く沈潜し、思弁的なものと詩的なものとを呼応させようとした。それはまさに彼の師でもあるブレヒトの思索に似ているのである。
さらに、ハイナー・ミュラーの「真のアクチュアリティ」とは「象徴と愚意」における「はかなさ」が異化結合的(つまり、わかりやすく言えば、既成の概念を壊し、新しい歴史認識を記憶として継承し、演劇を新しい文化装置とすることである)ともいえる「歴史の死相」との出会いから出発したのである。また、東ドイツの消滅と西ドイツとの同化によって、その虚偽性は二重の意味でミュラーの「現在」を否定的にさせたのである。
それ故、舞台芸術作品特有の一回性という「いまここにしかない」表象文化において、ハイナー・ミュラーの進歩の概念はカタストロフィーの理念によって基礎づけられているのである。

【2】ハイナー・ミュラーの『ハムレットマシーン』の難解さとは?暗喩の鏡とは?
さて、演出家にとって、あこがれでもあり、恐ろしくもあるハイナー・ミュラーの『ハムレットマシーン』の上演にあたり、なぜ、彼の前衛性が難解なのであるかを解析していきたい。
周知の通り、ハイナー・ミュラーの目指す第一の演劇の意味は、ブレヒトやベケットと同様に、現実を解体すること、そして現実に亀裂を与えることであった。つまり、それは完成されたものとして現実に与えられる外部からの亀裂を意味せず、現実がすでに言語を代表する記号化によって糊塗されている表面をはぎとり、その奥に隠されている亀裂を暴き出すことを意味しているのである。そして、その亀裂こそ、「生きた人間そのもの」の誕生するトポス(場所)なのであり、再生の原点なのである。
つまり、一度生み出されたミュラーの言葉が次の瞬間には、すでに批判の、または否定の対象になっている。いわゆるそれをブレヒト流に言えば「異化作用」(ここでは、簡潔に言えば、演劇において様々な境界を超えたその豊かさと深さは嘘であり、語るものと、語られるものの分裂と憑依という病の体現者こそが均質で空虚な時間ではなく、今によって満たされる時間こそ歴史と現代の関係性をより明確にするのである)なのであるが、この際限のない自己否定の、或いは自己の対象化する主体もまた新たな言葉による説明の対象となるのである。だから、この『ハムレットマシーン』では、いかなるイデオロギーもその対象の外に抜け出すことは出来ない。
したがって、このミュラーの『ハムレットマシーン』での「私」(この戯曲の文章の中で、「私はハムレットだった」の「私」)がたどりつく認識は、構造主義的言語学の立場に立つ、ジャック・ラカンの主張する主体のあり方にきわめて類似したものとなる。
つまり、この「私」の主体がやがてそこに(現実に)配置するものは、それがみずからの姿を消すことによって他者の中に生み出す欠如の形をとった、みずからの欠如なのである。この「私」の消失は、いわば主体がその最初の疎外から、そこに戻るミュラー自身の名において手元に携えながら消失するのである。
『ハムレットマシーン』のその「私」は一体誰なのか、という問がよく言われるが、「私」の意識の中の裂け目としての「私」というミュラー自身の発言は「自我と他者の言語に等しい」とする構造主義とそれに続く思想と類似している。それはマルクス主義の新たな地平における追求と、その可能性の展開を予想させるものである。
ハイナー・ミュラーのこのような立場を、思想的には「ポスト構造主義」と言うべきか、或いは「新マルクス主義」の組み換えの端緒と見るべきかは、今まだ決め難いように思われる。
いずれにしても、ここでは再びハイナー・ミュラーは「人間」を救い出そうとしている点において、アンチヒューマニズムの方法を用いながら、ヒューマニズムの系譜の内に立ち返ろうとしているのである。
しかしながら、ミュラーの言う「この人間とは何か」という問は、このテクストの中で問われているばかりではない。ミュラーは全作品の中で、「人間が絶えまない批評の主体であること。そして言説による言説の対象化の主体である面においてのみ、人間の本質を把握できることを示している」のである。それ故、その意味で、彼の言う革命とは終わりのない自己脱皮をも意味するが、それは言葉の持つ性格そのものなのである。中心の脱落した構造を持ち、ここが満ちることはない。それは個人の、同時に社会に満たされない夢の構造だからである。
【3】ニヒリステックな破壊の衝撃を含んでいる『ハムレットマシーン』
ハイナー・ミュラーはこの「ハムレットマシーン」において、時代精神のトポス(位相或いは場)の中で、鋭く切り結んだ存在としての作品の刻印を残している。それは一般には実に疑問の多い関係性ではあるが、これを未来形の演劇だとは言ってはいない。さまざまな境界を超えた、つまり『ハムレット』を超えた豊かさと深さは嘘である。この作品のコラージュ的手法においては、時代状況に対峙し得る新しい芸術の模索を「新アヴァンギャルド」といわれる超前衛作家ハイナー・ミュラーに求めようとするには無理である。
それはブレヒトの後継者と言われたミュラーが、ますますシェイクスピア劇の改作を試みるのも「ブレヒト疲れ」の風潮のなかでは、シェイクスピアに遡って前進する必要があったからなのだ。つまり、ブレヒトの「素朴な真実」からスタートしたミュラーの劇作試行へのそれは1966年に他界した彼の妻「インゲ・ミュラー」との出会いにも関係している。詩人インゲはハイナーより4才年長で1953年にハイナーと結婚し、のちに『賃金を抑える者』を共作している。彼女の影響がすべての作品に影を落としているのである。
さて、『ハムレットマシーン』のテクストでは、すでに役割の分担がほとんど、消滅している。(ちなみに、これは「ダイヤ・モノ・マルチローグ」といわれている)これらのテクスト内へさらに内的一人称の要素が大幅に混入し、当然、時間や空間を超えたイメージの断片で、より飛躍的、より集中的に綴られているのである。
このような『ハムレットマシーン』のテクストは上演のセリフとしては、もはや一般的コロスや語り手の交替をする手法では十分な効果は発揮し得ないのである。ひと言でいえば、現実の上演術に作者の文学性が先行しているのだが、その作者自身の発言を借りて具象的に表現している。しかしそのイメージの膨大さから何を汲み取って上演するかが鍵となっている。それが難解さの所以なのである。
この作品には、まさに上演する者の感性や肉体性を演劇として膨らませ、しかもそれらを破壊しなければならない困難な作業が待っている。
それに観客と上演者との間に共通の認識と救済の内在的な絆が必要なのである。
ちなみに、デリタを待つまでもなく、ブレヒトもミュラーも、多少の政治的硬直性を含みながらも、言説の虚偽性を見抜いていたのである。つまり、日常の見慣れたものを異常なものとして示す「異化」を目的とするブレヒトやミュラーの演劇活動は、言説による差異化の意識的な応用のひとつだったのである。よって、この作品の「ハムレット」と「オフィーリア」の二項対立は際限のない還元の中に消滅してしまう虚偽性を含んでいるのである。
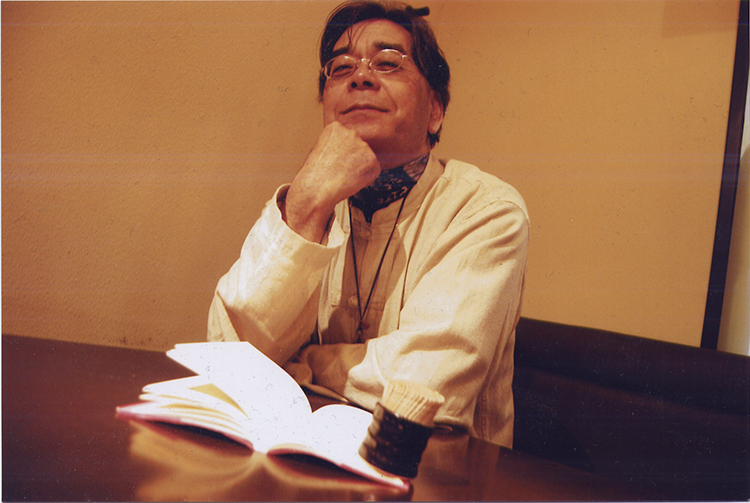
【4】「ハムレットマシーン」を上演するにあたっての演出ノート
ハイナー・ミュラーのこの『ハムレットマシーン』というテクストは、それぞれが書かれた時点で時代の課題や実践的な対話や対決があり、旧来の演劇のジャンルや既成概念を脱構築化しながら、内容も形式も試みの意図もさまざまである。
演劇とは、演劇の言葉と時間、記憶、個々の記憶や集団的記憶、そして歴史の認識として、その記憶を継承し更新する文化装置であるはずなのだ。
そこから引き出せるものは、まだまだ多様で、正解などなく、それがまさに演劇の多様性を豊かにしてくれるのである。
この『ハムレットマシーン』では、私には「なぜ演劇をするのか」という根源的な問いかけがあり、一体、何を試みようとするのか、という自問自答がある。
一般的に、演出家は、皆、過去の死者たちによる「亡霊との対話の方法」を探り出し、その対話の場として演劇を再生させ、現代に蘇生の可能性を探りたいという思いが強いのである。
したがって、私のやってきた、実験演劇集団「風蝕異人街」では、まさに「風蝕」の軌跡である「ベケット―イヨネスコ―ブレヒト―寺山修司」という図式において、ハイナー・ミュラーを内在させ受容してきた私には、この作品はいつも新しく、革新的である。
だが、この作品の断章的性格はしばしば作者の先行と恣意性ゆえに、受容者の私もいつも途方に暮れるのである。
しかし、私の思索プロセスは構造主義の影響を受けて「デリタ、フーコー、ドゥルーズ、ガタリ」などに傾倒し、今は「ポスト構造主義」を演劇に取り入れている。
その場合、ミュラーのメタファー(隠喩)は「ひとつの意味には還元不可能であり、ある種の遮光装置のようにひとつの表象世界が、想像力を解放して、概念では得ることが出来ないラディカルな演劇に転換していった」のである。
だから、私は、この『ハムレットマシーン』では、「ハムレット」を多重的多層化していくことにした。つまり「私はハムレットだった」という「私」を重層的に特定されたものにした。
その具体的表現方法としては、俳優たちをスピーカーとムーバーに分け、「言葉と多層的身体表現」を用いた。つまり、『ハムレットマシーン』での「動詞」をより強調し、可能にするために、俳優の身体をひとつのコード・マシーンとすることで、『ハムレット』を破壊するために書かれたミュラーの「対抗劇」により近づくことが出来るのである。ちなみに、このムーバーとスピーカーに分ける方法論は遠くは能や狂言などで行われており、近くはドイツのダンスカンパニーや日本のSPACの芸術監督、宮城聰氏が使っている。
さて、私たち「風蝕」の実験的表現をするために、私たちは、日頃からひとつのメソッドを取り入れ、しかもピナ・バウシュ(ヴッバタール舞踊団、芸術監督)やオハッド・ナハリン(バットシェバ舞踊団、芸術監督)の思想や方法論を何とか取り入れようとしているのである。よって、「ドイツ、タンツテアター」、特に「ノイエ・タンツ」(ドイツ表現主義)にどれだけ近づけるかが日頃の課題なのである。つまり「ダンス+演劇」を「演劇+ダンス」という、近代劇の文法を打ち破る何かを模索しているのである。
そのために、この作品において、「私」は「ハムレット」を多重化し、そして「オフィーリア」を多重化し、直接対決させたのである。そのあたかも二人芝居のごとく二元的配置は、この『ハムレットマシーン』を先鋭的かつ象徴的構造としてあぶり出してくるのである。
いうまでもなく、現代演劇では、すでに新しい方法論などは開拓しつくされており、ただ新しい組み合わせしかなく、だからこそ、従来の「死滅した劇的構造のなかに想起の爆発力」を身につけるべきだと思うのである。
しかしながら、ハイナー・ミュラー『ハムレットマシーン』がこれからどのように作動していくかは、より前衛的な演出家の新しい方向性を示すものであろう。
そのために巨大なメタファー(暗喩)の鏡として、この作品に一体何が浮びあがってくるのであろうか。
「メタファーは作者より賢い」といったのは誰だったのか、まさにその答えはハイナー・ミュラーの作品の中にドラスティックな形で構築化されている。つまり、日常において既成のものを壊しはじめることから、ハイナー・ミュラーのメタファーは理解することが出来るのである。そして、それを具象化するのが、演劇という舞台芸術なのである。