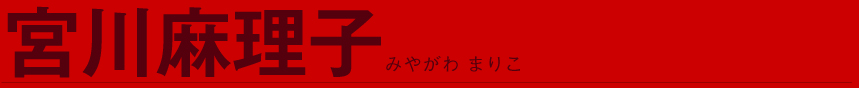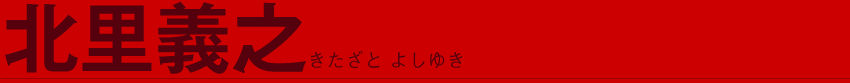index:
受賞者の発表
>新人賞
>オーディエンス賞
審査員による講評
>北里義之
>志賀信夫
>宮川麻理子
>d-倉庫 ホームページへ
受賞者の発表
ダンスがみたい!「新人シリーズ14」審査員による「新人賞」と観客投票による「オーディエンス賞」は下記作品に決定いたしました。
受賞2団体は今夏行われる「ダンスがみたい!18」で受賞作の再演,
来年の「ダンスがみたい!19」で
新作の上演を行います。ご期待ください!!
ダンスがみたい!「新人シリーズ14」新人賞
白井愛咲「コンテナ」
ダンスがみたい!「新人シリーズ14」オーディエンス賞
tantan「傷としお。」
振付・構成・出演:亀頭可奈恵 出演:阿部真理亜,岡安夏音子,佐々木萌衣,田端春花,吉田圭
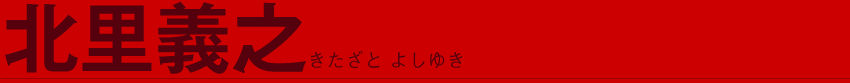
1955年東京生まれ。1980年代に音楽評論家として執筆活動をはじめ,同時代の先鋭的な音楽や即興演奏を含むオルタナティヴな領域を広く扱った。介護生活による数年間のブランクを経て,2012年から関心をダンスの領域に広げ,自身のブログ,『テルプシコール通信』,『ダンスワーク』などで精力的に現場レポートを発表している。音楽関係の著書に『サウンド・アナトミア』(青土社),共著『音の力』(インパクト出版会)など。
|
| |
総論
これだけ幅広いダンス公演を集中的に観て実感するのは,身体のカヴァーする領域はなんと広大であって,端々まで見通しがきく人間などおそらく誰もいないだろうということだった。激しく変遷したここ100年ほどのダンス史が語るのは,数々のローカルな舞踊の大本にある身体を発見し,時間をかけてあらゆる制約から解放していく過程だったのではないか。コンテンポラリー・ダンスとして語られる現在の拡散と多様化は,おそらくそうしたダンスの歴史の必然としてある。解放の道のりが行きつくされているとはいえないだろうが,途中経過の現在でも,自由度や選択肢の多さは若いダンサーを戸惑わせるにじゅうぶんだ。その一方で,こうした身体の広大さにくらべれば,言葉は限定的なものでしかなく,さらに限定的なダンス批評となると,言えること,できることなどたかがしれている。むしろその限定性が,公演へといたるダンサーの作品作りを可能にし,公演のあとでは,意見交換や公演評などを通して出来事としてのダンスを私たちの共有財産にしていくように思われる。
数多くの応募作のなかからd-倉庫が「新人シリーズ」に選出した36のエントリー作品は,例年そうであるように,以上に述べたような身体の現状を,実際のダンスの場において直截に反映したものとなっている。審査員に与えられた役割は,全部の公演を観る(私的に翻訳すれば,ダンスする身体の現状に立ちあう)こと,新人賞を選出する(ダンス環境にパースペクティヴを与える)こと,授賞式で講評を述べる(ダンスによる公共性の創出に参加する)ことの3点。3名の審査員は,観劇の過程で多くの言葉を交わさず,全部の作品が公演されたあとの審査会で,初めてみずからの見解を述べる。結果的には,審査員それぞれのパースペクティヴから個別の作品に対する意見は相違しても,受賞作に関する見解の相違はほとんどなかった。ダンスする身体の多様性にもかかわらず,あるいは,ソロから群舞にいたる創作方法の相違にもかかわらず,受賞作については,じゅうぶんな客観性のある評価ができたと思う。
私の場合,もっぱら音楽の領域で執筆活動してきて,本格的なダンス鑑賞はコンテがとっくに最盛期を過ぎてからだったので,ダンスする身体は最初から拡散し多様化した環境のなかにあったし,ダンスの専門家としてではなく,部外者のパースペクティヴからダンスという出来事を眼差している。そうした事情から,審査にあたっては,ダンスする身体に対して事前にメタレヴェルに立つような審査基準は設定せず,事後的に,ダンスする身体がまぶしく輝いて見えたり,回数を重ねてさらに深く観てみたい作品だったり,言葉を尽くして語るべき重要なテーマを持っていたりする作品をすぐれたものとして評価し,そのなかから候補作を選んだ。そのような作品は,明快なメッセージであらわされていなくても,ダンスする身体を通して,どこかでダンサー固有の現実に触れているように感じる。部分的なものであれば,それらは新人シリーズのいたるところに散在していたが,総合力で新人賞が決定した。
講評
各作品に対する講評は,公演順ではなく,作品スタイルによって分類しなおしたうえでおこなった。最初に全体を「ソロ」と「群舞」に大別したうえで,身体にフォーカスするソロの内側を「道具」の使用がある/なしでわけ(場合によって,衣裳を道具とみなすべきケースもあるように思われるが,ここでは皮膚に近いものとして扱った),関係性を問題にする「群舞」の内側を「演劇的な物語・テーマを持つもの」と「動きやフォーメーションを美的・形式的に追究するもの」とにわけ,さらに「ソロ」と「群舞」の間に,関係性の特殊な形態として「デュオ」の項を立てた。
ソロⅠ(道具なし)
尾花藍子『チブロー』
ステージ中央に座り,シンプルな手の動きからスタート。限定した動きの反復と,最後には,スカートになっていた衣裳をポンチョのように肩まであげ,さらに『千と千尋の神隠し』に登場するカオナシのように頭からかぶるという変化をつけながらのパフォーマンス。坦々と作業をしていくようなダンスだった。過去に数々の道具を使用したソロ公演を観ているせいか,思い切ったいさぎよさと自身への挑戦を感じた。聴こえるか聴こえないかのかすかな音量で,サイン波や水の流れ(に聴こえるSE)が挿入されたが,この音のありようが,今回のソロパフォーマンスに対する尾花の姿勢を示していたように思う。
入月 絢『Thread Clay 東京版』
冒頭,仮面をつけ,真紅のスカートをはいたフランス人形のいでたちでスタッフに運ばれてくる人形ぶりの前半と,長い暗転のあと,長い尻尾をつけた白い衣裳で猫を連想させる動物ぶりをする後半からなる。身体の物質感を前面化する舞踏ならでの手法を再解釈して,ヨーロッパ的な退廃美を描き出したところに個性が感じられた。ピュグマリオン伝説にまでさかのぼり,人間を出外れるふたつの身体を展示する舞踏公演だったが,人形や動物の身ぶりは魅力的でも,むしろ得体の知れない生き物でいたほうが,観客の視線を表層の物質感にとどめておくことができたように思う。
藤井友美『弐の顔』
2015年度の新人シリーズにエントリーした作品『顔』につづく「顔」シリーズの第2弾。顔を見せずにおこなうダンス。前作の暗闇に対して,今回は,変化のない,ほとんどが地明かりのなかで顔を隠すため,長い髪で顔の上半分をおおう奇抜な工夫をして踊った。左腕に巻かれた何本かの黒いアームリングとあわせて,戦闘意欲にあふれた「戦士」のいでたち。黒靴を手にして入ってくる冒頭,雛壇になった観客席を登って扉口から消える幕切れと構成はあったが,壁に衝突したり,太ももをたたいてカツを入れたり,しきりに足を踏み鳴らすなどの身ぶりに即興性が感じられた。素の自分にどこまでのことができるか挑戦する踊りだったと思う。
小谷葉月『Hold』
往来の環境音が響くなか,カジュアルな衣装をつけたダンサーが,自然に歩いている途中で地面から足が離れなくなったり,突然手が後方に引っぱられたり,大きな音に耳をふさいだりという,パントマイムの要素を持った身ぶりを展開していく。同じ身ぶりが,後になって照明が作る四角いスペースのなかで再現するのだが,そこでは見えない牢獄に幽閉される身体がはっきりと表現されていた。小谷のダンスがつねに背後から追われているような切迫感で貫かれていたことが,「痙攣」などの動作も含め,どこからやってくるのか,目に見えない強制的な力に翻弄されつづける「Hold」の世界を,カフカ的なものにしていた。
藍木二朗『Vintage air』
暗いブルーの照明が描き出す暗闇のなか,細い天井からのスポット照明が針の穴を通したように床に落ち,全身白づくめの衣装に身をかためた藍木は,そのなかに立って全身に光を浴びたり,落ちる水を手で受けるように手のひらをかざしたり,円錐になった光の際を手でなぞるなどのしぐさをする。身ぶりの象徴性を印象づけるスタイリッシュなこの場面に,ダンサーの美意識がもっとも強くあらわれたと思う。左手が右手の上腕をつかむ手と手が抗争する場面があったが,前後の動きとの関連性のなさがシーンを構成することはなく,ダンスの内容は,マイムのテクニックを披露することが中心になったと思う。
中村 駿『痕跡』
上手の搬入口から勢いよく飛び出してステージ中央で大きく踊った冒頭は,中村の意欲を直球勝負でぶつけた場面として印象的だった。中心となったのは,会場を移動してゆくダンサーの軌跡が見えない通路を後に残していく構成で,ポイントごとに立ち止まっては,植物らしきものの刺が刺さって手を引っこめたり,手のひらで作ったくらげのような怪物が顔にかぶさろうとするのをもう一方の手で防御したり,通路の途中に立ちはだかる重厚な扉を満身の力で開閉したり,通路上にある障害物をまたいだりと,パントマイムの動きを生の形でつなげていく内容だった。くりかえし登場する頭を抱える場面では,あれこれの身ぶりをダンサーの内面につなげる作業が期待されたが,マイムは表面的な動きだけに終わったと思う。
宮崎あかね『ソコノヒカリ』
茶色い着物を帯なしで羽織った宮崎が,地明かりのなかで上手のホリゾントの壁に寄りかかり,無音のなか,ゆっくりとした手足の動きをつなげていく前半と,ポップスやトラッド風の曲とともに,リズミカルにスイッチする白/赤のライティングが床上に描き出す四角い空間のなかに飛びこんでダンスする後半からなる作品は,タイトルからすると,二種類の「ヒカリ」に相対して踊るという内容だったのだろう。実際のパフォーマンスでは,身体を包みこむ形のないヒカリと,生き物のように動く形のあるヒカリの対照性はうまく際立たず,後半になるにつれて構成が散漫になっていき,そのためダンスの動きも際立たなかったように思う。結果的に,音のない前半の動きだけが強く印象に残ることとなった。
白井愛咲『コンテナ』
ダンサーのからだは,様々な動きでいっぱいになった巨大なコンテナみたいなもの? 個々に自立度の高い細かな動きを丹念に組みあわせ,細部がキラキラと輝くような動きの凝縮文体を作りあげた白井のダンスは,固有のヴィジョンをもった身体へのアプローチとして特筆すべきものだった。結果としてそこにあらわれるのは,坦々としていながらも,関係のない動きの連結が,意味の発生をたえず解体させるという緊張感あふれるダンス。さらに中間部に登場した場面がふるっていて,横に出す手でパーを作り,縦に降ろす手でグーを作り,ときおり顔を左右に振るというダンスらしくない動きで,ボサノバのリズムに合わせるのだか合わせないのだか,どっちつかずのまま千鳥足で会場をフラフラと歩くという,なんとも不可思議な光景だった。この味,狙って出せるものではない。新人賞受賞作。
三橋俊平『be here』
ダンサーが登場する前と踊り終わったあとに,誰もいないステージに地明かりが一瞬入る。これはたぶんダンサーよりもこの場所が主人公であることの表明だろう。「be」「I’m」というネイティヴらしき男女の声につづき,男性が「踊り」「踊る」「ダンスを踊る」「ダンス作品を踊る」と語っていく構成は,テーマである「ここ」を(観客がではなく)ダンサーが外部からのぞきこんでいる効果を与えた。声=意識から引き離され,空白状態で場に置かれた身体とは,このときいったい何者?という問いかけに,ダンサーが応答しようとするステージだったと思う。一方,暗闇のなかの蠢きに観るものの期待を高まらせた冒頭の長い暗転が,照明が入ったあとの身体をかえって平板に見せる結果になったり,右手をあげる,バックで駆けるなどの反復にボキャブラリーの少なさを感じるなど,大きなテーマに応える身体には不足があったと思う。
プロスペクト・テアトル『境界線上にて』
団体名での出演だが,ディディエ・ダブロウスキのソロダンス。上手客席前の床から対角線に走るオレンジの光のなかでのダンスと,下手奥の青い照明のなかで動く影のダンスが交互にあらわれ,最後にふたつのシーンがつなげられたあと,オレンジの光が作る境界線をダンサーが踏み越えて幕になるという構成。この間に,上半身裸で下手に座る背面のダンスや,パンツ一挺で客席前に立ち,リズムに合わせて顔を動かすコミカルな場面が挿入されていく。衣服をひとつずつ脱いでいくプロセスよりも,重量のある身体をようやく引きずっているような鈍重な動きの質が,身体感覚における基層文化の相違を感じさせて興味深かった。
À La Claire『√134』
団体名での出演だが,榑松朝子のソロダンス。冒頭,小さなスポットで下半身を照らし,身体の方向を細かく変える足もとの踊りからスタート。地面に立つだけの極小の場所から次第に光の領域が広がっていくにつれ,踊りも大きくなっていくという明快な展開。光の輪から一歩出てジャンプで戻るとか,高くあげた左手が枯葉のように落ちてくるなど,細かい動きが印象に残る。公演冒頭,暗転のなかの微小音(レコードの擦過音?)にはじまり,電車の音や波の音,機械の響きなど,ノイズや環境音が次々に変化を重ねていくサウンド・モンタージュは,ダンサー自身の手になるものらしいが,それだけ独立して聴くことのできる内容だった。
矢野青剣『Fonte』
長い長い暗転の時間を経てあらわれるのは,足もとを照らすスポットのなかで微動だにしないひとりの男。光の領域が広がって上半身が照らされるようになると,腹筋を動かす奇妙なベリーダンスがはじまる。やがて聞こえる男のうめくような,泣くような声に,不穏な緊張感が高まってゆく。これまで見たことのない風景,ダンスに対して好意的になされる理解などひとたまりもなく破壊してしまうような異様な身体の提示を狙ったものだろう。最後の場面も,ステージをマックスで照明していき,客電を入れて観客席まで明るくしたまま終幕にするなど,思い切った構成を貫いた。ダンスそのものは,意識的に選んだ限られた要素のなかで踊られたと思うが,異様な身体の提示という点では成功したのではないか。
ソロⅡ(道具あり)
阿部友紀子『Walz』
ウインナワルツで踊りながら,途中で真紅の衣装に着替えたり,パイプに水道の蛇口を取りつけたハンガーラックとデュエットしたりしてアクセントをつけた作品。探し物をしながら会場を歩きまわり,観客席の前でなにかを見つけてからダンスに入るという導入部の演出があり,公演の最初と最後に蛇口をひねって水が出ないという場面をくりかえしてまとめる。背の高いハンガーラックは,ダンスのパートナーになったり,そのなかでポーズする額縁になったり,身体を通す扉になるなどさまざまなものに変身するはずのところだったが,ダンサーとものの関係が普段と変わらなかったのでラック以外のものに見えず,イメージが広がっていかないのがもどかしかった。
小山柚香『decomposition』
抽象的なタイトルは,おそらくパフォーマンス空間の解体/再構築をいうのだろう。上手にたくさんの小さな紙,下手に身体より大きな紙を置き,それらに埋まったり乗っかったり包まれたりして踊るダンス。場が身体を枠づける「構造」を組み換える行為としてのダンスといえるだろうが,おそらく紙に頼りすぎたためだろう,ふたつの領域を往復する動きはかえって単調に感じられた。触覚などを利用して,観客の視線を巻きこんでいく工夫が必要と思われる。光は身体を(紙のような)表面/皮膜/二次元的なものにするといえるかもしれない。それに対して,二次元的な紙と身体の関係はどこまでいっても対象操作的で,常識的にしか見えないということだろうか。
深堀絵梨『その時,彼女は笑う』
冒頭,スポットのなかに横たわる深堀の姿は,長い眠りから覚めた朝の訪れを思わせる。起床した彼女は,鼻歌で「ひこうき雲」を歌いながら,上手奥に置かれた黒い椅子を出発点にして踊りはじめる。ダンス公演というより一人芝居というほうがぴったりくるステージ。椅子のうえでさまざまに形をとる場面もあったが,なにより注目されたのは,ひっきりなしに笑っては素に戻る表情の変化が作るリズムを,ダンスの構成要素として取り入れるアイディアだった。はじけるような身体を外に開きながら執拗に笑う演技を退屈させることなく見せたのは力量と思う。最後の場面で,ホリゾントの壁に映る自分の影の前にたたずむ姿にも演劇的なものを感じた。
田村 悟『ルーツ』
サングラスに背広姿というクールなスタイルで登場した田村は,観客の期待をずっこけさせるアヒルのオモチャや小さなピストルを持参,みずから道化役を引き受けて,ネジを巻いてアヒルを床のうえで泳がせたり,ピストルを観客席にむかって発砲したり,アヒルにむかって発砲する場面ではやさしさを見せて銃口を外したり,最後には,カラフルなシャボン玉セットを内ポケットから取り出して吹いたりした。いずれも幼少期の記憶にさかのぼるダンサーの「ルーツ」なのだろう。脇の下に手を置き,脇毛か体臭かを形態模写して指をパアッと開いたり,まっすぐうつ伏せになった姿勢でセクシャルに腰を動かしたりするなど,いささか楽屋受けのネタを反復しつつのダンスだった。
Coquettish Dobermann『舞踏図:米音~爼のうえの。。。。。~』
作・演出の琳果,振付のBenie,パフォーマンスの貞森裕児という分業体制を組んでの舞踏公演は,それ自体が珍しい。舞台転換の時間を長々と引っぱり,横に長い黒幕を,何枚となく上手下手に敷き渡して床の全面をおおっていく導入部は,最後に舞台前面に出たダンサーが黒い幕を足に引っかけて一気にからめとり,奥の壁にかかった黒い梯子を登って二階へと引きあげてゆく幕切れと対になっていて,舞踏手に環境を与える大道具となった黒幕は,ダンスする身体より,ひとつの風景を創出し撤去する行為を見せるものとしてあった。舞踏の動きは,敷き詰められた黒幕に大地の黒土を幻視させるといったイメージに結びいていく。パフォーマンスは観客が抱える記憶の風景に訴えかけるものだったと思う。
鈴木瑛貴『INSIDE』
背後の壁に白抜きで投影される「日本国憲法」の条文と,それを無表情に坦々と読みあげていく男性の声,上手の椅子に腰かけるダンサー,しばらくすると「炭坑節」や「湯島の白梅」にはじまり,AKB48や「アルゴリズム体操」にまでいたる戦後歌謡の数々が憲法条文を読む声に重ねられていく。ともに戦後空間を構成する参照点と呼ぶべきもので,後者は流行歌を成立させるメディア空間の素描ともいえるだろう。モラトリアムの戦後空間を指して「牢獄」と呼ぶことがあるが,『INSIDE』は,そうした現状に対する批判が,顔の下半分を真赤に染めたり,最後に字幕映像のなかにはいって絶叫する行為を示すことで,「牢獄」の内側にありながら,身体を根拠におこなわれうることを示した秀逸な作品だった。
デュオ(群舞の特殊形態として)
E・C・M element『蝸牛』
最初に背中向きでスポットを浴びる石橋成昌,つづいて登場する西嶋久美子の上半身を使った踊りと,それぞれのソロがあったあと,膝のうえに乗ったり,足を手のひらで受けたり,背中に腰かけたり,両脚で胴体を持ちあげて高い高いするなどの工夫をこらして,西嶋の足を床につけずにコンタクトするアクロバティックなダンスが展開した。さらに後半では,歩く西嶋の足を持った石橋が床を這うなど,男性が蝸牛のようになるダンスが展開。ひとつのモチーフをさまざまな動きに変換していく作品だったが,デュオの関係性としては,女性を縁の下で支える男性のやさしさを見るようなドメスティックなステージだった。黒づくめの衣装に身を包んだ石橋の動きは,肉厚で,こってりとして印象的だった。
Motimaru『Twilight』
近藤基弥とティツィアナ・ロンゴの舞踏デュオ。対面して床に座ったふたりがパズルのように足をからませ一体となる。塊になった身体から,四本の手が出たり足が出たりしてシンメトリーの形を描き,やがて身体が離れて上手と下手に転がっていくという作品。タイトルは作品を包みこむ夜明けの雰囲気を示すとともに,プラトンの『饗宴』で語られたような,かつて一体の生き物だった男女の起源を暗示していると思われる。そのような存在をステージに置いてみせる作品のありようは,他者との関係性を描き出すのでもなく,舞踏的な質感を提示するのでもなく,ひとつの神話を語る作品になっていたと思う。そのため,最後の場面で分裂する身体は,ふたつの個体ではなく,ひとつのものの破片にしか見えない。
石井則仁&辻 祐『石泳ぐ魚』
ダンサーの石井が楽器を演奏するとともに,鼓童のメンバーである辻祐のドラミングに振付をするという前代未聞のデュオ・パフォーマンス。演奏家に振付ける試みは,寡聞にしてアイディン・テキャルが振付けた河崎純のケースしか知らないが,こちらはコントラバスのソロ公演だった。つねに新たな表現領域に挑戦する石井の探究精神は称賛に値する。音と踊りの儀式性をめぐり,ふたりの美意識に共通点があって成立した公演だろう。その一方で,石井作品にはコンセプチュアルな側面が前面化する傾向があり,アイディアを血肉化するはずの踊りが,振付けたままをさらう段取りにしか見えないことで,大きな損をしている部分があると思う。
下島さん家の中川さん『屍 シカバネ』
アシスタントのゲンゴロウが下手に控えていたが,ダンスは中川絢音と下島礼紗のデュオで展開。ステージ中央に敷かれた白布のうえで直立不動の姿勢をとる下島に向かい,マイクを手にして立つ中川は,「コンテンポラリーダンスの達人」の条件について説教してから,今度は下島の横に立って観客に観劇の心得を話し終わると,おもむろに「踊れー!」と絶叫しながら,下島の周囲を大暴れに踊って回る。最後には,音楽が止まるたび下島はハリセンでぶたれ,緑の芥子?を口に塗られ,バリカンで頭を刈られる事態にまでいたるが,公演時間が切れて,勝負は最後まで動かなかった下島の勝利に終わるというもの。見方によって無関係でもあれば共犯者でもあるふたりの関係性が,ゲーム的に展開する興味深い作品だった。
群舞Ⅰ(演劇的な物語・テーマを持つもの)
けむりとしずく『暗闇の魔法』
3.11直後の混乱をダンス化した作品の再演。日々の経過とともに当時の記憶が薄れていくなか,作品に封じこめられた時間と感覚を追体験するというのは重要な出来事だった。冒頭でおこなわれるメンバーの自己紹介から,「あの日どこにいたか」という問いをきっかけに作品へと入っていく構成は,意外性があって引きつけられた。交通機関の麻痺から帰宅困難者の群が都会に放り出されるという当時の東京の混乱を,群舞として構成するのはむずかしかったと思うが,原発問題をともなう3.11をいまの時点で扱うのなら,さらなるテーマの掘り下げが加えられるとよかったと思う。
ASMR『坐─すわる─』
ユーモラスな味わいとパンクな感覚で攻めるASMRのダンスは,相反するものが絶妙な匙加減でブレンドされ濃厚な味わいをかもし出すという点で,ダンスへの偏愛を誘うものだ。冒頭の文字映像に映し出される「偏食」「好色」「内弁慶」「小心」「照れ屋」「甘ったれ」などの言葉は,最後に「もっともっと言いたいけれど,みんなあなたのことが好きでした」「お父さんへ タカシ」という落ちで結ばれる。カルタ賭博?の場面や仏像の印を模した手の動きが,女性ならではの曲線美をアピールするセクシーな衣装とアンバランスしてみごとな変態ぶり。機材の不調で二度公演をおこなうが,印象が変わらなかったのは,ASMRそのものに強力な個性が備わっているためだろう。
dreaM.s coM.p TRUE/エムズカムトゥルー『F=G(Mm/r2)』
搬入口の屋根にならべられた7枚の黒板に,白いチョークで方程式らしきものをなぐり書きしていく黒服の人物。かたや,紙の束が斜め一列に並べられた暗いステージでは,団子状になった群舞が形なく蠢き,ふたつは同時並行的に動いていく。黒板を字で満たした黒服は,上手の黒い梯子を下りながら,壁面に貼られた大きな黒い紙にもなぐり書きをしていく。ステージに照明が入ると,群舞はランダムに壁にダッシュしたり,円を描いて回るなどのことをする。明確な形をもたない群舞は,人間というより物質の動きを象徴していたのかもしれない。科学は仮説を立てつづけるが,物質はそれとは無関係に動いていくというような。ほとんどの時間で黒服と群舞は交渉しないが,最後の場面では,まとわりつき,追いすがる群舞から黒服が抜け出し,ステージから去ってゆく。
大塚郁美×吉村早紀『フィニッシュ』
椅子というありきたりの小道具を効果的に配置し,群舞の可能性を最大限に引き出したすぐれたダンス作品が登場した。例えば,ホリゾントの壁に横向きで椅子を並べ,下手の搬入口で踊るソロダンサーが,踊り終わるとオートメーション式に椅子を交代して回っていく場面では,ひとりの横たわるダンサーを下手に配し,ステージ中央が広くあけられていた。あるいは,メンバー全員が三面の壁に面した椅子に座り,お互いを見ずにバラバラに動作する別の場面では,どうしているのか,ある一点で動きがぴったりと合う演出で,人々を操作するシステムの存在を暗示していた。後者の場面でもステージ中央が広くあけられたが,一見するとアンバランスなこの構成は,観客の視線をそれと知らせずに「監視人」として呼びこむ空間装置=パノブティコンとして働いたと思う。システム社会の人間関係を明快な群舞作品にして描き出した手腕を高く評価したい。
tantan『傷としお。』
「マハリクマハリタ」という「魔法使いサリー」の魔法の言葉をキーワードにした意欲的な作品。ひとつのしぐさをくりかえす仲間に近づこうとするメンバーが,あとわずかの近さでガラスの砕ける音に邪魔され,一目散に逃げていくシーンがくり返される最初と最後の場面では,スピード感のある展開のなかに,人間関係の救いがたさやはかなさをのぞかせていた。これと対照的な中間部では,「魔法使いサリー」に出てくる登場人物たちの声をサンプリングしたものにダンサーの動きを配役するという奇想天外なアイディアに驚かされた。声のサンプリングも昭和な家族ドラマもデジャヴ感あふれるものだが,そのことも含め,現代を生身で感じ取っているダンサーたちの感覚がダイレクトに伝わってくる作品だった。振付と構成は亀頭可奈恵。オーディエンス賞受賞作品。
群舞Ⅱ(動きやフォーメーションを美的・形式的に追究するもの)
牟田のどか『ハルシュトラ』
4人が一列に並ぶなか1人が転んで動きはじめる冒頭,下手奥から上手前へ伸びる対角線上に4つ並んだスポットのなかのダンス,上手前のソロと下手奥のトリオによる個と群の対比的なダンスというように,牟田の振付は,ダンスする身体の関係性よりフォーメーションの可能性を追究していくものだと思う。途中で,二人羽織のように重なったデュオが前向きで,次には向かいあって背中を見せながら,後ろのダンサーが前のダンサーの腰にそろそろと手を回してくる場面があったが,こうしたところで描かれるのが,デュオの関係性ではなく観客の視線に対する戦略といえるようなものであるところに,本作の振付のありようがよくあらわれていたと思う。
PegaA『カルマ』
群舞の動きが象徴性を帯びて美と結託していくロマン主義的な作風の作品といったらいいだろうか。作品タイトルは,公演でも使用されたKokiaの曲。輪廻から抜け出せない人間の業を歌う。カルマの物語はもちろんのこと,ホリゾントの壁の真ん中にかけられた黒い梯子がシンプルな装置となって舞台に象徴性が与えられていただけでなく,赤と黒,白というスカートの色が,そのままダンサーの役どころを示していた。こうした内容を表現するため,動きはアブストラクトなものに還元され,ダンサーの生身の関係を物語のなかに溶かしこんで,作品全体で大きなひとつの感情を描き出すような内容になっていたと思う。
住玲衣奈『ヒッポ』
下手前から上手奥へと対角線にならぶ3つのスポットのなかに,そろって下手を向いた野村琴音,坂本佳奈,住玲衣奈の3人が立ち,共演者を振り返ることなくヒップホップ音楽で踊りつづける。野村→住→坂本の順で床に倒れる場面を作り,音とは別に身体だけのリズムを作り出す。前後に登場するこの場面にサンドイッチされる形で,「貧乳」「フリーター」「高学歴」など,乙女の悩み的な文句を書きなぐった紙を3人が身体じゅうに貼りつけ,「せーの」で共演者の紙を剥がしにかかる騎馬戦みたいな場面が挿入される。ふたつの場面に関連性はないが,ゲームの規則を自前で設定して動く点では共通しており,無意識にでも,人間関係の質がゲーム的なものになっている現実が盛りこまれたと思う。
E-project『びぃどろきんぎょ~つきのまにまに』
ダンサー5人が金魚をかたどった赤,白,黒の衣装を身にまとい,色ごとに分かれて踊ったり,全体でフォーメーションしたり,白い椅子のうえでソロを受け渡すなどして踊る。「金魚の記憶がないてるよ」と歌うたまの名曲『らんちう』や,かなかなと鳴く蝉の声,遠くの飛行機の爆音といった懐かしいサウンドを採用してノスタルジーの世界を作った。後半になると,メンバーが口にする「からみ」「色」「世界」といった断片的な言葉でイメージの尻取りをしていく場面が登場,「gashi」という音が「餓死」と「画紙」の連想に分裂していくゲーム的な展開が印象的だった。
久保佳絵『キライキラリ』
ダンス・フォーメーションが,つねに人間関係にまつわるあれこれの感情を暗示しながら展開していくのが特徴の作品。とはいえ,関係のもとになるテーマや物語の説明はないので具体的なことは想像するしかなく,場面によっては,人の配置が単なる風景や大道具の代用にしか見えないこともあった。作品の冒頭,暗闇のなかのふたりの女性がパソコン画面で顔を照らす場面では,画面を見せたがる女と見たがらない女の関係がなぜそうなるのか,演技などでヒントが示されないので想像ができないといった具合。ダンスの側面では,交通整理をしているような,手話をしているような素っ気ない記号的身ぶりや,最後に登場する『Bang Bang』の曲に合わせ,男性が左右の手首を振りつつ歩み去っていく幕切れなどが印象に残った。
ハナトチロル『to』
高瑞貴と松林由華のふたりが,途中で靴をはいたり脱いだりしながら,ふたつの搬入口も使って大きな輪を描きながらステージを走りまわる前半の場面で,シマダタダシは搬入口の屋根にいて,下のふたりが昇ってこられないよう黒い梯子の先で仁王立ちになる。またお互いに手を引っぱりあう動きを多用して,デュオのライバル関係を描きながらダンスしていく後半の場面では,天井から降りたシマダが,ふたりの対極をなすような位置を意識的に動いていく。結局,両者の動きは最後まで交差することがない。両者を無関係のままにした演出上の理由はよくわからないが,結果的に,空間が広く使われることにつながったように思う。関係性を描く女性デュオのダンスに対し,シマダの存在は,無関係であることでパフォーマンスに出来事の同時多発性を招き寄せ,空間を開くことになったものと思われる。
根本紳平『アクネ』
舞台上のダンサーが3対1の組合せをとっていたことは,作品を貫く「仲間はずれ」のテーマと深い関係にある。前半は,ステージ中央を照らすスポットをめぐる攻防が中心となり,ひとりが輪の外でダンスするのと対照的に,輪のなかに入った残りの3人は,背中合わせに座ったり,お互いを輪のなかからはじき出したりする。後半は,搬入口の屋根に登ったひとりが,ライトセーバーのような色とりどりの光の棒を衣装にはさもうとしてボロボロと落としつづけるなか,階下のフロアでは走りまわるトリオのダンスが展開していく。最後の場面では,手前に出た3人にスポットがあたり,1人が立とうとすると別の1人が引き倒すというパターンをくりかえす。この作品でも,1人と3人の間に無関係の関係が生まれ,出来事の同時多発性によって空間が開かれる結果につながった。
三浦建太朗『地中の宴』
公演の冒頭で,白く汚れた衣装を着た男女2組のペアが,街のペンキ屋の体裁で,白い脚立4脚を縦横に活用しながらテンポのよいアクロバチックなダンスを展開する。その後は一転して,部屋の電気を消してテレビを見ているという想定のカップルが登場する。いずれも日常的な風景を非日常へと逸脱させていくようにして群舞が巻き起こる感じ。途中で戻ってくる冒頭のスピーディーな場面では,坂本龍一によるピアノ演奏版『戦場のメリークリスマス』が流れたが,これは表現がありきたりなものに落ち着いてしまうおそれがあり,避けたほうが賢明だったかもしれない。最後は再びTV鑑賞の場面になるが,今度はカップルとTVの間に立った男性が踊り出すところで幕となる。
↑TOP |

批評家,編集者。舞踊,文学,美術などについて『TH叢書』『Danceart』『Dancework』『Invitaion』『図書新聞』などに執筆。舞踊学会員,舞踊批評家協会員世話人。テルプシコール「舞踏新人シリーズ」講評者,「ダンスがみたい!」,アサヒアートスクエア,シアターX 国際舞台芸術祭などの企画・審査,JTAN会員。批評誌『Corpus』(コルプス)責任編集,メールマガジン「maldoror」発行人 。サイト「舞踏批評」主宰。
著書『舞踏家は語る』(近刊,青弓社) 編著『凛として,花として―舞踊の前衛,邦千谷の世界』,『フランス語で広がる世界』,『講談社類語大辞典』
|
| |
総評
今回は,かつての受賞者で他の賞も総なめにしている,川村美紀子の影響を受けた舞台が二つあった。どちらも川村とともに踊っている人が中心だったが,その一つtantan『傷としお。』がオーディエンス賞を受けた。今回の出演者で,もし川村美紀子という名前を知らないなら,コンテンポラリーダンスというジャンルでは,戦えないだろう。
どのジャンルもそうだが,自分の周辺のダンス,舞台ばかり見ていても,新しいものは生まれない。そのため出演者には,ぜひ別の団体の舞台を数多く見てほしい。もちろん来年,川村チルドレン的グループばかりになっても困るのだが,受賞したtantanには,川村とは異なる要素,発想などももちろんあり,他に抜きんでていた。
そして新人賞の白井愛咲『コンテナ』は踊らないダンスに近い,ポストモダンダンス,ノンダンス的な要素と,体一つで立ち,体から踊りをつくりだすということを,非常に丁寧に行って,その力を批評家のみならず多くの観客にも感じさせた。この二組は,今後,新たなダンスへの道を切り開く可能性が十分にある。そして,個人としては,大塚郁美×吉村早紀『フィニッシュ』が次点という評価だ。
今回は男性の出演も目立った。36組のうち9組,男女ペアもあるので,ダンスの舞台としてはかなり多い。玉川大学,大東文化大学からの出演者が目立ち,男性が女性たちを振り付けるという作品もあった。
前回は日本舞踊からの挑戦もあったが,今回はバレエ,モダンダンスのベテランの挑戦もあり,それぞれ自分の殻を破ろうと闘う姿に感動した。1組が怪我で欠場したため,35組すべてがそれぞれ自分自身と闘っていた。コンペティションならではといえる。そして3.11や日本国憲法を扱ったもの,父への追悼を感じさせるものなど,思考や思いが重ねられた作品があったことも特徴的だ。
トヨタ・コレオグラフィー・アワードも今回で終わり,新しいダンスを求める登竜門は,次回15回のこの「ダンスがみたい!新人シリーズ」と,「横浜ダンスコレクション」ほかいくつかのみだ。何度も挑戦する出演者もおり,前年との違いを指摘する熱心な観客もいる。毎回満席となり,小さい劇場だが,12日間の出演者と観客数を合わせれば,毎年延べ1000人近くの人々が「新人シリーズ」を支えてきたことになる。14回,つまり延べでなくても1万人近い人々が関わってきた。
講評会は2時間半にわたったが,自分の舞台の批評だけでなく,他の人にはどんな言葉がかけられているのか,それもきっと参考になるはずだ。ぜひ,読んでみてほしい。これまでは,分量を同じ程度に揃えていたが,今回はそうしなかった。
次回はどんな舞台,新たな身体表現が登場するのか,どう変わるのか。楽しみにしている。
1月13日(水)
尾花藍子
暗転から両手が動く姿に叩く音。フェイドインすると,座って両膝を叩く音。叩きながら立ち上がり,胴体から上を叩き,右を向き,手を回して振る動きに変わる。横向きに直立して両手をそれぞれ回し動かすのだが,その手が見事。バレエダンサーとも違う美的なフォルムを描いて動く。ほぼ無音。上手に移動して中央を向き,手を口に入れて出す音をマイクで拾って会場に弱く響かせる。「手」にこだわった展開は,ダンスともパフォーマンスともつかない領域だが,闇の中のスポットと動きで巧みに見せて魅力的だ。手のこだわりをもう少し拡張して,厚みを出せると,作品として強度を増すように思う。
入月絢
スタッフが人形を中央に運んでくると,それが動き出すという演出で,顔を白い布で覆い右目は黒く縁り表情のない存在として,人形振りだが,マイムの動き。英国で学んだコーポレルマイムが生かされる。音楽も欧州的なロック。長い暗転の後,中央に横たわる白い姿は,実に美しく,布の端を尾のように伸ばし,白龍か蛇の化身の雰囲気でゆっくりと横たわったまま動き,這う。なんとも魅惑的,幻想的という言葉がぴったりで,踊る姿に引き込まれる。最後は立ち上がって静かに暗転していく。物語性と幻想性は感じられたが,それ以上に,身体そのものからくる何か,表現のエネルギーを表すには,強いカタストロフを感じさせるといいのではないか。
牟田のどか
4人のユニゾンで,1人が倒れるという冒頭から,2人が前後になって踊るデュオがおもしろい。上手で1人がソロを踊り,下手で残りがのたうつ場面など,ちょっと癖のある音楽に,それぞれの踊りを強調するなど工夫がみられる。全体としては,踊りの動きを解体,脱構築しておらず,技術はあるのだが,見やすいダンス,既視感のある舞台にとどまったように思う。コンテンポラリーダンス,新しさを感じさせるには,コンセプトを重視し,他にはないものを追求する冒険心が必要だろう。
けむりとしずく
男女2人が上手で「3.11のころは」という自己紹介を語る場面で始まり,下手から男1人女性2人が登場し,それぞれが暴れるように踊る。やがて混じり合い,1人がずっと舞台を走り回り,中央ではダンサーたちが多様に踊るなど,壊れた感を演出していく。おそらく別々の出自,ダンス経験のため,ユニゾンでもそれぞれの個性が出て,いい意味でまとまらない世界,違和感のある世界を生み出し,目が離せない部分が多かった。そしてこれらを,とても自由な感覚で生み出しているところも好感が持てた。
1月14日(木)
ASMR
高野山の男声の声明が響くなか,ホリゾントに光が入ると,正座する仏像のような姿が浮かび上がり,ホリゾントに「小心,甘えっ子」など,マイナスイメージの言葉が次々と写され,仏像と見えた肌色レオタード衣装の女性が,「スーダラ節」でソロを踊る。さらに声明とボレロの音が重なるなかで,両側のアルコーブから同じ衣装の女性が2人出てきて,3人で踊る。横たわったポーズの変化から次第にユニゾンで,途中にはロック,そしてナポリ民謡などが巧みに重ねられて,声明とボレロの通奏音のなかで,踊りが展開する。
最後は元の形に近づき,再び文字が投影される。怠け者といったマイナスの言葉の羅列,そして最後に,それでも大好きでした。お父さんという言葉で閉める。動きは目新しくないが,巧みな音楽と構成,そしてマイナスの言葉たちが実は亡き父へのオマージュであったという落ちは,心に響いた。
藍木二朗
中央に丸いサスペンションのスポットがあたり,そこに手や体をさらして動きを見せる。それが次第に踊りになる。マイムベースの関節を使った動きは,勅使川原三郎の踊りが,マイムの発展形であることを気づかせる。シンセサイザーの音からエレクトリックピアノの音に展開するが,動きのバリエーションは少し少ない。本当はもっとボキャブラリーがあるのではないか。ある意味で,自分を少し縛りすぎているように思える。もっと解放してもいいのではないだろうか。
藤井友美
髪で顔を隠して舞台で暴れるように無音で踊り,そこにジャズが流れると,それが踊りとして見え始める。その間合いや動きの感覚は非常に巧みで,とてもいいダンサーだと感じさせる。後半はパーカッションの音が強く非常にインパクトがあり,そこに負けじと踊りつつ,体をならす。踊りも巧みでエネルギーを感じるが,パーカッションの音のインパクトが残ってしまった印象。その踊りを追求する姿勢はいいのだが,どう見えるかをもう少し考えると,大きく変わってくるように思える。
大塚郁実×吉村早紀
舞台に七ついすを並べて,7人の灰色系衣装の女性が座り,徐々に1人づつずり落ちてきて,あぐらを組むと前に倒れて,海老反りから跳ね上げた両足を組んで倒れうつ伏せになる。無音で淡々と5人が行った途中で暗転。光が入ると激しいロックの音で,左のアルコーブ(へこんだ入口)で1人が暴れて踊り,右のアルコーブに向けて横に並べたいすに5人が座り,下手手前のいすの下に1人がうつ伏せで動かない。暴れた1人が次の1人から押し出されるように踊りやめ最後のいすに進むと,順送りで右のアルコーブに入り,これが繰り返される。激しいスリーピースバンドの音にリズムの音,スプレーを振るカチカチ音のようなものがずらして繰り返されて,違和感を醸し出す。
暗転すると,いすとともにそれぞれが壁向きなどで並び,壁に頭を預けるなど,無意味と思わせる所作を繰り返す。2人ずつなどユニゾンで踊りらしい動きも混ざるが,ダンスを外す,ダンスにするという意図がせめぎ合う。
暗転すると下手手前に三つ並べたいすの下に女性が大の字になり,いすの上に女性が重なる。そこに残った女性たちがいすとともに,重なっていく。全員重なって暗転,と思われた瞬間,女性たちが上手でユニゾンの群舞を1回,そして終わる。
大学生の作品とは思えない完成度に非常に驚いた。最初の並んだいすからずり落ちる女性たちの場面でまず観客を引き込む。「何が起こるのか」,「ダンスなのか」と思わせる感触。さらに暴れるように無手勝流で踊るところと,いすとともに静かな踊らない動きを巧みに構成し,見せる。いすを使いつつ,座ることの否定,いすの上と下など空間を考え,アルコーブの巧みな使い方にも顕れている。そして最後の一瞬のユニゾン。しびれた。
1月15日(金)
阿部友紀子
ウインナワルツのかかるなか,中央奥にアルミのハンガーラック,下に赤いドレス。黒いぴったりした衣装の阿部が上手のアルコーブから走り込み,あわただしくラックについた蛇口から水を飲もうとして,去っていく。これを数回繰り返す。音楽がバッハに代わり,赤いドレスを着て踊り出す。その動きは踊れる優れたダンサーであると感じさせ,伸びやかな動き。ただモダンダンスの定型とも見える。音楽も知られた曲を重ねて,最後に蛇口に向かって,「やっぱり出ない」と一言。これもモダンダンスの定型といえる。ただ,キャリアのあるこの優れたダンサーが「新人シリーズ」にチャレンジしたことは快挙で,その舞台は,若手にも学ぶところがあるはずだ。
小山柚香
下手に重ねたA3くらいの紙の下に大の字になって動き出す。次に上手に広げられた大きい紙の上で動き,踊る。動くことで生じる紙の音を巧みに使ったソロで,最後に中央に来て踊って終わる。そのシンプルな発想と感覚は魅力的だ。ただ音楽が環境音楽的な優しい音で合い過ぎていて,テンションが感じられない。そのコンセプトはよく,優れたダンサーと思える。もっといろんな違和感のある音楽などを試せば,きっとかなり魅力的な作品になるだろう。
小谷葉月
ジーンズにブラウスというシンプルな衣装で,中央に出て踊り動く。四角いサスペンションの明かりの元で踊り,円形の明かりで踊り,音楽も変化するのだが,踊り自体,動き自体は変化が少ない。手を引っ張られるような動きから入るダンスや,痙攣的な動きなどが混ざるが,踊っているという以上の印象を得ることができず,ボキャブラリーの少なさと,素な感覚で即興的に踊ることで,それがそのまま作品になると考えているように思えた。見えない苦闘があるのかもしれないが,それを経たダンスとはあまり思えなかった。
dreaM.s coM.p TRUE
舞台奥は両側にアルコーブ(へこんだ入口)があり,上にも上がれるようになっているが,その上で1人が,相対性理論の公式に基づく数式などを,黒く張られた紙に白いチョークで書いていく。舞台には上手奥から下手手前まで斜めに紙の束が並び,中央部分に男女4人が重なっている。男女はやがて動き出すが,ダンスというより,パフォーマンス的な動き。ただ,バラバラな動きでも一つにまとまるという意識が強く感じられ,上で書く女性との対照で舞台をつくるという感触がある。抽象的なコンセプトを立てて人を集めて実現するという力は感じるが,全体として地味というか,訴えてくるものが弱い。当日パンフも準備して意味がわかるようにはなっているが,ダンスは,説明なしで何かが伝わる作品であってほしい。
1月17日(日)
中村駿
ストリート系出身という印象の踊れるダンサーで,激しい曲で冒頭インパクトを与え,それから静かな曲で心理的表現をしたいということはよくわかる。ただ,マイム的な動きをすると中途半端で荒い。また,心理・感情表現をするには,ストーリーだけでない動機づけをしっかりしないと,伝わらない。それでも,その踊るエネルギーをパワーは注目したいところ。肩胛骨を見せて踊るところは,特に気になった。そのディテールにこだわるところをもっと拡張することでも,新たな意味が生まれる気がする。
E・C・M element
男女のペアで,男が1人登場してサスペンションの光の下で動き,後ろから女が来るところで暗転。次に女が1人で男が後ろから。その後は,男の体に女が足先から乗り,下に降りない,床に足をつけないという動きのバリエーション。これは2年前にも二つのグループが行ったが,一つはもっと巧みに絡み続けて秀逸だった。また,黒い背景に黒い衣装はもったいない。白い衣装ならディテールが伝わるはず。デュオとして「動き」に絞った端正なつくりだが,見せ方を考えれば,もっと伝わるだろう。
深堀絵梨
荒井由美の曲を歌いながら,中央のサスペンションの下で手先から踊り出すところは印象的。そして上手奥のいすに座って,踊りが始まるのだが,少々動きのバリエーションが少なく,曲が変わっても踊りは同じという印象だ。最後は荒井由美で終わり完結したが,場面場面で踊りの変化が必要。ボキャブラリーを増やすか,いまのボキャブラリーでどう見せるかを考えるといいのではないか。
PegaA
5人全員が黒い衣装で,1人赤い布をつけている女性がリーダー的感覚でソロと群舞を構成する。動き自体は新しさのないモダンやジャズダンスの群舞で工夫が必要。技術はあるのだが,オリジナリティが弱い。たぶん周囲のダンスしか見ていない,知らないという感じで,もっといろんな舞台を見て,学んでほしい。総評にも書いたし,他のグループにもいえることだが,同門や同じ傾向のダンスばかり見ていても,そのなかで技術の差を競うのみにとどまってしまう。違うダンスの世界に触れることで,新しいものを生み出す可能性が出てくるはずだ。
1月18日(月)
宮崎あかね
黒いキャミソールパンツに茶色の着物を前をはだけて羽織って,上手奥に座っている。左足の膝から下を水平に上げて,ダンと踏み出して,中央に来て無音で踊るところはかなり印象的。下手に長く延びると,音楽が入り,ピアノにシンプルな女性のシンガーソングライター系で優しい曲にあわせて踊る。はみ出した動き,定型を外そうという動きはあるが,いま一つ響かないのは,音楽の優しさに踊りが合いすぎているからではないか。自分の殻を壊すように,一つの音楽にこだわりすぎず,いろいろ試してみたほうが,観客に訴える可能性が広がるだろう。
田村悟
中央手前におもちゃのアヒルと銃。スーツ姿で後ろ向きで登場して,ダンス的でない動きを展開するところは,期待させる。前を向くとサングラスで,踊りたい意識を押さえた動きを見せるのだが,腋臭が匂うとか,エロっぽく腰を振るとか,笑いをねらった動きを繰り返すところは,内輪受けのみにとどまってしまう。それが後半まで続いて,同じ動きの繰り返しとなってしまい,残念だった。単純に「ウケ」をねらっても多くの観客には通用しないだろう。
白井愛咲
奥のアルコーブの上に顔が出ている。無音のなかで,顔がゆっくり後ろを向いたり,全身が出てきて,頭のみ中に入ったり,奇妙な場面をつくる。それが降りてきて舞台に登場すると,白っぽいブラウスにパンツで,日常態という落差。座って腕の長さで床をはかるような動きから,体の動きを部分部分で自立させて,それによって動きをつくる。しゃがめば左の足を両手で動かすことで,体を動かす。伸ばした足をどうするか。手をどうするか。それぞれをモノ化して動く。踊れる伸びやかな身体を持っていることは,動きで察せられる。踊りを探る,体の部分から踊りをどうつくるか,実験を繰り返す。考えられるさまざまな動きを試し続ける行為は,非常にスリリングだ。
ボサノヴァ的な音楽がかかると,握った左手を上下し,右手を横に伸ばして開いて閉じ,首を左右に振るという三つの動きを,腰でリズムを取りながら繰り返す。右手の動きを止めたり,左手を止めたり,首を止めたりという組合せで,左右に若干円を描くように移動しながら,淡々と男声のミニマルなボサノヴァにあわせて踊る。
この単純なミニマル,ある意味で軽い体操的な動きが,音楽に対して微妙に体でリズムをとっていくところで,ダンスになっている。日常と非日常のまさに狭間だ。日常とは,実は英語にすると「生活」になる。ジョン・ケージの時代,デュシャンの時代から日常=生活とアートという違いが問題になってきた。ケージに発するポストモダンダンスはそれを超える試みだった。そしてノンダンスの時代。それが白井のミニマルな動きにもつながっている。半世紀,いやデュシャンからすれば一世紀近く問われてきたこの問題を,私たちは問い続けている。
tantan
下手の円形の照明の中で1人座ってポーズし行為的な動きをするなかに,1人が奥のアルコーブから登場してゆっくりとくねりながら近づき,照明の輪にさしかかると「ガシャン」とガラスの壊れる音がして逃げていく。次に2人,3人と同じ行為を繰り返す。
次に全員が中央奥に輪のように集まって立っていると,「魔法使いサリー」のアニメソングがちょっと早回しでかかり,アニメの中のせりふが流れると,1人ひとりがキャラクターに応じて体を動かす。アニメの声は物語に依らず,つながらないフレーズの断片だが,それに応じてそれぞれが勝手な動きをするところが,非常におもしろい。するとシューベルト「野バラ」がかかり,1人が思い入れたっぷりに踊り,また「サリー」に戻る。「サリー」のギャグ?から「野バラ」でソロという激しいギャップ。これをメインにしながら,次第の踊りのテンションがあがり,曲も速くなり,群舞,ソロ,デュオなどさまざまに重なる動き。単純なダンスではなく,脱構築的な壊れた動きときれいな動きを交えて踊る。それぞれカラフルな上下の下着で派手に暴れるが,エロスを感じる余裕もないテンポで展開し,圧倒される。見ている人間には最後まで,サリーちゃんの「テクマクマヤコン」が頭に残る。いやあ見事!
川村美紀子のグループメンバーで,川村とデュオなどでも鍛えられている亀頭可奈恵のこの振付作品は,川村の行っている遊びとダンスによる解体作業に重なるものがあるが,アイデアは独自。そして亀頭は川村の「壊れそう」な感覚の一歩手前で,徹底して踊らせる。それでも他のカンパニーの数倍のエネルギーを感じさせて,なんとも圧倒的だ。
1月19日(火)
三橋俊平
冒頭と最後に,人がいない舞台を見せる。暗転のなかで,階段後ろあたりから,息をする声が聞こえて階段から登場かと思うと,舞台に板付き。すると「ダンスとは」といった問いかけの言葉がさまざまに流れるなかで,中央でソロ。一見自分にそれを問うようだが,その言葉を自分に本当に課しているのかは,ダンスに現れているようには見えなかったのは,なんとも残念だった。
Coquettish Doberman
暗いなかで,黒い布の束を舞台で広げて左右一杯に何枚も敷き詰めていく行為から始まる。最後に下手に黒い鯉のぼりをかける。暗転して,アーサー・ブラウン「I put a spell on you」がかかるなかで,暗いなかで寺山的にマッチをすって,その明かりがある間だけ,少し動く。それを三カ所で行った後,階段からゆっくりと落ちてくる。そして舞台で転がって動き,布を体に巻き付けて,アルコーブの中央にかけた階段を布すべてを引き吊りながら登り,アルコーブの上に行き,その穴から,布をひきずりながら,穴の下に落ちていく。
作り出すイメージはおもしろいが,布を巻き付けていくあたりから,ピアノからシンセのちょっと甘い曲になってしまい,前半の緊張感を失う。音楽も最後まで妖しい暗い雰囲気を生かせば,もっとよかったはずだ。
ハナトチロル
黒コートの長身髭の男がアルコーブ上に上り,ゆっくりと踊るともつかない動き。下に黒い衣装の女性2人が登場して,なにげなく歩き,アルコーブに去り,やがて舞台を走る。アルコーブの中も使い,そこに入ると片方のみ靴を履いたり,走り方,方向を変えたり,2人で引っ張りあったりしながら走る。やがて,男が下に降りてきて倒れたりする。そのなかで,上手手前の光に1人が向かうともう1人が阻止するような動き。一連の動きから2人にスポットが当たり,絡んだり離れたりして,ポーズでおわる。おもしろくなりそうなのだけど,そうならない。もう一つ弾けると違ってくるのではないか。
Motimaru
フェイドインすると暗いなか,中央のみにスポットが当たり,肉の塊が見える。徐々に光が入ると長髪の2人が絡み合った形で動かないことがわかる。やがてノイズとシンセサイザーによる音楽とともに徐々に動く。ゆっくりとポーズを変えて,絡み方が変わり,離れそうになって戻り,曲が変わり,徐々に離れていって終わる。
舞踏のモードで,海外(イタリア)ならではの雰囲気のある集中した舞台。シンプルながら,美的にも非常に見せる。美学的に完成されているが,もう一つ強いカタストロフがあると,舞台として強度を増し,観客にもさらに強く訴えるはずだ。
1月21日(木)
住玲衣奈
3人組が上手奥から下手手前に斜めに,三つの円形の照明の中で激しく踊る。三者三様だが,奥の白い髪の女性は川村美紀子に揺らぎ方,技の出し方など,そっくり。使う曲も似ており,激しいダンス。次に,その川村似のダンサーが,紙に「ダンサー」「貧乳」などと書き,それをそれぞれの体に張り付けて,さらに奪い合うゲーム。意外と飽きないが,ひとしきり終わると,また3人のダンス。たぶんこのゲームの中にもダンス性か,あるいはもう一ひねりあると,厚みが出てくる気がする。
石井則仁&辻祐
最初は石井が弓でノイズを出して,太鼓演奏者の辻が踊って,音楽家と踊り手の逆転を演出し,次に石井の頭の後ろにつけた太鼓を辻が叩くという形になる。この頭につけた太鼓を叩くというのは,なんとも奇妙な絵だが,技術は双方ともしっかりある。そして辻のパーカッション,太鼓と石井が踊るというオーソドックスなモードになる。どちらも巧みだが,最初の二つの演出があっても,やはりシンプルな太鼓と舞踏だったという印象が強く残る。
E-project
最初に1人が中央で蠢くように踊り,黒い衣装の女たちが後ろを動くときには,おやと思ったが,次にモダンダンス的な赤と黒,白の衣装になり,踊りの内容も同様でオーソドクスな印象。音楽にたまの「らんちゅう」など,そして言葉遊びなどの工夫はあるが,既視感がある。
そしてやりたいこと全部詰め込んでしまった印象だ。舞台の長さに関わらず,やりたいアイデアを全部入れてつくると,観客には却って単調に見えることを心してほしい。まず全部入れたら,極力そぎ落とし,それぞれの景もメリハリをつける。そこから派生してさらに新しいものを加えて,さらにそぎ落とす。そういう作業を繰り返してほしい。
久保佳絵
手話のような脱構築型な動きは,とてもおもしろい。ただ,後半はそれぞれのソロをはっきり見せてしまって,そのつながり,脈絡がない。そして前のグループと同様に,やりたいことを全部入れた感があって,もっとそぎ落とすべきだろう。いまはビデオもすぐ撮れるのだから,メンバーで見て議論し,さらに外部の人,例えばまったくの素人でも,見せて感想をもらうと,おそらくかなり参考になるはずだ。そうやって,「他者の視点,外部の視点」を知ることは,観客のまなざしを知ることであり,舞台をつくる上で,大切なことだ。
1月22日(金)
鈴木瑛貴
日本国憲法をホリゾントに映し,男の声がゆっくりと朗読するなか,黒い長いワンピースの女性が,下手の光の中でいすに座りソロを踊る。中央に移り踊り続け,途中で朗読が小さくなり激しいパーカッションサウンドが響くなか,激しく踊るが,再び朗読となって,淡々と踊り終わる。
非常に丁寧な踊りで,長い髪に伸びやかな動き,淡々とした踊りには好感が持てる。音楽も多様で工夫がみられる。ただ,2年前に舞踏家笠井叡が「日本国憲法」と題して,セーラー服の女性たちの朗読の元でソロを踊った作品を見ているので,知らないのだろうが,文化庁の賞も受賞した有名な作品で,できれば知ったうえで作品にしてほしかった。それを見ている観客にとっては,捉え方が変わってくるのだから。
根本紳平
茶色い衣装による女性の群舞が基本で,1人離れて踊るなど,動きの中には既存の動きを壊そうと見える部分もある。ただ全体としては,きれいに見せてしまう。
後半で1人がアルコーブの上に上って蛍光色のトーチランプをたくさん体に挟んで踊り,ビジュアルも考えているが,その部分も,残念ながら成功した感じは弱く,アイデアのみにとどまったという印象である。
下島さん家の中川さん
中央に白い布を敷き,おかっぱ,ランニングにパンツの少女っぽい女性が立つ。下手の壁ぎわに男性が1人控える。黄色い髪に白いワンピースの女性が登場し,立ち止まり,動かないポーズをいくつかとる。おかっぱはじっと動かない。黄髪はマイクを持って,コンテンポラリーダンスの作り方を語り出す。
「髪は」,「衣装は」といった定義や,「音は無音」など語った後に,踊りながら,おかっぱに向かって,踊れとわめき出す。文字通り黄色い声を上げて叫びながら,激しく踊りつつ,おかっぱを攻撃する。やがて,脇の男から巨大なハリセンを受け取って,おかっぱを叩きながら「踊れ」と叫ぶ。わさびを受け取っておかっぱの口に擦り付けて攻撃する。そして,電気バリカンを受け取って,おかっぱの髪を刈りはじめる。すると,男があと30秒とカウントし始めて,それとともに終わる。
コンテンポラリーダンスとは,という問いかけを自らに貸しつつ,そのわからなさ,曖昧さを攻撃のエネルギーにして,ぶつけるところはおもしろい。ただ黄色い声で叫ぶのは,極力抑えて,むしろ攻撃のボキャブラリーを増やすなどして,そちらにウエィトを置いたほうがいいように思う。
1月23日(土)
三浦健太朗
白塗りの脚立を持った男女が4人,ペンキのついた作業服的なパンツで踊り出す。長身の三浦を中心に,動きは丁寧に構成された振り付けで,脚立との関係もしっかり使いこなし,舞台になじんでいる。ダンスのエネルギーもテクニックも十分にあって,見せる。しかし,それ以上の何か,「わかる」,「なるほど」という部分を超えたもの,わからない部分があると,コンテンポラリーダンス,アートの領域に入ってくるように思う。
プロスペクト・テアトル
長身でスキンヘッドっぽい外国人の動きは存在感もあって,見せる。それはフランス人のコンテンポラリーと舞踏の中間のように見える。しかししばらく見ていると,そこには踊りというより,動く身体があるのみだ。そして場面と衣装を何度も変えて見せるところも,踊り自体が変わらない。さらに顔の変化で見せるところも甘い。おそらく武道を学び,後にダンスと舞踏をかじったという印象だが,むしろ武道のみを背景に,オリジナルな動きを追求してはどうだろうか。
À La Claire
光の中でふつうの素な身体性を生かして,丁寧なソロを踊ることが,このソロの基本になっている。それはきわめてまじめなスタンスだ。しかし,どこか自己充足しているようにも見える。自分の中を見つめて踊ることが,結果として他者に開かれていく。それは,自分の踊りを見つめるなかで,新たな発見がなければならない。それは改めて,他者を見出すことなのではないか。ソロとともに,自己と他者,踊る自分と見る他者を考え,感じていくと,シンプルなソロが,もっと開かれていくはずだ。
矢野青剣
暗い中のサスペンションの光で,下半身がかろうじて見える。すると,その筋肉に彩られた下半身の腹部が蠢いている。呼気と吐気,筋肉をコントロールして,下腹部の筋肉が動く。その動きは通常目にすることのないものだ。それとともに,声が発せられる。低い男声の苦しげな声。その場面は10分近くも続いただろうか。
次第にからだが動いていく。両手,両足も開き,徐々に動きが開いていく。長い無音から音が静かに入り,ノイズのようになり,それが次第に音楽になって盛り上がっていく。これは,ある種のボレロといえる。よく見ると,明らかにバレエ的身体をもつ矢野の動きが開かれていく。バレエのメソッドや動きを極力排除して,自分の踊りを模索している。その姿勢はすばらしい。おそらく,声を発さないほうがよかったはずだ。というのは,体と動きだけで十分見せる力が,このダンサーには確実にあるのだから。
↑TOP
|
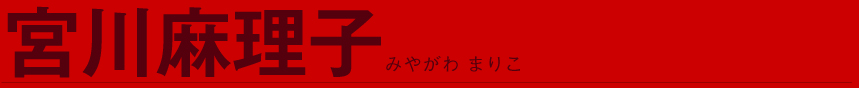
| 日本学術振興会特別研究員。舞踊学会,表象文化論学会会員。東京大学大学院 総合文化研究科にて,大野一雄を中心に舞踏の研究を行う。これまで国内外の 学会で研究成果を発表。並行して,シアターアーツ,artissue,テルプシコー ル通信などに劇評を寄稿。川口隆夫『大野一雄について』への論評で第18回 シアターアーツ賞佳作受賞。 |
| |
ダンスがみたい!新人シリーズ14 審査を終えて
今回は出演者36組(うち一人は怪我で棄権),それぞれ作品の志向も基礎となるテクニックも多様であり,各々が何らかの形ではっとさせるような瞬間を呈し,見応えのあるパフォーマンスが多かった。一体何を基準に審査をするのか,見る側の視点が返り討ちのように審査されているようでもあり,そもそもコンテンポラリーダンスの評価軸とは何かという点を改めて浮き彫りにする,示唆に富んだ時間であった。私にとってコンテンポラリーダンスとは,一言で言えば,今現代に生きている私たちが,自分を取り巻く環境や身体,知覚に対して「身振り」を通して応答すること,と一応言うことができる。もちろんそれは,バレエやモダンダンスなど,伝承されたテクニックを使ってはいけないということではない。これらの振付的遺産に対して,現代の,というよりも自分自身の視点を持ってアプローチすれば,それはコンテンポラリーな視座を持つことになろう。ウィリアム・フォーサイスがバレエのテクニックを土台としながらもそれを更新し続けているように,室伏鴻が舞踏から出発しつつも常にアクチュアルな身体を提示し続けたように,ゼロからの創造でなくともコンテンポラリーダンスであることは可能である。
この観点から,審査基準としては次に述べる点を重視した(これはもちろん私なりのダンスの見方に依拠する一つの評価軸であり,逆にその私の偏った見方を打ち壊すような強烈な作品が出て来て欲しいという期待もあった)。一言でまとめるならば,振付家なりダンサーなりがいかに「身体」を捉え,思考し,そしてその痕跡をどのように表現しているか。できるならそこで提示される「身体」が,今まで一度も見たことがない,人を驚愕させるようなものであってほしいと思う。あるいは,これまでのダンスの見方,日常生活でのものの見方,知覚そのものを歪めうるもの,そしてそれを,身体を通して実践しているもの。とはいえそうした作品は,そうそう登場するものではないというのもまた事実である。(最近では,David Wampachの『Urge』において,カニバリズムを巡って展開される身体から繰り出された欲望のあり方であろうか。これは拒絶的な反応すら引き出した。)よってこれに準ずる基準を以下に設定して審査に臨んだ。まずは振付家の目指すコンセプトが明確であるか。そして25分間の作品として,ドラマトゥルギーがきちんと成立しているか。つまり,テーマに照らし合わせて,振付や構成が破綻していないか。既成のテクニックを使うだけに甘んじず,自ら何かを生み出そうとしているか。あるいは,テクニックに依存するなら,それを追求しているか。そこに見る人を惹き付けるだけの「テクニック」はあるのか(素人を起用した場合,その合理性があるのか。また舞台上にいるダンサーたちに振付家の意図がきちんと伝達されているのか)。
そして今回は問題にしなかったが,劇場で作品を上演するという当たり前の条件へも,疑いの目を向けるべきであろう。資本主義に則って,作品が劇場間を循環するというシステムに乗っかることが,果たしてダンスにおいていいことなのかどうか。コミュニティダンスは,盆踊りは,はたまた路上やクラブで踊るといった,そのようなダンスたちと,劇場で見せるダンスは本当に切り分けられるのだろうか。またそこに優劣は付けられるのだろうか。ダンスの作り手自身が問い続けなければならない問題であろう。
36作品中,審査会の段階で3つを押すことになっていたが,私は白井愛咲とtantanの2組をまず強く押し,それに準じる形で深堀絵梨を推薦した。
白井愛咲 は,自分のコンセプトをしっかりとたて,それを自身の身体で十分に具現化できるだけの能力を持っていた点を評価した。冒頭,舞台の2階部分に頭だけ出ている意表をつく幕開けに始まり,腕や足など体の一部をオブジェに変えつつ,それを制御する白井というダンサー自身も同居する動き,体の一部をメトロノームのように淡々と動かしていく場面など,モノの動きを的確に観察し身体の部位で表象する。解釈を押し付けるのではなく観客の想像力に訴えかける微妙なさじ加減も好感が持てた。今後長編作品に挑む際に,この雰囲気を生かしつつうまく緩急をつけられるかが課題であろう。
tantan の『傷としお』は亀頭可奈恵の演出・振付である。出演者全員のエネルギーの統一,魔法使いサリーの「マハリクマハリタ」の呪文の言葉を効果的に使い,女の子的表象とその裏側を,魔法がとけた後を想起させる構成で効果的に見せた。全体を貫くドラマトゥルギーもしっかりしており,勢いを失わないまま作品として纏め上げた。動き自体はさらに関節や方向など多様に展開できる可能性が残っている。また,「女の子と魔法がとけたその裏側」というジェンダー規範をもう一歩踏み込んで考えられればさらに作品に深みが出るのではないか。
深堀絵梨 は,圧倒的に視線の使い方が巧妙であった。観客を挑発するような眼差しを送ったかと思うと,急に脱力しその視線は裏切られる。正面性を保って客と対峙する前半の表情の変化(作られた笑いと突き放すような無表情の展開)も魅力的であった。惜しいのは後半,視線を外へ投射せずにさらされる身体に変化し,斜めのラインを使用した踊りとなった時,あまり発展がなく単調になってしまったことである。
この他,ソロの作品は,自身の身体から繰り出される動きに対して丁寧にアプローチする試みが多く見られた。ただそれが,コンセプチュアルな作品の中で,徹底した力を持って,説得力のある動きとして,上演の時間すべてを通して展開・貫徹されていたものはなかったように思う。上演順に以下,寸評も付しておく。
13日の 尾花藍子 。ミニマルな動作を,余分なものを削ぎ落として徹底した。ほおの内側をいじくる指や,拍子を打ちながら「手ぼけ」になっていく手など,自分の身体さえも周縁のもの・他者的なものとなってしまうかもしれないという様相を見せ,異質な身体を提示していた。14日の 藍木二朗 は,小さなスポットから始まる見せ方や,ロボット的な関節を起点とした動きなど,随所に工夫が見られた。ただシンプルなだけに,身体の強度や照明との関係性をより洗練させる必要性を感じた。同日の 藤井友美 は,髪の毛で顔を隠し身体に注目を集めた上でのアタックの強い動きや瞬発力,その反動で浮遊する手や上半身の動きなど,コントロールと見せ方がうまい。ただ,ドラマトゥルギー的に全体を通しての緩急が惜しい。15日の 小山柚香 ,紙のように折ることで体重の移動が起こり,体に変化が生じる。紙という素材を通した身体への探究である。ただ全体的にやや単調であり,特に大きな紙の使い方が想定内。小谷葉月 は,冒頭はやや癖があるが普通に歩く動作をして,空間を一人のダンサーとして引き受ける力量を感じさせた。ただ全体を見ても,どんな身体・ダンスを目指しているのかやや判然としない印象。痙攣や爆発的な流れ,日常の身振りの切り替えはうまい。17日 中村駿 。肘から先,手首や指の形作る振りと,ブレークダンス的なテクニックや床でのダイナミックな動き・エネルギーの組み合わせ。大胆さと細やかさの変化が面白かった。ただ,マイムは要練習。また,何かに追われるようなストーリーに頼らず,身体の動きで十分見せられたのではないか。18日 宮崎あかね 。最初の微細な伸び,足を持ち上げる動作は丁寧だが,細かい体重移動に伴う管理が甘い。その後も,体をひねりきる前に次の動作にいってしまうなど,ある身振りが何かを見せる前に終わってしまう。あえてイメージが生じる前に動きをやめているのならば,体の緊張や空間を支配する集中力を拡張すべきであろう。田村悟 「ルーツ」は上記のグループと毛色の違う作品である。微妙なコミカルさや,クスッと笑える演出は笑いを誘った。しかし動きの部分でのテクニックをもう少し磨くべき。テクニックはあっても邪魔にはならない。22日の 鈴木瑛貴 は,日本国憲法を読み上げるナレーションを使用。そこで繰り広げられる身振りには切実さが感じられた。歌謡曲に合わせた全体主義的な身振り,赤く塗られた顔の引きつり,こわばる体など強烈な印象を残した。ただ,選ばれた条文とその前で行われるダンスの繋がりと,そもそも条文を選んだ基準自体の二重のぼんやりとした感じが,ダンス作品としてやや説得力にかける。23日には足もとだけに照明が当って始まるソロが二組。A La Claire は全体として,丁寧さは伝わったがコンセプトが体に落ちきっていない。最初の足先からは,細やかな動きが展開,足の裏の皮膚感覚まで見えその辺は秀逸。矢野青剣 は,バレエ的な体幹がしっかりとした身体で,最初のスポットから腹での呼吸を見せる。しかし後半は動きのバリエーションが展開しきらない。また叫び声は慎重に使わないと,観客が引くだけである。自分の身体を前面に出して勝負する心意気は感じられた。
グループでの作品は,モダンダンス的テクニックに依拠するものが多かった。踊りが物語を伝える媒体になっていて身体への探究が希薄,アンサンブルとしての動きの統一が十分ではない,空間を支配できるだけの圧倒的なテクニックには至っていないなど,共通の疑問点を指摘できる。もちろん,各々「魅せる」ポイントはあった。13日の 牟田のどか ,全体の中で一人が飛び出して踊ったり,斜め,前後と空間を使うフォーメーションの変化は良かった。14日の ASMR は機材トラブルで二度上演することになったが,投射された言葉の有無で,動きが与えるイメージの印象を大きく変えた。15日 阿部友紀子 はモダンダンスのソロを発表。観客が予想できる範囲を超えてシーンを展開できればなお良かった(例えばラックの使用など,工夫の余地が残る)。dreaM.s coM.p TRUE は多様なバックグラウンドを持つダンサーを起用しているにもかかわらず,既存の振付テクニックに依存した部分が目立ち,彼らの身体性が十分に生かしきれていなかったのが惜しまれる。17日の PegaA 。フォーメーションの変化は工夫されており,伝えたい物語は理解できたが,曲の雰囲気への依存度が高すぎる印象。21日 E-project 。冒頭の,起き上がろうとして肩や腕がひねられ,それが回転して倒れるという身振りや,その後同じポーズで登場した4人の統一感から期待はできたが,身体や振り自体への問いかけがその後の展開の中で不在であったのが残念。
この他,グループ作品では演劇的要素の強い作品や,決まったテクニックに依存しない作品も登場した。初日に登場した けむりとしずく は,東日本大震災に対する応答の一つとして特筆に値する。3.11という一言から震災のイメージを共有することで,その後に来る動き,例えば冷静な走りと痙攣的な身振りの並列など,内容に動きが呼応していた点で非常に説得力があった。14日の 大塚郁実×吉村早紀 も,構成面は優れていた。椅子から崩れ落ちるシーンの脱力や,激しく踊る中盤,また椅子の使い方もその場しのぎにならず最後まで効果的。ラストも,終わるかと思わせて外す。全員のテンションや体の使など細かいところに目を配ればさらに力のある作品になろう。19日 ハナトチロル 。男が何かを探ったり,酔っぱらったように動いたりとやや不気味な雰囲気の中,全く異質な女2人の身振りという構図は面白く,また安易に読解できる関係性を明示せずに,うっすらと交差する状態に最後まで徹底したことで逆に想像力を喚起した。ただ全体としてコンセプトが突き抜けておらず,観客が困惑する部分もあった。21日 住玲衣奈 は,川村美紀子的な振付。アタックの強いムーブメントからの余波が体を伝わり,3人の振付はバラバラでも同じテンションを共有。音楽の拍子や歌詞にそれぞれ反応し,音に対して敏感な動きが展開される3人斜めに並んだシーンはあざやかで,動く体を見るカタルシスも感じられた。ただ,構成はもう一ひねりほしい。同日の 久保佳絵 。タブレットで照らされた2人の顔という冒頭は印象に残る。引きずられるような動き,バレエ的な動きなど,様々な要素が混在。ソロのパートも,チャップリンぽいコミカルさや,細かい指や手の動きといった要素で見せる。また,エネルギーを放出せず,ムーブメントの中に留めるような体の使い方に由来する不思議な重さは表現主義的か。ただ,全体を通したドラマトゥルギーが甘いと感じた。22日の根本紳平 は,出演せず振付に徹した。スポットを穴に見立てそこに飛び込もうとしたり,際で止まったりといった演出や,中心から体の外側へと向かうエネルギーなど,ダンス自体には惹き付けられた。また四つん這いで微細に前後に揺れたり,ぷすっという音を入れたりと,細部が光った。ただその効果が全体の中でどのような意味を持つのか伝わりきらなかった。
ところで舞踏はコンテンポラリーダンスの中でどのような位置を持つことになるのか。例えばフランスでは,舞踏家を目指さずともダンス教育プログラムの一環として舞踏を通過していることが多い。そのような点では,舞踏はコンテンポラリーダンスの一角に座を占めている(ちなみに,フランスにおける舞踏の受容,特にコンテンポラリーダンス黎明期における影響については,シルヴィアヌ・パジェスによる著書『Le butô en France』に詳しい)。今回も舞踏を学んだダンサーたちによる作品があった。13日の 入月絢 は,異質なものに変貌し,重厚な世界観を見せる圧倒的なテクニック。ただ,人形振りの時の微妙な身振り(体重移動に伴うわずかな足の動きや手先の震え)がわざとか制御できていないのか,あまりに微妙なラインであったのと,それが生み出す効果が疑問。19日の Coquettish Doberman はタイトルからして「舞踏図」である。出演した貞森の,前屈して膝をまげ,体を縮こめて小幅でわずかに弾みながら動くシーンは,不気味な老婆のような表現で惹き付けられた。冒頭の布を敷くシーンが見せ物として成立しておらず,観客の集中力をそいでしまったのが残念。同日の Motimaru は男女のデュオ。前半の2人の体の組み方は非常に工夫されており,髪の毛で顔を隠していることもあって,次の動きが予想できない生物のよう。手足の伸張も呼吸するように,末端まで集中力が行き届いており体で見せる。音楽がずっとかかっていたが,それよりむしろ2人の呼吸がこの中でどう展開されていくか,エネルギーの循環を感じたかった。21日に登場した石井則仁&辻祐 。儀式的な演出と全体を貫く集中力があり,パフォーマンスとしての完成度は高い。石井だけでなく,奏者の辻も呼吸と身体のテンションを合わせた点が,単なる伴奏にならずに2人で濃厚な世界感を作ることに成功した要因であろう。ただ踊り自体は山海塾の方法論に留まっているように思えた。最終日のプロスペクト・テアトル も舞踏の流れを組んでいる。体の使い方はやや太極拳的でもあり,集中力がある。顔の表情やパーツを使ったダンスは笑いを誘った。ただ,体の動きは全体を通してみるとバリエーションが少なく,空間全体を支配しきれていない。暗転の多さや移動する時の足音など,構成面での詰めの甘さも目立った。
この他,「コンテンポラリーダンス」あるいは踊りそのものに問いを提示した作品として,以下の2組が挙げられる。19日の 三橋俊平 は,「ダンスを見る」「振付を踊る」という行為に対する問いかけを行った。これらがナレーションとして流れ,その前で三橋は,所々過去の振付(体をまげての内側へ肘でアタックするピナ・バウシュ的な振りなど)も体現する。冒頭も,真っ暗な中気配と息が客席後方から聞こえ,得体の知らないものが出てきたように工夫されている。見る/踊るという点に対して多層的にアプローチを組んでいた。22日の 下島さん家の中川さん は,「(踊らない/ダンス的ムーブメント以外にダンスの要素を求める)コンテンポラリーダンス」に対する問題提起である。中央に立ち,何をされても動かない(バリカンで頭を刈られても)女の周りで,「動け!」と叫び,どんどん激しい踊りを展開していくもう一人の女。時間ギリギリまで踊りきって幕。この踊りにもう一工夫欲しかった。
また,近年はヌーボー・シルクと呼ばれるサーカスの要素がコンテンポラリーダンスや演劇にも流入し,新たな脈絡を築いているが,それにやや接近したパフォーマンスも見られた(出演者の側にそのような意識があったかどうかは別として)。17日の E・C・M element は男女2人のデュオ。女が床に接触しないように男の上を歩いたりする辺りは,関かおりのダンサー同士のゆっくりとした,けれども場所を間違えれば怪我をしかねない高度な技術にも似ている。後半,ジャンプやリフトが入ってくる点は,サーカス的な要素がより濃くなった。サーカス的身体をさらに鍛錬するというのは一つの方向性として有効であろう。最終日の 三浦健太郎 は,ダンス的なムーブメントの中でアクロバティックな要素を取り入れた。小さな脚立を多用した演出で,頂上の面積が狭い所に乗って微妙なバランスをとって足を上げたり,振り回した脚立の上をジャンプしたり,金属という固い素材と身体がもたらす緊張感が面白かった。展開や動きのバリエーションにはまだ改善の余地がある。
最後になってしまったが,今回自分の名前を前面に出して責任を負って作品を発表し,外部からの評価を受けようと決意された参加者の皆様に心より敬意をはらいたい。作家になるための第一歩は結局,作品を発表する他はなく,この第一歩を踏み出すか否かには雲泥の差があると思っている。
↑TOP
|
|