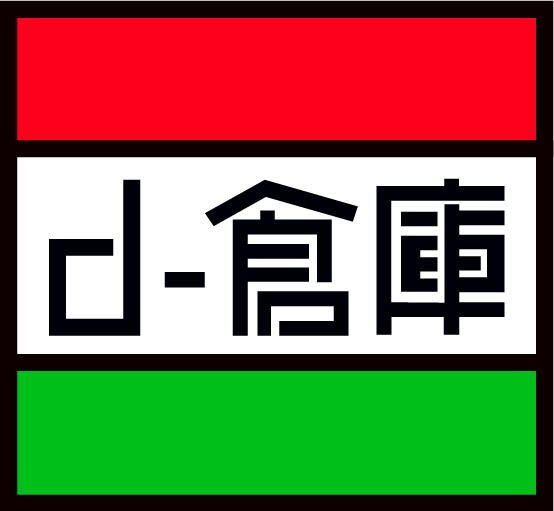今回、初めて審査員を務めたが、まずは“新人”としてこのコンペティションに参加するダンサーが、毎年このように多く存在することに驚くとともに、コンテンポラリーダンス界の今後への希望を抱いた。大学が新人ダンサー、振付家の供給源になっているようだが、同時に中堅、ベテランと思しき人まで参加しているのは好ましい。全ての参加者の意欲と健闘に、また10日間に及ぶ上演と講評会・授賞式を支えたスタッフに拍手を送りたい。
まず、全体的な印象として、グループ名や作品タイトルを一見して、首を捻るものが少なくなかった。既存のモダンダンスや舞踏などとは一線を画したいのだろうが、奇をてらった意味不明なものも多く、積極的に意味性を付与しない目的であるにしても、言葉の選択と文字を配列した時のセンス、説得力が必要だろう。タイトルで説明する必要はないが、観客が作品を観て納得できるものであってほしい。
次に作品の構成について。25分という尺をワンシーンで構成するのは難しいため、いくつかのシーンで構成していくことになる。物語なりプロットが明確な作品であれば、おのずと構成も決まってくるが、抽象的な作品が多いコンテンポラリーダンスではそうはいかない。シーンを積み重ねていくうえで、断絶したいのか、切り替えたいのか、連続性を持たせたいのか。単に目新しさや奇をてらうだけではなく、「何故か?」を突き詰めなければ作品として構築されていかないだろう。そのうえで、どのようにシーンを切り替えるか、関連性を持たせるかの技術が必要となる。暗転の使い方、音楽の切り替え、間の取り方等々、多様なダンス作品や演劇作品、映画などを見て研究し、その中から自分たちのダンス空間、身体による表現に相応しい方法と技術を獲得してほしい。 また、ダンスである以上はもっと身体と真摯に向き合い、強く、繊細に鍛えてほしい。既存のダンスや様式を用いるのはまったく構わないし、自分なりのトレーニングを探すのでもよい。コンセプトからダンスを創るだけでなく、日々からだに向き合うことから発想を得、からだの内と外を動かしながらアイデアを磨き、可能性を広げたうえで、取捨選択していってほしい。ダンスの動き以外に、言葉(発語)を用いるものが多かったが、ダンスの補完としてではない用い方をさらに探求してほしい。25分間の作品を観客の前で上演するためには、それなりの時間を投じる覚悟と責任がある。本番はゲネでもリハーサルでもない。模索はスタジオでからだと頭を酷使してすませてから、本番に臨んでほしい。準備不足を、荒々しい大仰な動き(強い動きではない)や大声、笑いでねじ伏せようとしてはならない。
なんとなく説教臭くなってしまったが、以上の点は、そのまま私の評価に跳ね返っている。
審査の過程で、作品の構成力と批評性、発想のオリジナリティ、身体性、パフォーマンスとしての完成度などを重視した。現在の日本におけるコンテンポラリーダンス、というコンテクストを鑑みながら、この短い歴史の中で今回出演したダンサー、振付家たちの、コンペティション時における作品の出来と将来性を期待して選択した。 以下、注目したもののみをあげる。
Von・noズ「不在をうめる」
作品が始まった途端に、自分たちの世界観を動き、衣装、照明、音楽を総合的に用いて表現することができていた。イメージが先行しがちな現代のコンテンポラリーダンス界にあって、ややオーソドックスかもしれないが確かな技量を感じた。荒い動きであっても、身体が鍛えられているため雑にならない。ダンスの各要素を統合して一つの作品を創る完成度を高く評価した。
スッポンザル「鼈」
上演機会が多いためか、パフォーマンスとしての完成度が高い。鍛えられた身体による明瞭な動きに説得力があるが、それは反面、動きの強度に頼る危険性もある。与えられた空間をいかに使うか、照明、音楽、衣装をいかに絡ませるか、今後に期待できる。
チーム・チープロ「皇居ランニングマン」
作品に社会と歴史に対する批評性があるのは、日本のコンテンポラリーダンスでは珍しい。ダンスと映像を用いる手法がシニカル、ユーモラスであり、映像には手描きのイラストも用いるなどアナログ感も絶妙。古い世代としては、ホイチョイ・プロダクションによる深夜テレビ番組「カノッサの屈辱」に通じるセンスを思い出して楽しめた。ダンスではない動きを用いてダンスとして提示すること、そのコンセプトは良いが、そのためにはさらなる説得力がほしい。
天野絵美「麹」
テーマに沿った動きを用いた作品の構成に長けている。独自の動きもあり、パフォーマンスとしてもまとまっているが、ダンス作品としての枠からはみ出すような挑戦もほしい。顏の表情が強いが、からだの表情も研究してほしい。
その他、恵まれた身体能力で際立っていたのが、本間愛良「茶をひくほど暇な女」、大橋武司「Piano Trio」。バレエ、新体操で鍛えられた身体の癖やボキャブラリーを活かすのは構わない。そこからスタートしてステレオタイプを脱し、自らの身体性の箍から飛躍して、さらに作品を磨いてほしい。
作品のテーマとダンスがうまく重なり、独自の世界観を構築していたのが三橋俊平「BPM-Rebuild-」。舞台での居方、観客とのインタラクションを活かしたパフォーマンスで個性を生かした作品に仕上がっていたのは、深堀絵梨「Living」、トロリテケロリ「人魚シンフォニー」。舞踏の身体の濃密なプレゼンスを見せたのが有代麻里絵「毎朝数千の天使を殺してから―薄明―」。徐々に衣服を脱ぎながら歩くことから走ることへ変わっていく、というワンテーマを突き詰めた後藤茂「R」は、疲れてあえぐように走る身体の動きがダンスになる瞬間があって注目したが、その後を蛇足としないための構成力がほしい。山本和馬「枯れた首」、宮崎あかね「マリー」は自分のスタイルが確立しており明確。それを疑い、壊すことからさらに先へ進みたい。一方で、ベテランのLU LA LA DANCE(阿部友紀子)の「『蘇』~ソ~」は、確立した自分のダンスを壊そうとする潔さに好感が持てるが、次回は自身の振付でそれに挑戦するのもよいだろう。グループの共同作業で熟考の跡が現れていたのが、茎「At Last」、横山八枝子「ICARE」。このめ「たゆたゆ」も前半はグループでの空間の使い方が巧みで緊張感を保っていたが、後半の展開がやや中途半端だったのはもったいない。
それ以外は講評会で話したので割愛するが、ソロ、デュオ、グループなどそれぞれの特性と長所を活かした作品創りを、それぞれに期待する。既存の価値観を疑いつつ、過去を謙虚に学び、日々からだと向き合いながら、同時に獲得したものを取捨選択して、これからもコンテンポラリーダンスに挑み続けてほしい。

稲田奈緒美 (舞踊研究・評論)
幼少よりバレエを習い始め、様々なジャンルのダンスを経験する。早稲田大学第一文学部卒業後、社会人を経て、早稲田大学大学院文学研究科修士課程、後期博士課程に進む。博士(文学)。桜美林大学芸術文化学群演劇ダンス専修准教授。バレエ、コンテンポラリーダンス、舞踏、コミュニティダンス、アートマネジメントなど理論と実践を結びつけた研究、評論、教育に携わっている。著書に『土方巽 絶後の身体』(2008)他。
>back
|