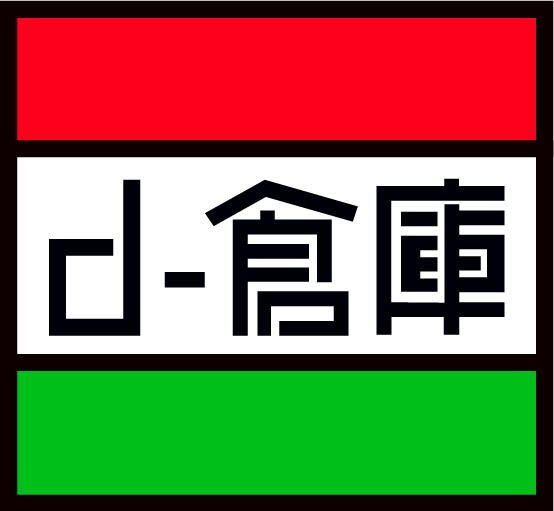「ダンスがみたい!新人シリーズ」は、振付家賞ともダンサー賞とも作品賞とも決められているわけではない。しかし賞を出すのは「応募者」に対してということになるので、かなり振付賞に近い視点から審査した……と講評会では述べたのだが、今自分のノートを見返してみると、振付と実演をあわせた総合力を見ていた、という方がより適切なように思える。どのような出演者・振付家・スタッフを選ぶかも演出のうちという意味では、総合演出力、と称するのが良いかもしれない。
作品と観客の一回性の出会いをよりどころとするダンス、しかも統一的なテクニックや価値基準を持たないものを、いかに「審査」するか。たとえばバニョレ国際振付コンクールがランコントル・コレグラフィック・アンテルナショナル・ドゥ・セーヌ=サン=ドニというフェスティバルに形を変えたことからもうかがえるとおり、現代の多様なダンスに対し、暫定的にでも順位をつけるコンペティション形式を当てはめることは妥当なのかという点は、おそらく誰もが感じている悩みであろう。とはいえその一方で、公的助成を得るためには可視的な「実績」が必要になってくる。また賞というひとつの評価が、創作という孤独な作業に向き合うアーティストの活動の励みになることがあるという側面も否めない。なかなかのジレンマである。 昨年との重複になるが、本コンペティションの特徴は、受賞者に対し、受賞作の再演(同年夏)と新作上演(翌年夏)というふたつの機会が約束されることにある。その場かぎりの表彰に終わらせず、2年がかりで支援するこの体制からは、未来を見据え、アーティストの挑戦に伴走しようとする主催側の姿勢がうかがえる。
審査にあたっては、可能なかぎり公平を期すために、以下3つの基準を設けた。
(1)動きや身体性の選択に、一貫する美学を見て取れるか。
(2)作品の構成力があるか。作品のヴィジョンが明確に表れているか。
(3)既存のもの、あるいは自分自身に対する挑戦や批評的まなざしがうかがえるか。
また「新人シリーズ」と名付けられていることに鑑み、今回上演された作品の現時点での完成度もさることながら、そこにうかがえる発展性を重視した。
全体を通して気になった点は、大きく3つある。
第一に、終盤にいきなりユニゾンになる、すなわち同じ振付を皆で踊り出す、という作品が散見されたことが気になった。演出として効果的ならよいが、割と無頓着に使っている例が多いように思えた。皆で踊り、パートに分かれ、またバラバラになって……というパターンは、場合によっては「群舞の構成として手慣れてはいるけれど、それ以上ではない」という印象を抱かせてしまう危険がある。形式は、うまくオチをつけるためにあるのではない。形式こそ、作り手の独創性が出る部分ということを、今一度気に留めてほしいと思う。また、これはソロ作品にも言えることだが、25分という枠組みの中で、静かなところから始めて盛り上がる激しいダンスにまで持っていくのはなかなか難しい。観客の方が、そのテンション変化についていけないということが起こりうるからだ。他者にどのように見えるか、という客観的な視点が求められる。
第二に、空間との関係が弱い作品の多さを残念に思った。特にソロ作品の場合は、どうしても観客の目はダンサーの身体を注視しがちになるため、そこからどのように空間を広げられるかが鍵になる。それはそのまま、作品世界の広がりにもつながるであろう。また、照明の使い方も重要だ。光と影への意識は、「作品世界をどう描くか」のみならず「身体をどう見せるか」という意識にも直結している。
第三に、稽古している身体は強いということを改めて実感した。その人が身体について思い巡らした時間はそのまま舞台に出るもので、積み重ねた身体はそれだけのクオリティを有している。それは、作品をうまく踊ることとは別次元にある。舞台のためのリハーサルや本番、それ以外にその人がどれだけ身体と踊りに向き合う時間を費やしているか。どのような稽古でも構わないが、ひとつ確かなことは、リハーサルや本番はここで言う「稽古」の時間ではない、ということである。何かひとつのものの完成を目指す場で培われるものもあるが、表現する身体の下地を作るのは、日々自分の身体に向き合う地道な時間なのである。
この点に関連して、伝統的なバレエ・ダンス教室に加え、近年は大学教育やワークショップといった場が優勢だが、オープンダンススタジオの系譜と呼ぶべきものが一方にはあり、安定したダンスと振付の技術を持ち、複数のジャンルを踊りこなす人材をこれまでも輩出してきた。そういったダンススタジオ内で継承されている技術や文化が確かにあり、今も育成の場として機能し続けていることを、私たち観客側も今一度省みる必要があるだろう。
以上の基準のもと、私が注目したのは、Von・noズ(13日)、高瑞貴(6日)、三橋俊平(10日)の3作品である。このほか印象に残ったものとしては、天野絵美(6日)、茎(10日)を挙げたい。各作品については、上演順に以下詳述する。
最後に、36作品いずれも渾身の作で、残念ながら受賞に至らなかった中にも素晴らしいもの、記憶に残る瞬間が数多くあったことを改めて記したい。道なき道であろうとも、自らのやりたいこと・信じることを徹底的に突き詰めていった作品にこれからも立ち会いたいと、一観客として切に願う。

1月4日(金)
チーム・チープロ『皇居ランニングマン』
皇居前広場という特殊な「場」で踊れるダンスをテーマにとった、レクチャー・パフォーマンス的作品。場の記憶や制約を逆手に取っていく方法はクレバーで、ダンスという「アート」とランニングという「スポーツ」の境界にアプローチするという点で、ダンス自体に対する批評的視座も獲得している。作品終盤の実演シーンについては、発展形の動きの動機付けが弱く、それまでの流れとやや切断しているように見えてしまった。作品のコンセプトがクリアで強固なので、前半と同じくミニマルでシンプルなステップだけでも十分見せられたかもしれない。また砂利音との関係は、工夫の余地を感じる。
大熊聡美『苺ミルクの妖精になりたい』
作品冒頭、そして作中にも何度か出てくる、極度に緊張した硬直姿勢の強度・気迫は、見る者を強く掴む力がある。客席に対して、警戒あるいは敵意ともとれるような鋭い眼差しを向けていたことは印象的だ。メルヘンチックなタイトルとは裏腹に、描かれるのは全く甘やかではない「苺ミルク」、いつ爆発するかわからない危うく激しいエネルギーを内包した少女の姿。強固な世界観があり、描きたいものへの明確な意思がうかがえる。ただ作品後半、舞台前方の牛乳グラスと後方のウサギのぬいぐるみの間を幾度も往復する場面は、思い入れが先行しすぎているようで、舞台上の演出としては効果的に立ち現れてこなかった。苺を潰した瞬間の劇的インパクトを、その後の場面が凌駕していないのが惜しい。
後藤茂『R』
レトロムーディなシャンソンが流れる中、舞台上を周回しながら少しずつ服を脱いでいく。それに応じて歩きの速度も上がり、最後は全裸で走るところまで。前半の緩慢な展開で、観客側も微細な変化を注視するモードになる。どちらかというと閉ざしていた冒頭、服を脱ぐにつれて身体から緊張が取れていくように見えるのが面白い。しれっと舞台を去ったかと思うと、2階部分に現れ、油を身体中に塗りたくりながらポージング。確かに「見せる」「人前に立つ」身体で、説得力がある。やっていることは非常にシンプルだが、それを貫く強い意思、自分をあえて晒し者にする度胸を感じる。客席からも思わず笑いが出ており、目論見は成功と言えるかもしれない。
粋地獄『Some of Trauma』
主語をもって語る男性(中村)と、匿名的な女性たち6名。語る男と踊る女という構図なのだが、両者の関係がやや不明瞭。また、振付家である中村がひとり「語る男」のポジションに立つことは、力関係が過剰に見えてしまう恐れがある(語る男/踊る女の力関係を意図的に見せた作品例としてはピナ・バウシュ『私と踊って』等)。ダンス的な要素と演劇的な要素の関係を模索している姿勢は評価したい。しかし、物語の筋を全て台詞が引き受けることにより、ダンスが情景描写に還元されてしまっていた。統率のとれた振付構成で、出演しているのも優れたダンサーたちなのだが、それだけに作品の本筋との関わりが見えないとダンスだけが浮いてしまう危険がある。もちろんダンスをひとつの表現ツールとすることは構わないが、ならばそれだけ、ダンスの位置付けを自覚的に定めていく必要があるだろう。
1月5日(土)
ノセミチコ『AND』
一定のリズムを刻む電子音の中、フェイスペイントを施したふたりのダンサーが、時にリズムを分かち、時に重ね合いながら踊る。このすこし無機的な関係を描くのに、揃いのメイクと動きの同質性が効果的に機能していた。舞台両端の小スペースに分かれて、「距離を隔てた呼応関係」を見せる部分は、動きの対応がもう少し明確になると、より面白くなるだろう。それによって、ふたりの関係にも深みが生まれてくるようにも思う。また手を触れ合わせる瞬間は、それまでシンメトリックな関係を築いていた両者が対峙するという意味で非常に象徴的で、照明からしても観客の集中が結晶化する。もっと集中して見せられそうな可能性を感じる。
大橋武司『Piano Trio』
現代音楽に乗せたソロダンス。音の展開に動きの質の変化を対応させているようだが、その変化がやや見えづらい。音に合わせることを意図的に回避しているのかもしれないが、完全に音と拮抗するわけでもないため、微妙に音からずれてしまったような印象を与えてしまい、違和感が残ってしまったのが惜しい。作品中盤の舞台上が一旦空になり、音もなくなる「空白」の場面は、効果的に活かせそうな余地を感じる。後半に入ってすぐの、膝下と腕を中心にした動きは印象に残る。純粋ダンスと、抽象的なエモーションの表現の間で揺れているような感覚を覚えた。
小林菜々『親愛なる午前3時』
無表情でテンションが高いのか低いのかわからない女性3人組が、深夜のぐるぐるした時間を淡々と描き出す。反復される音楽と振付は、深夜特有のなかなか進まない、かと思いきや急に進む、不思議な時間感覚の描写だろうか。反復の用い方は、展開の余地があるように感じる。パッと素明かりに近い照明に変わる「醒め」の瞬間が何度か設けられているが、その落差が現状は少々弱い。また落差という点では、また1人眠り、2人眠り……と「起きている人数」が減っていったときの変化/無変化も見てみたい。それによって、同じ空間にいるのか違う空間にいるのかといった三者の関係性も明確化するのではないだろうか。
宮脇有紀『dräpped into』
身体を非常に丁寧に探求しており、舞台を超えて空間が広がっていくようなポテンシャルを持つ作品。繊細かつ豊かな音がサウンドスケープとして機能しており、宮脇の佇まいの端々からも、思い描かれている「ある風景」があるように見える。ちょっとした目線、意識、動作ひとつで、身体を取り巻く空間内に「不可視の風景」を描き出せるのではないか、という可能性を感じさせた。たとえば、舞台後方の小スペースで、背中向きのまま日常風景のことを語る場面では、観客に語りかけるような台詞と内省的なダンスと間にギャップを感じ、やや唐突な印象。空間を媒介に、踊りと語りを接続させることも可能かもしれない。
1月6日(日)
高瑞貴『隣接』
開場の音楽・照明の時点から舞台に現れ、最前部に佇むことからシームレスに始まる作品。細部までコントロールが行き届いた身体と、静謐でありながら途切れることのない強い集中力で、観客を引き込んでいく。一挙手一投足が洗練されており、空間を生み出し、その中に自分を意識的に位置付けていくような、説得力のある踊り。身体と影の関係を丁寧に探求しており、身体そのものだけでなく、その影や空間全体にも目がいくような作りになっているように感じる。また影との関係は重層的で、ひとつの身体の中にも陰影のコントラストがあること、逆光の演出、背中向きのダンスなどにより身体それ自体も陰陽転じることに気づかされる。地味とも言えるかもしれないところを実直に探求した作品として、好印象であった。
有代麻里絵『毎朝数千の天使を殺してから―薄明―』
「毎朝数千の天使を殺してから」は田村隆一の詩から。カルメンの音楽、ハイヒール、赤い衣装と、女性性を極めて意識的に押し出したモチーフ群。それだけに「どのような像を描き、見せたいのか」「典型的なモチーフとどう向き合うのか」という設定がもうすこし見えてきてほしかった。作品冒頭、舞台後方の壁に張り付くように立ち、客席を見据える際の集中力と存在感は印象的。前半部で強調されていたハイヒールは途中で脱ぎ捨てられるが、その脱ぎ捨てる行為の動機や衝動、脱ぎ捨てた後にしばしば用いられたルルヴェの振り付けとの関係性等が明確に見えてくると、演出としてより効果的になったのではないだろうか。
天野絵美『麹』
ぴったりと身体に沿う黒い衣装を着た男女ふたりが、まるで機械仕掛けのおもちゃのように動く。そのコミカルでシュールな作品のトーンは、石井漠ら日本モダンダンスのパイオニアたちの前衛的感性を思い起こさせる。リズミカルな音とそこから引き出される身体動作の対応関係は非常に豊饒で、動きのひとつひとつにおもわず笑ってしまうような楽しさがあり、人間の身体というひとつの物体が持つ根源的な面白さに気付かされる。ふたりの調和も非常によく取れていて、独自の世界観を強固に体現していた。
黒沼彩葉『「祝典のための音楽」を踊る』
素明かりの中、舞台を踏みしめて直立する演者と観客が向かい合う、期待と緊張と集中が入り混じる静寂を経て、音楽が流れ始める。前半は背中向きで指揮者のようにその場にとどまって、後半は正面向きでより広がりのある踊りを展開する。使用したスパーク「祝典のための音楽」のは壮大な吹奏楽曲で、ダンス——なかでもソロダンス——ではなかなか選ばないだろう。それに果敢に挑み踊りきったこと、ひとつのシンプルなアイディアを力強く突き詰めたことを評価したい。音楽に乗せる箇所と、踊りが音楽のカウンターを果たす箇所の違いがもう少し明確になると、より多層的な表現になるかもしれない。また、全体がきれいな調和のもとにまとまっている作品だが、個人的には熱が入りすぎた指揮者ぐらいの激しさ、「破」の瞬間を見たい気もする。
1月8日(火)
酒井直之『第伍世代』
舞踏、なかでも土方巽が追求した日本人的身体と、自らの世代のつながりをテーマにした作品。自らの立つところ、歴史を顧みるようなアプローチを果敢にとったことは頼もしく、評価したい。しかし、舞踏との距離や、今これを「第伍世代」として取り上げる必然性と現代性、どんな身体を目指しているのかというヴィジョンは、残念ながら見えてこなかった。舞踏の最盛期や土方の活動をメディアを介してしか知らないものとして、その外形的模倣から入るのはひとつの道だが、その場合は、記録映像を用いて徹底的に外形からのアプローチを行った川口隆夫『大野一雄について』のように、コンセプトの強度が求められる。また、2018年は土方記念年(『土方巽と日本人 肉体の叛乱』から50周年)ということもあり、土方や舞踏を題材にとったイベント、フェスティバルが多数開催された。舞踏再考ブームといえる状況なだけに、その中で自分はいかなる立ち位置を取るのか、その立場と距離を明確にすることは重要であろう。現状はモチーフの表れ方がまだ直接的にすぎ、ともすると「舞踏的」な形象の単なる模倣に見えてしまう危険がある。
山本和馬『枯れた首』
細い明かりに照らされながら、首を垂らしたままアイソレーションの効いた微細な動きで見せる冒頭には引き込まれる。ただ、照明からはみ出し過ぎてしまい、見えるべきであろうものが影に隠れてしまうことが度々あったことは惜しい。光の当たり方を計算することで、演出がより効果的に引き立ったのではないか。また終盤のダンスシーンは、それまでの抑制の効いた展開とうまく噛み合っていないように感じた。25分という短い時間の中で、自らのテンションのみならず観客のテンションをそこまで持っていくのはなかなか難しいのかもしれない。
砂色クラゲ『原 シ』
パズルやオセロの駒のように、表へ裏へ向きを変えながら、パタパタとフォーメーションを組み替えていく6人のダンサーたち。何かが連動したり接触したりする瞬間に、ドラマが生まれるのか、淡々と無機的な調子を変わらず貫くのか、その選択がもう少し明確になると、全体としての見え方もクリアになり、構造が一層引き立ってくるかもしれない。また、無駄な動きがやや多く、きっちり止まりきれないダンサーが多い印象だった。図形的に組み変わっていくという構成を考えると、動きの輪郭や軌跡にはブレがない方が望ましい。
本間愛良『茶をひくほど暇な女』
土下座の状態から顔を上げたと思うと煙を吐く、その思わぬ展開に意表を突かれる。一曲使い切りの引用的なダンスシーン(ショーダンス風、バレエ『瀕死の白鳥』風、モダンダンス風)と、秒針音の中での手遊び足遊びのシーンが交互に立ち現れる。前者については、ぬけぬけとやってのける感じは面白いが、ややベタな印象も受けた。だが作者のフォーカスは、どちらかといえば後者にあるのだろう。退屈の描写が巧みで、場末感を醸し出していた。また長い四肢と柔軟な身体を存分に活かしながらも、それが全くいやらしくなく、妙味さえ出ていたことから、自分の個性や強み、見え方を客観的に把握している印象を受ける。作品としては荒削りな部分もあるが、インパクトがあった。
1月9日(水)
堀菜穂『紫陽花の咲く頃に』
リズミカルな音楽が爆音で流れる中強く激しく踊る場面と、クラシックや弾き語りに乗せて踊る叙情的な場面が交互に立ち現れる。その落差がもう少し見えてくると、演出意図もより鮮明になるように感じる。動きの精度が高く、強靭なダンサーであることがうかがえるが、のびやかさに少々欠け、振付をなぞっているように見える箇所があったのが惜しい。あえて抑制しているのだろうか、しかし特にリリカルな部分については振付も叙情的であるため、もう少し変化がほしい気もする。また現状は、紫陽花と雨というモチーフの組みあわせがややクリシェ的にも感じられ、タイトル落ちになってしまう危険もある。作品の展開を通してのイメージの拡張、あるいは転換を見てみたく思った。
望月崇博・酒井大輝『ブラザー』
手書き絵本の読み聞かせに始まり、男性ふたりが、組み技を駆使しながら仲の良い兄弟みたいなやりとりを展開する。楽しい作品で、好青年であろう人柄も感じるのだが、誰に向けて作った作品かという点がいまひとつ見えてこなかった。教育テレビ番組っぽい展開とオチのつけ方からして、子供向けだろうか。体を使ったコミュニケーションということなら、ボケとツッコミのキャラも動きの上で明確になると、ダンスである効果が増すだろう。また、足音のうるささが少々気になった。
深堀絵梨『Living』
ちゃぶ台を持ってうろうろしたり、正座で背中を丸め客席の方を見回したりといった時の佇まいに惹きつけられる。年齢を自在に変化させるような不思議な存在感と、観客の視線を吸引するその佇まいには、例えるなら武元賀寿子のアヤシさに通ずるものを感じる。ちゃぶ台とデュエットの場面は、彼女のパートナーはちゃぶ台ではと思うほどの馴染みを見せた。音楽については、日常の通奏低音としてのクラシック器楽曲、狂いとしての昭和歌謡(ザ・ピーナッツ)という使い分けだろうか。ダンスシーンとシアトリカルなシーンの接続あるいは断絶がもう少し見えてくると、作品としてまとまりが生まれるのではないだろうか。
project.M『Beyond the wall -壁の向こう側-』
作品全体を不穏でダークな雰囲気が覆っており、明確な世界観が打ち出されていた。出演する5人のダンサー(振付の小野を含む)も、それぞれ確かな基礎があり、全員であるひとつの抽象的な世界を立ち上げることに長けているように感じる。きれいにまとまってはいたのだが、作品を構成する個々のパーツ、とりわけコンタクトワークの部分に、既視感を強く感じた。少々段取りのように見えてしまい、作品から浮いて感じたがゆえかもしれない。また、例えばタイトルにもなっている「壁」の表し方も、シンプルでわかりやすい反面、使い古された表現に見えてしまう恐れもある。作品が展開していく過程で表現方法にも変化が見えると、また違う視界がひらけてくるようにも思う。形式、テクニック、コンビネーションの先を見てみたい。
1月10日(木)
このめ『たゆたゆ』
各自定められたルートを繰り返し歩く、縦列に並ぶ等、非常に幾何学的に構成された作品。まるで図形状を移動する点が踊り出したような印象を受ける。ユニゾンや特定のフレーズの反復、あるいは明暗転といった演出上の手法も、このシステマチックな構成の中にぴったりとはまっているため、本作においては効果的に感じる。またダンサー5名が、容姿やキャラクターは不揃いでデコボコながら、ある一定の温度感を共有しているという点も、作品に妙味を添えている。作品後半は、カラフルな照明と、『カリヨン・ダンス』のみんなのうた的なメロディーに乗せた隊列ダンス。暗転を挟み、無音素明かりの中その隊列が続いている様を見せるのは、骨組みがむき出しになるようでシュールだ。コンパクトながら、構成が強固な作品であった。
三橋俊平『BPM-Rebuild』
BPMは、1分あたりのテンポの単位であり心拍数の単位。あるいはまた、ビジネス・プロセス・マネジメントの略でもある。メトロノームのテンポを設定して踊り、その後時計を見ながら1分間脈を測るという流れを3サイクル繰り返す、シンプルだが強度ある構成。回を追うごとに上がるテンポに応じて動きも加速していくが、両者は単純な比例関係にあるわけではなく、動きによって加速度が伸び縮みするので、観客の知覚をも問われるような体験になっていた。踊られるシーケンスは、1、1+2、1+2+3と段階的に長さがのび、積み上がっていくが、最後の4サイクル目は変調。アスリートのようにタフで、質実剛健の踊り。動きの軌跡が非常にクリアで美しく、物語的な展開はないにもかかわらず動きそれ自体にドラマが宿る瞬間があることが印象的であった。
茎『At Last』
ゆっくりと仰向けに倒れていく冒頭シーンに象徴されるように、引き延ばされたような独特の時間が、全編無音で紡がれる。床をつま弾く小さな音を効果的に使っていたことが、強く印象に残る。その浮遊感とぬめりのある動きを見ていると、身体自体が日常のそれからはかけ離れた「異形」へと変化するように思えてくる。個々がなすフォルムと全体がなすフォルムがあり、とりわけ4人の身体がもつれあう後半は、「個体」という概念自体がわからなくなってくる。その意味で、ひとりがその塊から抜け出し歩き去っていく結末は、象徴的だ。身体の異化により優れた効果をあげた作品と言えるだろう。
吉倉咲季『此処』
人形振りをベースにした振付を、非常に正確な身体制御で巧みに遂行する。ただ、正確すぎるゆえか、その先の表現の域まで行ききっていないような印象を受けた。人形振りというツールを使って何を描きたいのかというヴィジョンが、まだ明確には表れてきていないように思う。また、身体のラインを隠す大ぶりの白いシャツという衣装と、動きが描き出すものとの接点が見えづらかった。激しくなる動きに、コントロールを保ちつつも呼吸が乱れていく後半部の展開、そして序盤と終盤で反復される場面の差異または同一性が、鍵となっていくだろうか。
1月12日(土)
小野彩加・中澤陽『フィジカル・カタルシス』
微かな体重移動により、身体を凝視するように仕向ける中澤の冒頭場面。「M・U・S・I・C・・・・・Music」という言葉が、非常に正確なリズムで発される。続いて安定した腰と軸足が際立つ小野の場面。何度か暗転が挟まれるが、それによって景が転換することはなく、淡々と変わらぬ調子で続いていく本作を支配するのは、持続のロジックだろうか。激しく踊りまくる「カタルシス」とは対極からのアプローチを試みる、身体に真正面から向き合った作品であった。
DADADA『Kitsch』
お揃いのパジャマを着た5人の女性ダンサー。全編を通して音に乗せたダンスが展開するが、その音の取り方が非常に細やかであった。特に前半は選曲にも工夫が見られ、掃除機の音を効果音としてではなく音源として用いて踊る演出には意表を突かれた。滑るような軽やか動きを基調としつつも、動きの質にバラエティや抑揚があり、動きのシーケンスを作る技術の高さをうかがわせる。たくさんの手鏡を円形に置き、一種の「ステージ」を作る演出は、光の反射もあって効果的だ。その後の『ひみつのアッコちゃん』に乗せたダンスシーン以降は、少々ありがちな世界観と構成に感じてしまい、作品のコンセプト——戦略的「キッチュ」のあり方——はもう少し練る必要があるかもしれない。作品としては未完成なところも多いが、今後の展開が楽しみである。
トロリテケロリ『人魚シンフォニー』
花嫁衣装のような白いロングドレスでしずしずと現れた冒頭。台詞を発した途端ガラリとキャラクターが一変し、観客の注意を一気にさらう。自分の世界に相手を引き込むパフォーマーとしての迫力——舞台人が持つ根源的な魔力のようなものを感じさせるパフォーマンスで、客席からも笑いを引き出していく。『人魚姫』の物語に則ることが、徹頭徹尾本気かジョークかわからないことが、味と魅力になっている。鯉のぼりの中を這うようにしてくぐる最終場面は、「変化(へんげ)」の過程を想起させた。今回は台詞で持っていった部分が多く、実際それが効果的であったのだが、身振りの面だけに注目しても、ダンスとパントマイムのあわいは、ジャンルを超えた「身体の芸」の領域として、開拓しがいがありそうだと感じる。
窓ぎわの我ら『Masterpiece』
近くもあり遠くもあるようなふたりのダンサーの関係が特異な作品。一方が光の中で踊り、他方が影の中で同じ振付を追いかけるように踊る場面、手の振付がリンクしていく場面等、印象に残る場面が複数ある。作品としては、まだアイディアがうまくまとまりきっていない感もあるが、やりたいことのヴィジョンがあることがうかがえる。ジーンズに色違いの長袖クルーネックシャツという衣装は、作品から鑑みるに少々意外であった。また、メッセージソングである井上陽水『最後のニュース』を最終場面で用いることは、非常に強い意味性を持つ。平成という時代の終わりを象徴しているのだろうか。
1月13日(日)
橋本礼『裸足の街』
コートを小道具に、シアトリカルな身振りで紡いでいく作品。「語る身体」ができている、ということを第一に感じさせた。光と影で何もない舞台に様々な空間を作り出し、光に入る瞬間に空間が変わったように見せる、コートからにょきっと手足を出し、素手素足であることを引き立たせるなど、演出面も行き届いている。ただ、その演出手法やマイム的な身振り、表情の作り方等は、ややクラシカルであるようにも思われる。クラシカルなものを高いクオリティで実行し、しっかりと効果をあげていたことは評価したい。ただ可能ならば、これらの技法を橋本式にさらにアップデートさせた、独自の表現を見てみたい。
宮崎あかね『マリー』
膝を曲げた歩き、胡座、手を打ち合わせるといった身振りの反復、フリンジのついた赤い衣装と目元の赤いフェイスペイント、聖体拝領のパンとぶどう酒を思わせる小道具等、全体に儀式的な色がうかがえる作品で、20分では表しきれなかった壮大な世界観があることを感じさせる。随所に詩的なセリフが挟まれるが、その声の線の細さと、高い集中力で儀式空間を立ち上げていく存在感の「太さ」が、コントラストを生んでいた。なかでも、指の表現の強さが印象に残る。講評会でも指摘があったが、文化的——とりわけ宗教的意味合いを持つモチーフの使用には、意図せぬ衝突を引き起こさないためにも、細心の注意が必要になる。また「食べる/飲む」という象徴的行為が作品の筋にどのように関与するかがもう一歩明確になると、より効果的になるのではないだろうか(食べる場面が象徴的に機能している作品例としては、大橋可也『あなたがここにいてほしい』等)。
Von・noズ『不在をうめる』
LED懐中電灯を巧みに使い、まるでカットチェンジのように次々に「光」と「空間」を切り替えながら踊る冒頭場面で一気に引き込まれる。帽子を目深にかぶり、レトロな女性用スーツのような衣装をまとったふたりは、外貌的にはよく似て見えながらも明らかな差異があり、細かく正確に動く久保と破調の上村、一方がパターンを動き他方がランダムに動く等、対比の作り方がうまい。その久保が、帽子を持ち去る上村に後ろから飛びつく幕切れも印象的。劇場の機構を活かし切った作品であった。道具立てとして用いられていた椅子については、個数、使い方共にやや過剰に感じる部分もあった。この構成力なら、もっと引き算しても十分に成立するのではないか。まだこれから練度を上げていける部分も多いように思うが、とはいえ力のある作品であったことは確か。そして何より、明確なヴィジョンを持ってぶれずに創作を続け、常に新しいことに挑戦する姿勢を評価する。
スッポンザル『鼈』
三点倒立と体育座りが組み合わさった奇妙な造形で始まる冒頭で、掴まれる。その後もダンサーふたりで様々なフィギュアを作っていくのだが、ふたりのバランスが非常によい。両者とも確かな基礎があり、振付の選択にも一貫した美学がうかがえて、完成度が高い。再演を重ねている作品だが、衣装等に工夫を重ねた跡が見られる。作品の外枠のスケール感(作品の長さや舞台サイズ)に、内容的なスケール感がぴったり合致した好例と言えるだろう。長尺の作品を制作する際にどのような発想が出てきて、いかなる展開が生まれるか、期待させるものがある。
1月14日(月祝)
横山八枝子『ICARE』
サウンドホースの音が響く中、ゆっくりと動くヒラトと横山の関係、あるいは一種の恒常状態が描かれる。ふたりが存在した場所には白い痕跡が残っていき、2階部分を照らす青緑の照明が、白味の強い世界に色を添える。観客を等閑に付している印象を受けたが、これは意図的だろうか。ただその場合にしても、身体が内向的にすぎると、自己完結している印象を観客に与える危険性がある。また、前述のふたりと、音を奏でる者として独立して存在する恒吉との関係/無関係が見えづらかった。
渡邉茜『成る』
丁寧な訓練を重ねてきた身体で、とりわけ立ち上がってからの伸びやか動きは目を引く。しかし、とりわけ冒頭の足指手指をペンライトで照らす場面は、細部に挑戦しているにもかかわらず、客席から見るとその細部が影になり見えづらくなってしまったことが惜しい。どこに光をあてるのか——照明の当て方、光と影の関係をより探求することで、場面としても効果的に引き立つし、作品意図も明確になるのではないか。また、現状は自分の身体を探っている段階に感じた。それはそれで必要なプロセスでもあるのだが、その状態を作品として見せるのはかなり難しい。どこまでも探りたくなる気持ちも理解できるが、作品化する際には、どこかで区切りをつけてひとつのものにまとめ上げる、有限化の作業が必要になるだろう。
LU LA LA Dance『「蘇」~ソ~』
シアトリカルな言動、呼吸音を聴かせながらのダンス等、全存在を晒すようなソロ作品。やりたいことがあって挑戦した、というひたむきな気概を感じる。振付家の名前が筆頭に来がちな現代ダンスではあるが、出演するダンサーも、同等の「創作者」として評価されるべきであり、その点で、本作のように振付を他者に委ねるというのもひとつの方法といえる。本作に関しては、自分の殻を破りたいと求めながら、これまで積み重ねてきたものや「正しさ」にも引っ張られ、ふたつの間でせめぎ合っている状態であるように見えた。振付という枠組をさらに一歩超えて、演者である阿部の存在——枠からはみ出てしまうような部分、ある意味でそれが阿部としての刻印——がにじみ出てくると、作品の奥行きがさらに増すのかもしれない。
今村朱里『随わざるを得ない水』
たくさんの枕を小道具に、ガーリーな夢想世界から、アダルトな俗世界までを描き出していく。やりたいことがある切実さを感じるが、作品を構成するそれぞれの要素が直接的に過ぎ、まだ表現の域に到達していないように感じる。舞台上での表現にするには、ある種の距離化、つまり客観性を持たせる作業が必要になってくる。その上で、要所要所に直接的な表現を差し込むのであれば、舞台の枠組みを超えて観客を揺さぶるという点で効果的に働くだろう。扱い方によって、手にした枕だけでなく置かれた枕までもが人のように見えてくる瞬間があったことが面白かった。

呉宮百合香 (ダンス研究)
現在、早稲田大学文学研究科博士後期課程在籍、(独)日本学術振興会特別研究員。2015-2016年度フランス政府給費留学生。パリ第8大学と早稲田大学で修士号を取得。ベルギーの演劇雑誌Alternatives théâtralesに日本のコンテンポラリーダンスについての論考を寄稿するほか、RealTokyoやartissueにて公演評を執筆。ダンスフェスティバルや公演の企画・制作にも多数携わる。
>back
|