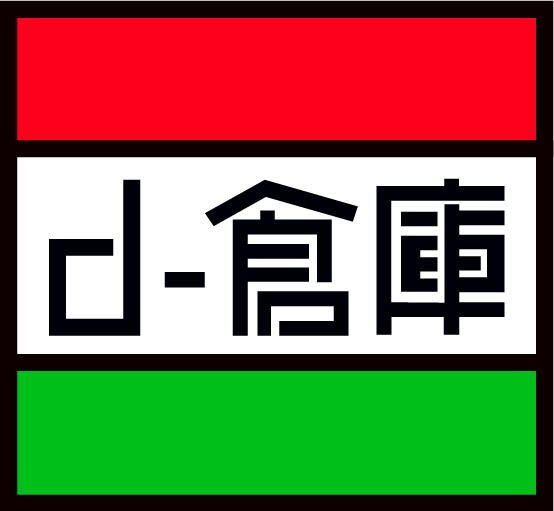はじめに
10年前にも私はこの「ダンスがみたい! 新人シリーズ」の審査員をしました。ちょうどコンテンポラリーダンスが盛り上がっていた頃です。今回、36組を見て、もはや「コンテンポラリーダンス」という名称は必要ないのではないかと思いました。「コンテンポラリーダンス」という言葉はもともと曖昧だったのですが、いまでは少々手垢がついてしまっているようで、目の前で生まれつつある多様なダンスを同じ言葉で呼ぶわけにはいかないのではないかと思えたからです。もちろん、10年前の方が作品の多様性があったことは確かです。でもそれは、良い意味でも悪い意味でもコンテンポラリーダンスという名称の曖昧さにひかれて集まった有象無象でもあったわけです。今回の36組もそれぞれまったく異なるのですが、その多様性は、かなりダンスの内部の多様性へと収斂してきているように見えました。たとえば、かつてアンチ・ダンスとかノン・ダンス、あるいはポスト・モダンダンスなどと呼ばれて、敢えてダンスの否定や解体を志向する美学もあったのですが、今ではそういう反骨精神や懐疑などはそれほど意味をなさないでしょう。常に既にそこにあるダンスを壊す必要はないし、その潜在性や可能性を引き出してくればいいのですから。10年前は、この人は本当にダンサーなんだろうか??という人がいくらでもいましたが、今はダンスの訓練をしてない人のほうがはるかに少ないくらいになっていますし、ひとりひとりのダンサーのテクニックは10年前に比べて格段に向上しているのは確かです。そうはいってもテクニックは、表現の可動域を広める力になる一方で、可能性を狭めることになる危険ももっているでしょう。そういう両面性も今回の36組を見て感じました。
そもそもダンスで何を表現するのでしょう。表現という概念ほど曖昧なものはありません。今回の36組を見てもそれぞれ表現しようとするものも、そのスタイルもまったく異なります。内なる思い、内的な感情、意志、哲学、関係性、社会的な問題や葛藤、抽象的な形式美など、様々なターゲットがありますし、そもそもそこにある身体がすべてであってそこから遊離した表現内容があるわけではない、という境地にまで達することも可能でしょう。それに、作品が実際に表現しているものと、作者が表現させようとしたものとが、そう簡単に一致しないのは、ダンスに限らずあらゆる創造行為で日常茶飯事ですから、作品が表現していることが作者のコンセプトだとは単純にはいえません。でも、実際の作品が作者のコンセプトをどれだけ実現しているかは、コンセプトを知らなくても作品の表層に現れている力を見ればたいていはわかるものです。おそらくそれが作品の力とか強度などと呼ばれているものだと思います。もちろん、何をしようとしているのかあまりにも容易にわかりすぎてしまう作品には、それほどの力は感じられないでしょう。何をしようとしているのかわからない作品は、まったく作者が混乱しているか、それとも逆に、今までのカテゴリーにおさまらないところにまで突き進んでいる可能性もあります。そんな突き進んでいる作品が顕れることに希望を託しています。
審査員であるからには、どういう観点に留意して審査したのか、あるいはどういう心持ちで審査をしたのかをあきらかにするべきでしょう。私としては、あらかじめ作品のコンセプトとか内容とか意図などはできるだけ知らないようにして、とにかくそこに現れた実際の作品を注視して、それがすばらしいのかどうなのか、今目の前で行われている作品から受け取ったもののみに基づいて判断するように心懸けました。ですから、タイトルも振付家の経歴などもほとんど気にせずに、とにかく目の前の作品にだけ集中するようにしました。どれだけその作品に共鳴することができたか、どれだけその作品に揺さぶられたか、どれだけのめり込まされたか、そういう自分自身の感受性に頼りながら、できる限り客観的に自分の感性を観察し、一つ一つの要素を腑分けして、なぜそれがよいのかを分析し、判断するようにしています。これはなにも審査だけのことではなくて、ふつうに舞台作品を見るときにはいつもそうしていることですけれど、審査となるとその判断基準の客観性のレベルを飛躍的に高めなければならなくなります。ですので、こういう要素があればよし、と単純に言えるものではなくて、同じ要素でも、効果的に行われる作品もあればまったくダメな作品もあるわけですから、何があれば評価すると一概にはいえないわけです。とにかく、見てみないとわかりません。
いま、コンセプトや意図などは見る際には気にしない、と言いましたが、それは、作者のコンセプトがどれほど適確に具現化されているのかということは、作品の表面に現れるはずだからです。コンセプトがそのまま実現されているかどうかではなくて、先ほども言ったように、強いものを備えているかどうかが表面に現れるからです。コンセプトをあらかじめ知らないとわからない作品は、力のない作品でしょうし、あとから言われて、ああそういうことか、と納得できることもありますが、それも作品としては弱い(もちろん、デュシャンの『大ガラス』のように、コンセプトと実際の作品が渾然一体となって作品を構成している例もありますが、あれはコンセプト自体が作品になっているわけです)。最初のコンセプトとはまったく異なるものが作品に現れてしまう場合もありますが、それはそれで力を持った作品になるでしょう。もっと言えば、コンセプトや意図や内容と言われるものは、作品自体と切り離されたところにあるのではなくて、もうそれ自体が作品と切り離せないものとして一体化していて、どこまでがコンセプトでどこからからが表現なのかわからなくなるまでになった作品こそが、力を持つと思います。今回の36作品にも、そういうコンセプトと表現との関係がどうなっているのか気になってしょうがない作品もあれば、気にならなくなるほど力を持った作品もあり、色々な段階が見られました。
それではそろそろ、36組それぞれの作品について見ていきましょう。順番は上演順です。なかでも特に注目したい作品は、チーム・チープロ『皇居ランニングマン』、天野絵美『麹(こうじ)』、茎(西沙織)『At Last』。それに次ぐのが、宮脇有紀『dräpped into』、小野彩加・中澤陽『フィジカル・カタルシス』、窓ぎわの我ら『Masterpiece』、宮崎あかね『マリー』、Von・noズ『不在をうめる』です。 
1月4日(金)
チーム・チープロ『皇居ランニングマン』
皇居の前、何もないがらんとした空間が広がる皇居前広場に注目した視点が素晴らしい。戦前・戦中には国体発揚の舞台、戦後にはGHQ本部が近くの第一生命ビルに設置されて、進駐軍のパレードも行われた。その後、血のメーデー事件の舞台ともなったという歴史を改めて突きつけられると、何事もなかったかのように同じ場所で正月に行われる一般参賀が白々しく思えてくる。その皇居前広場の砂利と松だけの広場でダンスをすると、「ここは皇居ですから」と注意されるらしい。だとしたら、ストリートダンスの基本ステップの「ランニングマン」を、そのままでは注意されそうなのでそれを小ぶりにしたら皇居前でも踊れるかもしれない、さあステップのレッスンをしてみよう・・・というレクチャーパフォーマンスが前半。この発想が面白い。ドキュメンタリー風の映像もあったので、実際に広場でやってみたのだろう。この前半のレクチャーに対して、後半はトーンが変わり、そのランニングマンのステップを2人のダンサーが淡々と踊ってみせた。軽快で心地よいダンスを皇居前広場で踊ることと重ね合わせると、どこか滑稽でもあった。滑稽なのは天皇という虚構のシステムを懸命に支えている今の日本のありかたなのかもしれないが、なんらかの批判的な言説がそれほど強調されずに、そのまま終わってしまったのが少々もの足りなかった。結論を提示するにはもっと長い時間が必要だったのか、それとも結論的な批判は提示しないようにしていたのか、そのあたりがもやもやとしたことが心残りではある。とはいえ、なかなか語りにくい天皇に触れる問題を作品とした心意気は素晴らしいと思う。チーム・チープロがこれから何をリサーチするのか注目したい。また、今回の「新人シリーズ」でレクチャーパフォーマンス形式の作品はこの1作だけだった。「新人シリーズ」には馴染まない形式かもしれないが、これからもっと増えていくことを期待したい。
大熊聡美『苺ミルクの妖精になりたい』
正面を向いて立ちつくしているうちに感情がこみ上げてきて泣き顔になる……こうして始まるこの作品は、常に感情に先導されてダンスが進行するように見えた。何らかの物語がそこにはあり、盛り上がる感情がいくつかあり、それが身体にまでのぼってきてダンスとなるという構造なのだろうか。見ていてその感情の盛り上がりにおいていかれてしまうと、なぜダンスが始まるのかわからなくなった。ダンス自体は、バレエの痕跡を留めながらも手足は伸びきらずに先端がぎゅっと縮こまる。その形は、彼女がメンバーでもあるBATIK主宰の黒田育世の動きに似ている。そんなに師匠の動きを真似なくてもいいのにと思いつつも、これも黒田育世のヘゲモニーの力なのだろうかと少々恐ろしくなった。後半、ミルクと苺とぬいぐるみの間をせわしなく行き来する。無言の演技で何らかの情念を表そうとしているのは理解できるが、物語を紡ごうとするあまりに過剰な身体表現となり、過剰に自傷的になりすぎはしないか。それが黒田育世のスタイルに通じることはわかるが、黒田育世のスタイルは彼女だけのものであって、もはや様式化し硬直化しつつあるとしたら、もっと独立した自分自身の表現様式を見出すべきだと思う。
後藤茂『R』
往年のスクリーンミュージックとアルトーのラジオドラマ『神の裁きと訣別するために』が同時に聞こえるなかで、彼は裸になった。もちろんいきなり裸になるわけではなくて、大きく円を描いて走りながら、次々と着ているものを脱ぎ捨てていき、最後に全裸になるまで20分近くかかっただろうか。ひとつずつ脱いでいけば全裸になるのは論理的必然。もちろん最後まで着衣のまま走り続けるという選択肢もあったかもしれないが、それでは観客の期待を裏切ることになったかもしれない。ともあれ彼は走り続けて期待通り裸になった。そして、裸になった彼は体にオイルを塗りたくって踊り出す。これはダンス作品なのか、それとも正月の余興なのかわからなくなるが、そういえば彼が属していた黒沢美香のダンサーズでは、いまは休業中の綱島ラジウム温泉 東京園の大広間で、余興なのかダンスなのかわからない極めて高度なダンス作品を上演したことがあった。ちょうど美香さんが体を傷めていた時だった。ダンスが立ち上がる瞬間は、芸術というご立派なものではなくて、むしろキッチュな芸に通じるのではないかという師匠の突きつけた問いをしっかり受け継いでいる。
粋地獄『Some of Trauma』
振付・演出の中村駿が語る内的世界を6人のダンサーが具現化する、ということなのだろうか。三度目の事故、PTSD、父親の叱責、等々、トラウマとノスタルジーが曖昧に混じり合ったような話が語られる。雨ガッパで現れ傘を並べるダンサーたちは、雨が嫌いだと言う中村駿を優しく包んであげる母性の体現だろうか。ノリノリの音楽に、激しく刻む縦ノリで踊るダンサーたちは、激しく踊る割にはうつむきがちなことが多い。本来は主体であるべき6人のダンサーたちが、いつまでも彼の物語と音楽に支配されていて、そこから抜け出せないのが見ていてつらい。それが作品の演出といえばそうなのかもしれないが、ダンサーが、振付・演出のヒエラルキーにそこまで従順でいることに疑問を感じた。
1月5日(土)
ノセミチコ『AND』
中央にひとり、そのまわりを円を描いてもうひとり。ふたりとも白い衣装。中央のひとりは間歇的に上体を横に倒しては元に戻る。バネのような力。そのまわりを回っているひとりも、間歇的に足を大きく上げたりする。大きく動く振付は力強いし、刻々と変わる幾何的パターンの構築は建築的な美しさもある。人というよりは物が動いている小気味よさを感じるが、それだけで終わってしまうので、ものたりなさをおぼえてしまう。とはいえ、内的な感情の表現などというものをまったく考えずに、抽象的な動きだけで構成するのは潔い。人間的な関係性などというものなどを考えずに、もっともっと幾何的・無機質的なメカニカル性を突き詰めたら、おもしろいものが生まれてくるのではないかと期待したい。
大橋武司『Piano Trio』
ひとつひとつていねいに動きを作るダンサーだ。いくつかの短いシーンをつなげたなかでも、蠅のような仕草で顔を伏せながら手を動かすところが面白かった。音楽は叩きつけるようなノイズっぽい音から軽いジャズまで多彩だけれど、体の動きは割と単調で淡々とこなしているように見えた。特に、ゆるやかな動きの時、力が抜けているともいえるのかもしれないが、芯に力があるようには感じられず、ただゆっくりと力を抜いているだけに見えたのが弱いところか。なんらかの内的な物語が進行しているようにも見えたが、それを伝えようとしているのか、それとも伝わらなくてもダンスだけで何かが伝わると思っているのか、そのあたりが中途半端に見えたので、もっとはっきりさせた方がいいだろうか。
小林菜々『親愛なる午前3時』
目覚まし時計と赤いポットのまわりで、なにやら3人が儀式を始めるかのように踊る。儀式と感じさせるのは、ポットのまわりを回るからだけではなくて、音楽に操られるように踊るからだろうか。あるいは音楽を追いかけて踊っているようにも見えたからか。体の中から湧き出す動きというよりは音に憑依された感じ。終始、無表情でいるのもそういう演出かもしれないが、アンニュイとうよりは淋しげに見える。音楽が流れるとそれに合わせて踊らされ、音が消えるとあてどなく歩くのも、単調すぎて演出の工夫がほしい。振付にもっと印象的な部分があればよかったけれども、それほど特徴が見られなかったのも残念。
宮脇有紀『dräpped into』
最初のシーンにひきつけられた。前屈して両手だけがゆっくりと、自分の体とは別物のように、それがどこに付いているのかわからなくなるように動く。そのうちに、手と平行な位置で、後方にある足も一緒に動き出し、さらに奇妙なものになっていく。両手をげんこつにしていることでそれが手であるとはすぐには見えない演出も、ちょっとしたところだけれどセンスがいい。途中でかなり長いセリフが語られたり、あちこちの場所を使ってなんらかの意味や物語が込められた断片的なシーンが挿入されたあたりは、その意味するところに付いていくのが難しくなった。おそらくそこに込められた大きな意味があるのだろうけれど、それがうまい具合に響いてこない。意味や物語に流されずに、あるいはそれを表現しているという思いに安心せずに、きっちりとそれを乗せる身体のあり方、見せ方を見つけてほしかった。最初の身体のインパクトの力があるのだから、もっと強い見せ方ができると思う。
1月6日(日)
高瑞貴『隣接』
全体的に、音楽の情緒が盛り上がるのを待って踊りを始めるように見えた点が気になった。音楽に頼っているからかもしれないが、踊りは音楽の情感をなぞるばかりで、踊り自体から音楽を越えるものや、音楽とは別のものがなかなか現れてこない感じがする。音楽が変わると踊りの雰囲気も変わるのだけれど、やはり音楽に振り回されているようで、ダンスが主導しているようには見えなかった。美しいフォルムを作るのには長けているのはわかるけれど、それがからまわり気味なのは、音楽に雰囲気や情感を任せっきりにしているからかもしれない。もう少し音楽と距離をおいたり、ずらしたりしてみると、ダンスそのものがくっきりと見えてくるのではないだろうか。
有代麻里絵『毎朝数千の天使を殺してから―薄明―』
動かないこと、踊らないことを称揚するロジックは舞踏が強調することが多い。おそらくそういう舞踏というジャンルがなければこの作品を踊りとして受け止めるのは難しいかもしれないし、そういう文化を共有していないとなかなか入っていけない世界かもしれない。足を上げようとしてバランスが取れなくてグラつく、そればかりかつねにグラついているのだけれど、そういう演出なのか、それとも体幹が弱いのか、わからない。幾度も倒れるが、足がもたれて倒れるわけではなくて、ハイヒールでほんの少しジャンプしてから倒れるので、演出なのだろうけれど、なぜ倒れるのかわからない。おそらく身体そのものへの真摯な志向──それは本人のでもあり観客のでもあろう──を要請する演出なのだろうが、どうも身体の表面で視線が止まってしまい、それ以上進めない。舞踏の語彙を踏襲しているように見えながら、バレエを遠く志向しているように見える動きが随所に登場する。とりわけ後半は裸足のままつま先立ちでゆっくりと回ってみたりする。つま先立ちといえば、ベンゴレア&シェニョーの『Dub Love』というトゥシューズの意味を塗り替えるような作品があるが、彼らの強烈な身体への志向に比べると、ゆるく見えるのだが、そのゆるい力のなさ、身体への志向をゆるめるのが舞踏の特徴なのだろうかとも思えてくる。
天野絵美『麹』
黒いタイツのふたりが、とても簡素な出で立ちで、とても色彩に富んだ音楽に合わせて踊る。普通なら凡庸なダンスになるかもしれないのに、はっきりとダンスが音楽を凌駕しているのに驚いた。音楽に反応して動きが生まれるのだけれど、見たことのないような新しい動きが次々に出て来る。しかもどれも音楽にピッタリ合っているように見える。それなのに、音楽に従属しているわけではなくて、身体の可能な動きで音楽に対抗するものを作ってしまっている。しっかりと音楽を聴いて、その音の運動を、身体の運動に変換するのだろうが、どうしたらそんな変換ができるのだろうと驚くほどで、しかもどの動きも楽しく、見ていて幸せな気持ちになる。これは素晴らしいことだと思う。喩えてみれば、音楽で踊るのではなく、一緒に演奏しているような感覚だろうか。身体がもうひとつの楽器のようになって、もうひとつのリズムを奏でているようだ。「麹」という具体的なのか抽象的なのかわからないタイトルからすると発酵してゆくイメージなのかもしれないが、作者が何を考えていたかがわからなくても、作品が泡だつほどに豊かな響きを奏でているのははっきりとわかる。創作のきっかけがどれだけ作品として昇華できるかが、よい作品となるかの分かれ目なのだとしたら、この作品は成功しているといえるだろう。おそらくそれができたのは、音と身体の動きに対する天野の並外れた感覚なのかもしれない。それなら、もっと多様な音楽でもっと長い作品を構成したらどうなるだろうか、これから色々な作品を見てみたい。
黒沼彩葉『「祝典のための音楽」を踊る』
「祝典のための音楽」という曲は知らなかったが、その吹奏楽曲をまるまるかけて、そして指揮をしたり踊ったり。前半は客に背を向けて動いていて、指揮のカリカチュアのように見える動きが多い。後半で正面を向くと、もう指揮というよりは曲に合わせて踊っているようになる。グザヴィエ・ルロワに『春の祭典』という作品があって、その曲をかけながら指揮をしてみせるのだが、彼の作品は指揮が積極的にフェイクを生み出しているといういかがわしさというか、表象のズレが露わになるが、この作品は、音楽を受動的に受け止めて踊っているだけのように見えてしまう。音楽の情感を振りで増幅することに専念していて、それを逸脱しない。もちろん、曲の盛り上がりに合わせて体を高揚させるダンスは見ていてとてもすがすがしいのだけれど、それだけで終わってしまうのは作品としては弱いだろう。なにかひねりがほしい。
1月8日(火)
酒井直之『第伍世代』
冒頭で土方巽の『鎌鼬』の写真などが幾枚も映されたのはオマージュだろうか、舞踏をやってみせるということだろうか、と思って見ていると、確かに舞踏らしいことが始まった。5人の男女が風の吹きすさぶ音の中で、風に逆らうかのように揺らめきながら立っている。東北のイメージなのか、北のイメージなのか。いわば、イメージの世界の中の舞踏のようだ。もしかしたら舞踏とは、身体性よりもヴィジュルが先行するものだったのかもしれないと思わせる。これは若い彼らの探究不足であって、まだまだ舞踏とは言えない、と見なされる可能性もあるが、もしかしたら、若い彼らだからこそ偏見も臆見もなしに、舞踏の本質をつかんでしまったのかもしれない。舞踏は身体性よりは一種のスタイルだったと。そもそも舞踏とはこういうものだということは、土方本人にも言えないだろう。土方がもっと長生きしていたら、舞踏は変質していて別の物になっていたかもしれないのだから。
山本和馬『枯れた首』
一人立ってうつむく男が何かに耐えているかのようにもぞもぞしている。そのうちに音楽で盛り上がり、動き始めるという導入は、身体そのものにはひきつけられたが、情感の盛り上げが、身体より先に音楽で生まれてしまうところはついていけなくなる。その後も、どうしても音楽に反応して手が動くところが多く、その単純な反応にはあまり共感できなかった。スポットを当てながら、光の外へと動きを進め、見えないところで動き続けているところなど、おもしろい演出もあった。見えないところにあるなにかを見てくれというメッセージなのだろうか。見えない内面、あるいは、見えている身体も実は本当は見えないこともあるのだということだろうか。
砂色クラゲ『原 シ』
6人がメカニカルに動く。全員で1つの機械装置ができあがっているかのように、それぞれがそれぞれの動きを正確に受け止めて、歯車のように動いていく。それでいながら、有機的な肉を持った生命の痕跡も残しているのが見えるのは、人間が行っているのだから当然かもしれない。それがおもしろいのだが、人数や組合せや幾何的配置が変わっても基本的な仕組みはほぼ同じパターンなので、次第に仕組みがわかってきて、別の人の動きが伝わるのを待っている様子の方に目が行ってしまうようになり、その時間がなんだか気の抜けた時間に見えてくる。動きの仕組みを見抜かれてしまってもシラケることのないほど精緻で強いメカニズムを生み出すか、見る者の予想を超えるパターンを差し挟むとか、なにか工夫があってほしい。
本間愛良『茶をひくほど暇な女』
非常に強固な自分のスタイルをもったダンサーだと思う。いわゆる瀕死の白鳥で知られる白鳥の羽の仕草を幾度も行い、それがこの作品の基調となっている。でも、白鳥の羽が次第にただの手のひらひらに見えて来る。身体の柔らかさをフルに活用していた動きも次第にゴツゴツした身体運動に見えて来る。ダンスのモードと日常のモードを幾度か切り替えて見せるのだが、それが生身のものというよりは観念的な切り替えにしか見えなかった。
1月9日(水)
堀菜穂『紫陽花の咲く頃に』
音楽に合わせて踊ることも心得ていれば、崩していく見せ方も心得ているのだろう。ショパンで踊る時も、音楽の情感に合わせながらも、手をバシッと叩いたり足で床をバシッと叩いたり、アクセントの入れ方も心得ているし、音楽のちょっとした変化を受け止めて演じるのもうまい。とはいえ、いずれにしても、音楽に合わせて踊ることしかできないのではないかと見えてしまう。激しい音楽では激しく踊り、情緒たっぷりの音楽ではたっぷりに踊る。ダンスとはそういうものといえばそうなのかもしれないが、作品として提示するにはもの足りなく思う。一つ一つの動きに余分な動きが過剰に付加されているようにも見えるのも、演技過剰に思えてしまう。もちろん、それが魅力だと見る人もいるだろうが、私としてはもっとスッキリとした動きが見たい。それも好みの問題かもしれないが。
望月崇博・酒井大輝『ブラザー』
紙芝居のように始まり、ふたりで動きをやりとりしながら、マイムで会話をしたり、格闘技で対話をしたり、ダンスでのコミュニケーションが続く。パッヘルベルも流れて、ほのぼのとした雰囲気やのほほんとした雰囲気をかもしだそうとするのはわかる。でも、このスタイルは一世を風靡したコンドルズにどうしても似ている。たしかにコンドルズはおもしろいかもしれないけれど、いつまでもコンドルズを追いかけていたら、新しいものを生み出していく時代に遅れを取ってしまうのではないかと心配になる。
深堀絵梨『Living』
丸いちゃぶ台を持ってウロチョロ。風呂敷を開けると、お茶碗と箸のセットがふたり分。でも今はひとりだけ。その淋しさを表すような身振りが少しずつ増幅していって、それがダンスになって行く。きっかけはそういう私生活のひとつのシーンなのだけれど、きっかけが何だったのかわからなくなるまでに、むちゃくちゃなダンスになっていくのが面白い。
project.M『Beyond the wall -壁の向こう側-』
フィジカルシアター的というのだろうか、何か大きな物語を体で表現する無言劇のように、濃厚な物語が背後にあるのをうかがわせるようにシーンが展開していく。おそらくは、タイトルにもあるように、大きな壁にぶつかっては破れ、また立ち上がってはぶつかっていく人生を描いているのかもしれないが、演技としか見えない身体の動きには、なかなか共感できない。演劇でもないしダンスでもないのはいいのだけれど、どちらのいいところも取り得ていないのではないか。最後に至って、身体ではなくて音楽の表現に頼ってしまったのもダンス作品としては弱い。
1月10日(木)
このめ『たゆたゆ』
5人の男女が、歩いたり転がったりジャンプしたり、フォーメーションを変えながら進む。冒頭あたりで2度ほど、暗転後に蛍光灯のまばゆい光が数秒灯り、皆が整列して静止している姿が印象に残った。ダンスらしい動きに依らずに日常的な普通の動きだけで、作品を構成していこうという意志がうかがえる。5人の幾何的配置を綿密に考えていたり、舞台の様々な細部を利用するのもその意志からだろう。後半、身につける物が大量に投げ込まれて、それを着込んだり脱いだりするあたりは、もう少し混乱した状況が生まれてもよかったのではないかと思う。途中で、皆がラインダンスのように並んで踊るところなども、意図的に淡々と動いているのかもしれないが、もう少し楽しそうに踊ることもできただろうか。あるいは、もっと徹底的に無表情に動いた方がおもしろかったのだろうか。どちらかに振れた方がいいかもしれない。
三橋俊平『BPM-Rebuild』
時計とメトロノームを置いて、踊り始める。時計とメトロノームということはもちろん時間に関わるわけで、実際、メトロノームのカウントは、次第に早くなり、彼の動きもそれに随う。という設定はわかりやすい。ダンス自体は、決して大きな動きや激しい動きをすることはなく、ゆったりとしている。なんらかの感情を表現するわけではなく、自然にそこにいるように踊る。それはとても好感を持てるのだけれど、その上で、そこで目を惹く大きなことが起きなくても、もっと見る者を惹きつける力が生まれて来たらよかった。
茎(西沙織)『At Last』
4人がほとんど同じベージュの衣裳でそれぞれの個性を消し去るようにして、色々な塊を作っていく。全体が塊となってゆっくりと変形したり、崩れたりしながら、2人対2人、3人対1人になったりする。3人の塊が1人を飲み込むような動きも見られた。粘菌が形を変えていく様子の観察といったら近いだろうか。その変化から生まれる音と、ときおり指で床を叩くかすかな音が聞こえてくるだけ。なんらかの意味を持ったストーリーが展開しているのではないかとうかがわせるが、もちろんそれは見ているだけではわからない。でも、わざわざストーリーを重ねなくても充分見ていられる。作者が元にしたストーリーとまったく別のものを、観る者が想定していることもあるかもしれないけれど、それはそれでいいのだろう。音楽で踊るような普通のダンスではなくて、身体の可塑性をフルに活用したこのような造形的作品をダンス作品と言えるか疑問に思う人もいるかもしれないけれど、ダンサーの訓練をしたからこそ、可塑的な身体能力を発揮できるのだから、広義のダンス作品と呼んでよいのだろう。近い作風には関かおりや三東瑠璃がいる。やはり2人とも異様なまでに身体の変形や変容に関心を持っていて、個性を消し去って既に人間かどうかもわからなくなった個体が離散集合して何ものかの生態を描写していくような作風はこの作品と似ているともいえるが、相違点も大きい。関かおりは、個体が集まった一種の社会を作品の中に作ろうとしているように見える。それに対して三東瑠璃は、個々の細胞が集まったひとつの生命体を作品で作ろうとしているように見える。西沙織も、一人一人のダンサーが細胞のようになり全体としてひとつの物をなしている様に見えるところでは、関よりも三東に近いが、三東が有機体というよりはメカニカルなシステムに近付いているのに対して、西はもっと有機的で柔らかな動きを多用するようだ。三東の作品よりもねっとりとした肌触りがするのはそのせいだろうか。関や三東が切り開いてきた道の近くを行きながら、まったく別の造形が生まれてくるのを期待したい。
吉倉咲季『此処』
手足の動きがとても柔らかくて豊かで、簡素な衣装によって、その美しさが際立って見えた。おそらく、メカニカルな人形のようなものを想定していて、その人形が立ち上がってひとしきり動きまわって、また動かなくなる、というシンプルなストーリーなのだと思う。寂しさの情感を表出しようとしているのがうかがえる部分と、動きの美しさだけで押し進めようとしている部分とが、分離して見えたのがもったいないと思う。両者の切り替えがはっきりしすぎたのかもしれない。曖昧に両者を並列させるよりは、どちらかをもっと際立たせるか、それとも融合させるとしたら、どういう見せ方をしたらいいか考えると、ずっと良い作品になると思う。いろいろ試してみてほしい。
1月12日(土)
小野彩加・中澤陽『フィジカル・カタルシス』
中澤は単純な仕掛けで場の意味を揺らがせようとする。プレイヤーを置いて、m、u、s、i、c と繰り返すのに音楽は聞こえてこない。わずかに手が揺らいでいる。そのいっぽうで小野はそうとうに踊れるようだ。太極拳のような大きな動きでゆったりと動く力のあるダンスは小気味よい。中澤の話す言葉がその意味内容をともなわずにぎこちなく消えて行くのに対して、小野の体は物体としてしっかりとそこで動いている。心と体の二元論的身体をふたりで体現しているのだろうか。ふたりがメカニカルに手足を組み合わせたり、接触したりするのは、どちらも一方だけでは存立しえないからなのだろうか。そんなふたりが同じ動きを繰り返す時、その反復がなぜか不気味に見えた。時々暗転が差し挟まれるが、明るくなってもさほどふたりの体制は変わっていない。暗転の役割や意味を曖昧にする仕掛けなのだろうか。随所にほのかな謎をはらんでいるのがおもしろい。しかもそれが身体と言葉が絡んでくる謎であるところがいい。
DADADA『Kitsch』
“Revolution 9” など、けっこう古い時代の曲が次々とかかり、音楽に合わせて踊るのだけれど、それほど濃厚な内容の曲ではなくてカラッとしたノイズっぽい音が多いせいか、音楽に踊らされている感じはしなくて、屈託なく楽しそうに踊る様子がとても好感が持てた。最後に、大量のコンパクトミラーを大きく円形に並べて結界のようなものを作り、その中で一人ずつむちゃくちゃに踊る儀式が待っていて、その突き抜けた感じが気持ちよい。ただし、一番盛り上がるところで中島みゆきの『時代』を使ったけれど、あくまでダンスで盛り上げてもらいたかった。最後に紙吹雪で終わったかと思わせておいて、掃除機が登場するあたりはうまい。しかも、掃除機の音は前半で幾度も使われていて、伏線も張られていた。
トロリテケロリ『人魚シンフォニー』
『人魚姫』のストーリーを借りた寸劇とダンスという構成なのだが、寸劇部分のユーモラスな狂乱と、情緒たっぷりのダンスとの差が大きすぎるように思えた。意図したことなのかわからないが、ダンスが劇の説明となっているようにも見えた。言葉で語られる状況や思いをダンスで表現しようとした場合、言葉なしで伝えなければならないために、どうしても過剰なダンスになるのだろうか。言葉による演技が素晴らしかっただけに、それと同等な力を持った表現をダンスで行おうとして過剰になるのかもしれないが、もっと力を抜いたダンスでも十分伝わるものはあると思う。
窓ぎわの我ら『Masterpiece』
赤と緑のストライプのふたり。ひとりがもうひとりの背中にのって、同じ姿勢で夢みるように始まる。ひとりがころりと落ちて、ふたりは並んで横になり、ひとりが片手を上げるのをもうひとりが阻止する。終わりにも同じシーンが現れたけれど、その時は邪魔されずに花の形に手が開いた。ふたりのとても親密な接触からなるダンスだった。印象に残るシーンがいくつかあった。たとえば、ひとりが光の当たっているところで踊っていると、もうひとりが光の当たらないところでひっそりと影のように踊っているシーン。遠いところにいながらふたりの関係が続いていくようでおもしろかった。ムリに意味や物語や情感を表現しようとするのではなく、自然に流れていくダンスでいながら、親密な関係性が浮かび上がってくるところが、ダンスとして優れていると思う。ひとつ、もったいないなと思ったのは、最後に手を振るシーンで井上陽水を使ったところ。せっかくそれまでダンスで築いてきたものが、突然割り込んで来た陽水に持って行かれてしまうので、むしろ無音の方が盛り上がったと思う。
1月13日(日)
橋本礼『裸足の街』
コートを被って立っている姿で登場し、その後ずっとコートと関係し続ける。なぜそこまでコートに拘るのかわからないが、ひとつのアイテムと徹底的に関わってみようという作品はありうる。その異様なまでのこだわりからか冒頭のシーンは緊張感を湛えていた。それでも、コートをなかなか脱げないという演技のような仕草が続くうちに緊張感はだんだん薄らいできた。中央の光の中に入るのを躊躇する仕草なども、なぜそんなに躊躇するのかその理由はもちろんわからないのだけれど、とにかく異様なまでに躊躇いの仕草の演技が強調されるのは、なにかそこに心理的なこだわりがあるのだろうかと思われてくるほどだ。コートをようやく脱いだら、こんどは寒いのか恥ずかしいのか、心理状態を表現する仕草が強調される。マイムのジャンルなのかもしれないが、強調される仕草にどうしてそこまでこだわるのかなかなか受け入れられないものがあった。あるいは、その演技に説得力がたりなかったということだろうか。
宮崎あかね『マリー』
赤の衣裳に赤の線が眼にうっすらと引かれている。一輪の花、壺、ワイングラスなどが、いかにも儀式が始まるように並べられている。そこに座り、それらの道具で本当に儀式らしきものが始まる。「毎日死んで行く無数の細胞の記憶……」などと、ときおり謎のようなセリフ。それがこの儀式に関わる言葉なのかはわからない。ずっと座ったまま、手を使った動きが続く。その動きはとても繊細で細やか。立ち上がっても、指で歩くような仕草。あくまで指が動きの中心となるのは一貫している。終わり頃になり、せんべいのようなものをワインに浸して食べるあたりで、ようやくこれは聖体拝領なのかもしれないとわかる。パロディのようにも、今ここで真摯な思いで行っているようにも、大人の真似をしている子供のようにも見える。楽しそうに行っているその仕草は、決して瀆神的なものではなくて、『禁じられた遊び』のポーレットや『汚れなき悪戯』のマルセリーノのように、形骸化した大人の宗教よりもより根源的な宗教性に触れていたのかもしれない。かつてカトリックは、異端として断罪されたグノーシス派やカタリー派の方が真摯な信仰や哲学を持っていることに動揺したこともある。「ひとしずくの水をください」という言葉は、『ヨハネの福音書』のイエスの言葉だったのだろうか。中世の頃のキリスト教は、教会からダンスを排除したことがある。もしかしたら宮崎は、宗教的なものとダンスを結び付けようとしているのだろうか。もちろん、世界中の多くの宗教を見れば、ダンスと結びついている宗教の方がはるかに多いだろうが、かんじんのキリスト教がダンスに不寛容だったのだ。ダンスと宗教的なものの関係を探る試みはとても有意義だと思う。しかもそれを研究ではなく実践として行うことができる人は貴重だ。
Von・noズ『不在をうめる』
ノスタルジックな避暑地風のワンピースに大きな帽子。タイトルも抽象的で、何らかの物語を表象するのではなくて、純粋に動きやダンスだけで構成しようとする作品構成には、自信と確信が感じられた。ふたりの動きの配分も、たとえばひとりが椅子と格闘している間にもうひとりは大きな動きで空間を埋めるなど、よく考えられている。おそらくはそうとうにダンスのテクニックは持っていると思うが、あえてダンスらしい動きを封じて、身体の動きだけで構成したのだろうか。それが少々もの足りなく思えた。ようやくダンスが始まったと思ったら、そこで終わってしまった。その先を見たかったのに。空間構成や動きの配分で抽象的な作品を作り上げる力はあると思うが、ダンスを抑制するのはなぜだろう。ある種の作品では踊らない方が評価されるという不文律があるのだろうか。踊ることによって、どうしてもそれまで身体に刻まれた訓練の歴史が見えてしまい、それが作品を狭めてしまうことを嫌うのかもしれないが、その危険を乗り越えて、新しいダンスを見出していくことも出来るのではないかと期待したい。
スッポンザル『鼈』
冒頭のふたりの異様な組合せは、仏像のようにも、怪物のようにも見えて、たしかに面白い。その後の展開はこの冒頭から予想されるように、ふたりの組合せの妙を中心にして、時々ユニゾンで大きく動く所がアクセントになっているようだった。組み合わせられた動きは面白いのだけれど、ひとつひとつの動きあまり力を込めずにゆるく、ユーモラスに行われていて、それも面白いのだけれど、全体にゆるさが目立ちすぎはしないか。ビシッと動きを作らずに、わりとゆるく行っているので、それをもっと硬質な動きにして、ピシッと合わせてみたら、もっと尖ったものが見えてくるかもしれない。
1月14日(月)
横山八枝子『ICARE』
原始的な人間の生活の風景なのだろうか、ふたりの人間がゆっくりと近付いたり離れたり、争うわけでも、遊ぶわけでも、つるむわけでもなしに、淡々と時間が過ぎて行く。何も起きない。だからこそ日常の風景なのかもしれない。ふたりは白い粉を身につけているから、あたりがだんだんと白くなっていく。何も起きないけれど、次第に舞台が白くなっていくことで時間の経過を思い出す。ホースを回転させてずっと鳴らし続けている音も、時間の経過を忘れさせるかのようだった。何か展開があって盛り上がった方が見ていておもしろいとは思うのだけれど、何も展開しないことこそが重要なのだろう。その時間を共有できるほどの強い力はまだそれほどないかもしれないが、この方向は続けてほしい。そして、この方向で1時間程の作品をどう作るかを見てみたい。
渡邉茜『成ル』
うずくまって、懐中電灯の光だけで足を部分的に照らし、押し入れに籠もっているかのようにもぞもぞしている非常にプライベートなシーンから始まる。中ほどで動きが大きくなったところは、わりと決まった形のダンスの動きに見えた。照明の変化で構成しようとした作品だと思うが、ダンス部分の力をもっと強めたほうが効果的だったのではないか。
LU LA LA Dance『「蘇」~ソ~』
右手のげんこつで左肩を叩き続ける動きが一種の負荷になってそこから生まれる踊りを制限すると共に、その制約で生まれる新しい動きを拾い上げようとしている、と言えるだろうか。“現代舞踊”で培われたダンステクニックの語彙の豊富さをあらためて感じさせてくれる作品だった。ひとめ見てわかるその特有の動きは、その過剰さに特徴があるのではないだろうか。バレエやモダンダンスで想定される動きよりも、意味を担う動きがはるかに細かく差し挟まれる。その過剰さがわかりやすい面もあれば、過剰さゆえに敬遠されることもあるだろう。いわばパラダイムを共有している場でないとなかなか受け入れられない過剰さと語彙かもしれないが、“現代舞踊”はまだまだ確実にその意味の世界を増殖しているように思われた。
今村朱里『随わざるを得ない水』
散らばっている枕を色々にもてあそぶ作品なのだけれど、もちろん枕があるからといっても日常のシーンではなくて、そもそもいくつも枕があるのが異常だけれど、夢のようにどこか歪んだ雰囲気で枕と戯れる。物憂げであったり、暴力的であったり、気分は定まらない。大きく足を上げたりする動きもあるけれど、ダンスを見せようとするのか、なんらかの気分を表すパフォーマンスを見せようとするのか、どっちつかずの感じがした。踊るわけにもいかないし、かといって物語を紡ぐわけにもいかない、というところで揺れているのだろうか。中心軸をどこに置くかもっとはっきりさせたほうがクリアになると思う。

坂口勝彦 (ダンス批評)
思想史。雑誌「シアターアーツ」編集委員。舞木の会共同代表。2017年には、『江口隆哉・宮操子 前線舞踊慰問の軌跡』(共著、かんた)、ジョン・ディー「数学への序説」の翻訳(『原典ルネサンス自然学』(名古屋大学出版会)所収)等を執筆。
>back
|