
 |
 |
| 柴田恵美〜集中する身体を操る〜 |
|
|
|
|




コロナ禍を批評する演劇的想像力
城山羊の会『ワクチンの夜』
藤原央登(劇評家)
- - -
新型コロナウイルスのワクチンの有効性や、死亡事例との因果関係はあるのか。専門家も断定できないまま、大事なことが進行している。そのような状況を投影した喜劇だ。ワクチンの効果を「嘘」に、副反応を「性欲」に置き換えて、性を原動力にしたすれ違いと暴力が展開される。
▶
続きを読む



突きつけられる、2018年~2021年の社会変容
水中めがね∞『有効射程距離圏外・Ⅲ』
藤原央登(劇評家)
- - -
中川綾音が率いる水中めがね∞の作品からは、社会で生きることの鬱屈感や抵抗の意志を感じさせられる。時に暴力性を伴うことで、観る者にひりついた感覚を与える。一方でストリート系のカッコ良さやテキトーさもあるため、フッと肩の力が楽になる瞬間もある。攻撃的でストイックな中に、スマートさと脱力性が顔を覗くのである。
▶
続きを読む



新型コロナウイルス感染症対策を生の舞台に取り込み、見事に対応した貴重な作品
FUKAIPRODUCE羽衣『おねしょのように』
藤原央登(劇評家)
- - -
何組もの男女のペアが、作・演出の糸井幸之介によるオリジナル楽曲に乗せて、様々な愛の形を歌い語る。FUKAIPRODUCE羽衣は、そんな「妙―ジカル」の作風で知られる。類型化されたキャラクターが登場するため、観る者はそれぞれに、特定の人物が語るエピソードに心を寄せることができる。そして誰もが経験したであろう「あの時」の心情が、うまくくすぐられる。さらに糸井の楽曲が、掘り起こされた切ない感情を増幅させるのである。
▶
続きを読む



「心の革命」を起こして戦後史を受け止める
TRASHMASTERS vol.33『堕ち潮』
藤原央登(劇評家)
- - -
久しぶりにTRASHMASTERSの作品を観た。上演時間3時間越えと変わらず長大で且つ、多彩な問題が取り上げられるので重厚である。しかしながら作品の幹がしっかりとしており、核が捉えやすい劇構造である。充実した観劇体験であった。
▶
続きを読む



我々は人を死なせる恐れなしにはこの世で身振りひとつもなし得ない
俳優・演出家・仙台シアターラボ代表 野々下孝
- - -
我々は仙台を拠点に2010年から演劇活動を行なっているが、一貫して古典作品を原作にした現代劇を上演し続けている。我々にとって古典作品を上演するということは、古典を現代に甦らせることとは似て非なるものだ。古典は、形だけを残して体温も匂いも失ってしまった化石に例えられる。学者の仕事が化石の発掘作業だとしたら、演劇人の仕事は一体何なのか?
▶
続きを読む



人間には理性(言葉)と肉体(無意識の苦悩と歓び)がある、
立本夏山「人間劇場」旗揚げ公演『行人日記』
原田広美(心理相談&夢実現「まどか研究所」主宰、『漱石の〈夢とトラウマ〉』著者)
- - -
立本夏山を舞台で最初に見たのは、2019年2月のヴィクトル・ニジェリスコイとの共同演出・出演の『ふたり、崖の上で』(原作:『白痴』ドストエフスキー、於space EDGE,渋谷)だった。この時には、ロシア人の男性ピアニストの即興演奏も、大いに舞台を盛り上げた。そこに即興の要素が入っていたのは、偶然ではなかったかもしれない。
▶
続きを読む



水場を巡る生者の生態から、死者の葬列への見事な転換
堀企画『水の駅』
藤原央登(劇評家)
- - -
平田オリザ『東京ノート』(1994年)に続く堀企画の2作目は、現代演劇史における古典のひとつ、故・太田省吾が率いた転形劇場の代表作『水の駅』(1981年初演)。『トウキョウノート』(2019年12月、アトリエ春風舎)ではシーンをバラバラにしたテキストレジーよりも、美術館のロビーから闇の広がる無機質な空間演出が印象的だった。そこに登場する人物たちは、暗闇の墓地に浮かぶ人玉のように実体が不透明に感じられた。そこでフェルメールの絵や家族の話といった、生活感のある市井の人々の会話が交わされる。
▶
続きを読む



二人芝居に改変して明瞭になった、社会の中における男の在り様
オフィコットーネトライアル公演『ブカブカジョーシブカジョーシ』
藤原央登(劇評家)
- - -
オフィスコットーネは長年、犬の事ム所を経てくじら企画を率いていた、大阪の劇作家・故大竹野正典作品の上演に取り組んでいる。今回は新たに、くじら企画で1992年に上演された『ブカブカジョーシブカジョーシ』を取り上げた。サラリーマンのアイデンティティクライシスと男のメランコリックな哀愁を描く本作は、大竹野作品の骨格と世界感を示す成果を挙げた。
▶
続きを読む



芝居を観る愉悦を与えたProject Nyxの代表作
Project Nyx『新雪之丞変化』
藤原央登(劇評家)
- - -
Project Nyxが女歌舞伎として上演した本作は、これまでになく俳優の演技で魅せるしっかりとした「芝居」に仕上がっていた。密輸の一大組織を作り、幕府とは距離を置いて独自の利権を確立した和蘭屋清左衛門。奉行役人である土部三斎(小谷佳加)はその利権に預かった挙句、清左衛門を罠に嵌めて死に追いやり、彼の妻を寝取った。
▶
続きを読む



過激思想に通じる、日本人の潜在意識に巣くう差別意識
流山児★事務所『コタン虐殺』
藤原央登(劇評家)
- - -
倭人(日本人)に搾取され続けた末、1669年のシャクシャインの戦いで蜂起するも敗北するアイヌの歴史。そして1974年に起きた、アイヌの独立を訴えて町長を襲撃した北海道白老町長襲撃事件。2つの時空間を往還することで浮かび上がるのはもちろん、日本人によるアイヌ民族への根深い差別である。だが本作は、過去の歴史的な差別を追うだけで終止しない。現在に至るまで差別が残っており、時にそれが過激思想へと高進すること。
▶
続きを読む



「個の核」から溢れ出る生のエネルギー~カフカとゲシュタルト療法の視点から
OM-2(演出:真壁茂夫)×柴田恵美(振付・共同演出)『傾斜 -Heaven & Hell-』
原田広美(「まどか研究所」所長・心理療法家・舞踊評論家)
- - -
OM-2の作品は、1998年初演の『K氏の痙攣』から見た。だが初演ではなく、横浜の大きな会場で見たシカゴの俳優達とのコラボレーションの再演を見た。物語やあらすじはなく、実験的な身体劇だった。それは、今も変わっていない。横浜で見た『K氏の痙攣』では、最後に大きなスクリーン一杯に、何十という心理療法の名称がテロップで写し出された。
▶
続きを読む


より良い世界を創る一員となるよう観客を鼓舞
世田谷パブリックシアター+エッチビイ『終わりのない』
藤原央登(劇評家)
- - -
地球温暖化や紛争、他国を無視した大国の自国第一主義と独善主義によって、世界は混沌としている。この情勢が高進した先に待っているのは、地球の崩壊。現在とは、未来に地球が消滅するか否かの転換点である。このような現状認識の下、散見される懸念を解消して地球の未来を救うべく、一人ひとりがより良く生きよ。そう直截にエールを送る作品であった。
▶
続きを読む



二項対立と両義性の狭間で耐えるということ
DULL-COLORED POP『福島三部作』
藤原央登(劇評家)
- - -
DULL-COLORED POPが渾身の連作を2019年の夏に放った。福島県双葉町を舞台に、福島第一原子力発電所の誘致から東日本大震災における原発事故までを描く、長大な年代記「福島三部作」である。昨年上演された第一部と、新作の第二部と第三部を合わせて一挙に上演した。私は一日に3作をまとめて観た。そのことによって原発政策を巡る戦後史の流れと、原発の是非を巡って揺れ動き、ときに分断される人々の複雑な心情が良く伝わってきた。
▶
続きを読む



韓国社会の「いま」を伝えるパフォーマンスと構成力
劇団新世界『狂人日記』
藤原央登(劇評家)
- - -
ストアハウスカンパニーが運営する上野ストアハウスでは、主催事業として「ストアハウスコレクション」(2013年~)を年に数回開催している。日本とアジアの集団が、時にテーマを共有しながら競演する催しで、2019年7月時点で15回を数えている。中でも「日韓演劇週間」と題された日韓の企画が最も多い。7回目となった「日韓演劇週間」では、日本のDangerous Boxと韓国の劇団新世界が公演した。
▶
続きを読む



ダンスの戦争責任
~1940年 戦時下の舞踊家たち~
坂口勝彦(ダンス批評・思想史)
- - -
「政治と舞台」というテーマを与えられて数ヶ月。幾度か構想を練り直してようやくここに至った。日本の戦時下でのダンス。そして、舞踊家たちの戦争責任の問題。どちらもいまだにはっきりと語られていない。語られないまま戦後が始まり、今に至っている。それを語り得る舞踊家もほとんどいなくなってしまった今、それを問わなければ、昭和、平成、そして令和という天皇に由来する年号の背後に隠れて戦争責任がどんどん遠くかすれてしまうだろう。〔……〕
▶ 続きを読む



大竹野正典への実像を体現させた関係者たちの愛
オフィスコットーネプロデュース 大竹野正典没後10年記念公演 第3弾 改訂版『埒もなく汚れなく』&『山の声-ある登山者の追想-』
藤原央登(劇評家)
- - -
大阪で活動した劇作家・演出家の大竹野正典(1960~2009年)。彼の死後、その作品に魅せられたのが、オフィスコットーネのプロデューサー・綿貫凛である。2012年12月に、大竹野作品に魅了されるきっかけとなった遺作『山の声-ある登山者の追想-』(2009年、OMS戯曲賞大賞受賞)を上演。それから足掛け7年、オフィスコットーネは再演を含めて様々な大竹野作品を上演してきた。
▶
続きを読む




イ・ジョンイン インタビュー
サムルノリ「三道農楽カラク」上演に向けて
▶ 続きを読む




梁鐘譽インタビュー
サムルノリ「三道農楽カラク」上演に向けて
▶ 続きを読む



d-倉庫、日本国憲法の上演について
die pratze 現代劇作家シリーズ9「日本国憲法」を上演する
長堀博士(楽園王主宰、劇作家、演出家)
- - -
毎年春に開催されるフェス、日暮里d―倉庫における「現代劇作家シリーズ」が今年も開催された。同フェスは毎年一人の近代から現在に至る劇作家の「一つの戯曲だけ」を取り上げ、多くのカンパニーが上演するという斬新なフェスであるが、今年はその斬新さも増して、その戯曲として選ばれたのは「日本国憲法」であった。「日本国憲法」は果たして戯曲であるのか、と問われる人も多いかも知れないが、まずその問いは間違えている、と解釈して話を続けたい。つまりこの「現代劇作家シリーズ」で取り上げることで、これ以降「日本国憲法」は戯曲に成ったのだ、と受け止めれば良いに過ぎないと考えられるからだ。
▶
続きを読む

 
破局の後の壊れた日常
OM-2『Opus No.10』
新野守広(立教大学教授 ドイツ演劇研究者)
- - -
OM-2の最新作『OPUS(作品)No.10-アノ時のこと、そしてソノ後のこと…-』を見た(2019年2月23日、ザ・スズナリ)。入場すると、まず目に飛び込んだのは、舞台を床から天井まで覆うほど積み上がった段ボール箱の壁である。開演後しばらく経つと、この壁は大きな音とともに崩れ落ちた。破局であろうか。壁が崩れた後には、事務所のセットが見える。事務机やロッカーが置かれ、「アベ政治を許さない」のビラが貼ってあった。こうした日常的なセットが組まれることは、OM-2の公演では珍しい。〔……〕
▶
続きを読む

 
SNS社会へ出立する卒業生への贈り物
座・高円寺 劇場創造アカデミー 9期生修了公演『犬と少女』
藤原央登(劇評家)
- - -
なんとなくつながる社会。それが21世紀の我々が生きる社会である。TwitterやFacebookといったネットメディアを通して、その感を強く抱かされる。そこは誰が何を考え何をしているのかが、日々報告される空間だ。フォロー数や友達が増えると、こちらがフォローしてもいない第三者の動向までもが「お知らせ」されてくる。そういった一切が煩わしくなると、膨大なツイートや書き込みが暴力的に感じるようになる。〔……〕
▶ 続きを読む
 


“政治的でない人はいない”と“表現をしない人はいない”は、同一線上にある“意識”であり“生活”そのものではないのか?
牛川紀政(音響家)
- - -
〔……〕それは、2015年11月に入って、両国で大橋可也&ダンサーズの公演と、浅草で岩淵多喜子振付のインテグレイテッドダンスカンパニー響の公演をやった直後に、チェルフィッチュ帯同メンバーより単身1日遅れでツアーに合流するため、ヘルシンキの空港到着後直ぐに劇場に向かって、仕込みをしたのが幕開けのツアーだった。〔……〕
▶ 続きを読む

 
正系なき時代の異端は誰がそう名づけるのか?
北里義之(音楽・舞踊批評)
- - -
「ダンスがみたい!」実行委員会がプロデュースする新たなパフォーマンスシリーズ<異端×異端>も2年目を迎え、一年に一度の開催ながら、ここまでのところで、佐々木敦『paper song』、川村美紀子『或る女』、三東瑠璃『Matou』、武井よしみち『I wish you were here 2018-sep』と、パフォーマンスの質にも作品内容にもまるで似たところのない4作品が揃った。シリーズタイトルに掲げられた「異端」という言葉については、フライヤー掲載のテクストで簡潔に採用の趣旨が語られている。〔……〕
▶ 続きを読む

 
夕暮れの侘しさと、笑いと
藤原央登(劇評家)
- - -
舞台上に佇む長身の男。そこにもう一人の男がやってきて開演前の前説を行う。彼が前説の最後に、佇む男の胸をトンと突く。劇場内にある大きな柱に、背中から軽くぶつかる男。すると舞台空間にオレンジ色の照明が強く当たり、やってきた女と長身の男が視線を交わす。その最中、前説を行った男が長身の男の足に何やら細工を施す仕草をする。作業が完了して前説の男と女が去る。それを受けて、前に進もうとした長身の男は派手に倒れてしまう。そんな彼を犬になった数匹の俳優が取り囲み、遠吠えを続ける。〔……〕
▶ 続きを読む

 
「PAMS/ソウル芸術見本市」の報告書
真壁茂夫(OM-2演出家)
- - -
Seoulの街並みも大分変わった。近々では5年程前に来たのが最後だが、その時より更に洗練されている。近代的な高層ビルが立ち並び、凸凹が多かった歩道や道路も整備されている。オシャレなカフェも多い。スターバックスがそこいら中にあるのは頂けないが…。 しかし、都市の近代化はどこでも同じようなイメージで個性がなくなっていく。都市の行先はそうなる運命なのだろうか…。今日からソウルで「国際芸術見本市 PAMS」が始まる。PAMSとは別なのか一緒に開催しているということなのか、色々とあってプログラムが良く分からない。僕が英語も、韓国語も出来ないのが一番悪いのだが…、その一環で開催されているのであろう「Street Art Festival」。〔……〕
▶ 続きを読む

 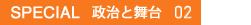

〈アート〉と〈アクティヴィズム〉の狭間で
――ライバッハ、北朝鮮、福島第一原子力発電所――
石川雷太(現代美術家)
- - -
2001年、アメリカの同時多発テロの直後、現代音楽家のシュトックハウゼンが、インタビューの中でWTCのテロを「偉大な芸術作品」と賛美したとして叩かれ謝罪するという事件があった。実際にはWTCに対するテロ行為を肯定しているわけではないが、比喩的表現としてそう発言してしまったということらしい。真意はわからないし、シュトックハウゼンの意図がどうであったかについてもさして興味はない。〔……〕
▶ 続きを読む
  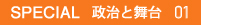

「政治的」なパフォーマンス・アートの実践
イトー・ターリ(パフォーマンス・アーティスト)
- - -
「政治的なアートはアートではない」と言われてきたひとりの表現者としては、なぜ否定されるのか知りたいと思いながら活動してきました。
70数年前の戦争時において、画家たちは戦争画を描くことによって協力したわけですが、敗戦後は批判の的になってしまったというトラウマが影響しているのではないかという説を聞きます。芸術家たちは翻弄されたけれども、戦争体験や戦争そのものを検証しないまま過ごしてきた戦後社会と共に埋もれていったのではないか。〔……〕
▶ 続きを読む

 
現代演劇にはめずらしく左派批判を含んだ「政治劇」
ホエイ『スマートコミュニティアンドメンタルヘルスケア』
藤原央登(劇評家)
- - -
中学校の教室という閉鎖空間を舞台に、凄惨で異常な光景が繰り広げられる作品だ。笑いを軸にそこに向けてエスカレートしてゆく様は、スラップスティック的である。語られる内容は、表層的にはいじめや暴力である。社会の縮図としての教室。大人社会で起こることのすべては、子供の人間関係に集約されている。閉鎖空間における対人関係のパワーバランスを通して、人間の本性や機微を描くことはままある。〔……〕
▶ 続きを読む
|
 |
[artissue FREEPAPER]
artissue No.013
Published:2019/08
2019年8月発行 第13号

|
 |
 |
| 舞台人と生活 |
|
|
|
 |
 |
| 公演までの稽古場の風景 |
|
|
|
 |
 |
| テント芝居・野外劇の現在形 |
|
|
|
 |
 |
| 今求められる「ハムレットマシーン」 |
|
|
 |
 |
| 実験的・先進的舞台芸術の現代的役割 |
|
|
|
|
 |
 |
| 特集・東京以外の劇団からの
[発信] |
|
|
|
 |
 |
| 特集・ダンス!
|
|
|
|
 |
 |
| 特集・ダンス!
|
|
|
|
 |
 |
| 演出家インタビュー
|
|
|
|
 |
 |
| 前衛芸術ってオモシロイよっ!!
|
|
|
|
 |
 |
| 演出家インタビュー
|
|
|
|
|
|







