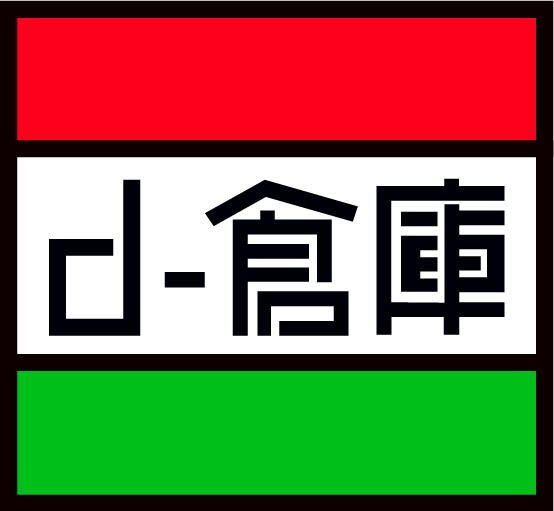総評
コンテンポラリー・ダンスの領域が、従来のどんなダンスよりも多様な身体表現を許容するものであることが、無条件でよきものといえないのは、実際の現場で、それがダンスの定義を更新しながら、身体表現の領域そのものをひろげるというように働くのではなく、多様化とともに林立するといっても過言ではないジャンルの細分化とともに訪れる視野狭窄のようなもの、換言すれば、身辺雑記的なものにしか目を向けなくなるという落とし穴が待ち受けているからだ。しかしそのことがよくわかっていても、時代の趨勢としてやってくるそうした社会的、文化的条件を私たちは回避することができない。問題は身辺雑記的なありように居直ったり、安住したりしないことである。それと同時に、そこを打ち抜いていこうと性急になるあまり、身辺雑記的なことを無視してしまわないことである。身体が切り開く世界は、私たちが想像する以上に広大で多様なものである。いまここに生きている身体において実現されるべきそのことは、まだ開いていない扉のひとつひとつをすべて開いていくような作業といえるだろう。どこかに正解があるわけではない。コンテンポラリーの時代的条件をとことん利用しつくすことで、コンテンポラリーの先にある世界を開くという、ただひとつの行為があるだけである。

講評
昨年度の区分方法に従い、各作品に対する講評は、公演順ではなく、作品スタイルによって整理しなおしたうえでおこなった。組合わせによって似たような作品が並んでしまう日があれば、それが作品の印象に影響することもじゅうぶんありうることではあり、観客の身体を媒介にして、作品と作品の間で起こっていることも興味深いが、ここでは作品を一単位として論じる方法をとる。以下は昨年書いた作品分類法であるが、旧稿を見返す労をはぶくため、若干の手直しを加えて再録する。最初に全体を「ソロ」と「群舞」に大別したうえ、ダンサー固有の身体にフォーカスする「ソロ」を、身体へのアプローチの相違を示すと思われる「道具」の使用のある/なしでわけ(作品によって、衣裳を道具とみなすべきケースもあるように思われるが、ここでは皮膚に近いものとして扱った)、その一方で、関係性を問題にする「群舞」を、内容的に「演劇的な物語・テーマを持つもの」と形式的に「動きやフォーメーションを美的に追究するもの」とにわけた。さらに「ソロ」と「群舞」の間に、関係性の特殊な形態として「デュオ」の項を立てた。以上は便宜的なものにすぎないが、ひとつの身体整理法として試みた。
>ソロⅠ(道具なし)
>ソロⅡ(道具あり)
>デュオ(群舞の特殊形態として)
>群舞Ⅰ(演劇的な物語・テーマを持つもの)
>群舞Ⅱ(動きやフォーメーションを美的・形式的に追究)

●ソロⅠ(道具なし)
À La Claire[榑松朝子]『密かな部屋』
「密かな部屋」に見立てた会場を、ダンサーが訪れ、去っていくまでを起承転結の構成で踊って明快な作品。榑松の公演を観て感じるのは、音楽性にすぐれた(とても耳のいい)ダンサーだということである。ダンス公演の場合、音楽はほとんど効果音のひとつとしてしか使われない。安あがりの舞台装置というところだろう。榑松の場合、音楽はそれ以上のもの、たとえありものの音源を再構成しただけだったとしても、それ自体が舞踊譜のように構成されているもので、音だけ聴いても出来事が想像できるようになっている。小さなグリッチサウンド、カラカラと鳴るノイズ、タンポポの毛のようにのぼっていく鉄琴?の音、中間に登場するリズミカルな音楽など、本公演での音のありようは、密かな部屋のしんとした雰囲気を描き出し、作品の大きな部分を担っていたと思う。
歩くように踊られていくダンス、くりかえされるでんぐり返しや横転、リズミカルな音楽に乗っての回転とジャンプ、最後の場面では、上手口の内側から光がやってきて、密かな部屋に外の世界が波動を送ってくる。様子をうかがいながらダンサーが外に出ていくところで幕。ちなみに、よけいなことかもしれないが、作品の冒頭で、はいていた靴と靴下を脱ぎ、上手口に足をかけて長押まで身を乗り出す場面があったが、そんなことをするダンサーを見たのは初めてだった。
涌田悠『涌田悠第一歌集』
「満喫の小さきソファは宇宙船 よるべなさなどきらめく塵だ」
「7枚で900円のパンツはき 時給910円で働く」
「踊りつつうつむいている客が見え 自分の腹の音が聞こえる」
日常を細やかな感情で描きとり、みずみずしさにあふれる自作短歌を暗誦しながら踊った涌田悠。昨年の横浜ダンスコレクションで『カツ丼のうた』を踊ったときには、くりかえされる朗読が、言葉自体の重さを生んでいたように感じられたが、今回は、『第一歌集』と名づけるくらい作品が増えたということだろう、多くの短歌を次々に読みあげていくところに、日めくりカレンダーのように感情の風景をめくっていくような解放感が生まれていた。ところどころで自分の記憶をたしかめるかのように、「今日の、今日の?」という自問を重ねるなど、実際に詩行を思い出していたのかもしれないが、それが一本調子を免れる読み方につながっていた。感情の流れが見えない身体としてひとつあり、実際に観客に身体を投げ与えるような声のふるまいがひとつあり、そしてそこにダンスの動きがアンサンブルしていく様子が、三つの身体がからまりあって心地よく響きあうダンスそのものだった。
公演の冒頭や末尾で鉛筆が紙を引っ掻く音が流れたのも、ダンサーにとっては効果音などではなく生活の音そのもの。パソコンやネットが普及する以前から生きている私のような人間にも新鮮に響いた。
佐藤ういえん[佐藤有紀恵]『直太郎』
ういえん流「談ス」の試み。「談ス」はコンタクト作品だが、ソロでパフォーマンスする佐藤のコンタクトは、共演者とのそれではなく、観客との密なコミュニケーションを意味している。身体を観客に開くことを表現の内容にしているといったらいいだろうか。暗闇で懐中電灯を使い、ホリゾントを照らしたり、自分の顔を照らしながら新年の挨拶と自己紹介をしたり、勤めはじめた会社での恋バナの話から「いい女になりたい」という告白に流れたかと思えば、観客といっしょにラジオ体操やカウントダウンをしたり、「私、1月4日にして踊りおさめなんです」という気になる言葉をつぶやくなどの語りかけの間に、ときにはハミングしながらダンスが踊られていく。最後には、公演終了の目覚ましが鳴っておしゃべりが中断され、冒頭で彼女が忘れられないといった言葉──時は金なり──がくりかえされて終幕となった。エントリー36組のなかにあって、もっとも観客に近い場所で踊られたダンス公演だった。
青剣/北川綾乃『世界が踊る中心でわたしは踊らない』
上手に椅子に座る形で位置した北川綾乃が、三味線や小唄で情緒纏綿とする響きを奏でるのと対照的に、センターに仁王立ちする青剣は、奇声を発しながら得体の知れないうごめきをつづけていく。「太くある月日重ねて」というような言葉も発するが、それはたちまちのうちに形のない声の波間に沈んでいく。声に関しては、即興ヴォイスには語法というものが不可欠なので、身体のありようともども、これはアンフォルメルな形象をめざしたものではないかと思われる。三味線と身体は、交感的なデュオをするのではなく、むしろおたがいの行為を邪魔しないように隙間を見つけていくような共演のしかたをしていたので、通常のデュオのように、おたがいを開くということはなかった。なにかの合図なのか、ときどきチリリンという小さなベルの音が鳴る。最後の場面で、観客席の雛壇に座りこんだ青剣は、「みなさん、退屈だったら、自由に歩きまわったり、伸びをするとか、咳をするとかしていただいていいんですよ」といった。彼がステージに戻ると暗転。
私の場合、前年の新人シリーズ14に「矢野青剣」でエントリーしたときに「異様な身体の提示」と見えたものが、年をまたいでの反復によって、コミカルに見えてしまうということが起こった。ねらいがたったひとつであることが、ダンス作品としては骨だけを残したスカスカの印象をもたらし、身体そのものを単調なもの、扁平なものにしていたと思う。それがダンサーの意図した身体であったかどうかはよくわからない。
小野彩加/中澤陽『紀元前小野前|before Christ before Ono』
演出を担当する中澤陽とデュオの表記になっているが、ダンスそのものはソロとして構想されたもの。公演の冒頭に、茶色いケットを肩からすっぽりとかぶって全身を隠した小野は、すたすたと下手まで歩き、左手だけ出した姿勢でじっと静止してその場に立つ。まったく踊らない。というか動かない。しばらくして照明が変わると楽屋に引っこみ、黒い上下の衣装に身を包んで再登場すると、今度は上手口の前に正座した。正座した姿勢から、居合い抜きでもするかのように一気に立ちあがる武道的な動きは切れ味よくエネルギッシュで、ダンサーの性格に直結する(と思われる)快いピュアネスを感じさせるものだった。作品はダンスの誕生前と誕生後を表現しようとしたのかもしれないが、コンセプチュアルな構成と清新な身体の動きがそれぞれの方向性を示す作品は、両者の間でいまだ落としどころを見つけかねているように感じられた。
松岡綾葉『長き夜の夢』
不安定にフラフラとステージをうろつき、ホリゾント屋根にのぼってふるえたり、下手前からくる強い光のなかに座り、ホリゾント壁に自身の影を投影して手を動かし影絵をしてみせるなど、「夢」という以上に、そこではすっかり世界のたががはずれてしまう「夜」の雰囲気をつなげていく、それ自身が夢遊病的なダンス作品。公演の途中で、上手に移動していく四角い光がホリゾント壁に投影される。ダンスから立ちあがってくる夜の雰囲気は、はっきりと覚醒した意識のなかでとらえられているという意味で、夢と現実が逆転した世界のようであった。終演間際で何度かフラッシュのような閃光が入り、目の内側に侵入してくる光=目覚めを予感させるのだが、中屋敷南の『lonely』が、最後に目覚めて現実世界に戻ってくるのと対照的に、こちらは少しずつ速まっていくターンをくりかえしながら暗転、最後まで覚めることのない夜の夢のなかをさまよったまま終わっていく。それがどこかで恐れの感情に触れてくるのだった。
●ソロⅡ(道具あり)
長屋耕太『bear』
パフォーマンスの中心になったのは、ふせた水色のジョウロとそのなかにいれられた大小のボールだった。最初に立ったホリゾントの前から進み出てきた長屋は、ふせたジョウロまでやってくると、低くした頭を近づけたり、そのうえに四つんばいでおおいかぶさったり、左足の先でそのまわりに円を描いたりしたあと、口にくわえて持ちあげる。とたんに大小のグリーンのボールがあたりの床に散乱するが、長屋はボールにはかまわず、口にくわえたジョウロを運ぼうとする。しかしうまく支えられないのかジョウロは何度も床に落ち、そのつど手を使わずに口で拾いあげる動作がくりかえされる。いったん落ちたジョウロから離れ、ロボットのような動きを入れてステージを歩きまわった長屋は、ふたたび四つんばいになり、今度は足の間にジョウロをはさんで持ちあげると、床に散乱したボールをそのなかに入れはじめた。足で高く支えあげられたジョウロにボールが満ちると、ゆっくりと床のうえにおろされていく。タイトルの「bear」は、「クマ」の意味ではなく、「(我慢して)支え持つ」意味で使われていたわけである。
最後の場面では、ステージ中央に立った長屋が、ジョウロのなかのボールを観客めがけて投げつけるようなふりをして、後方や脇に投げるパフォーマンスがあり、前に進み出てくるところで倒れるのと暗転するのとがほぼ同時だった。小辻太一『動かせられる』のように、ダイレクトに大道芸の要素を持ちこんではいないが、ボールを扱うという点で、昨今注目されているジャグリングの要素をさりげなくパフォーマンスにとりいれた作品になっていた。ロボット的な動きやパントマイムの要素にも、昨今のダンスの動向に配慮したセンスが感じられる。
今村朱里『投石器』
センタースポットに浮かびあがる一対のハイヒール。ホリゾントに背中向きで立つダンサーは、地明かりで前に進み出ると、ハイヒールの前に座り大きく開脚した。履物を手にとって立ちあがると足にはく。このハイヒールは、永遠に踊ることをやめられなくなる運命の靴の象徴であり、ダンサー自身の身体であり、ダンサーが社会にみずからの身体を投げこむ投石器の石なのではないだろうか。ダンサーが踊っている場所は、下手に投げかけられる大きな四角いスポットと上手の小さな丸いスポットの間、ふたつの場所をつなぐ光の道のうえである。往来の音、人々の笑い声が流れる。光の道を何度も往復しながら踊るダンサーは、ふたつの場所の間で宙づりになった心をそのまま踊っているようだった。
尾形直子『ハイアー』
冒頭で大きな布団のようなものを頭にかぶり、うつぶせになるダンサー。頭をおさえて上手口に転がっていく。どこからかラジオの雑音が聞こえる。かぶりものを支えながら立ったり座ったりした尾形は、運動会を連想させるファンファーレの音楽が流れると、かぶりものをはずしてホリゾントに置き、前に出てラジオ体操のようなダンスをはじめた。たとえば、両手を腰にあて、左右の足を蹴り出す動きと、両手を3度ふりおろす動きを交互にするというようなダンス。暗転があり、明かりが入ると、尾形はかぶりものに頭を突っこんで倒立していた。床に倒れると、かぶりものの端を両手で持って、強風に吹き飛ばされまいとしているように床のうえを動いて両足を大きくふる。この後の動きも、前半の予想外の展開をつないでいくもので、クリシェ化した文脈を外していくようなダンスが踊られたといえるだろう。
運動会の大玉のような大きなかぶりものの採用や、脱いだかぶりもののうえでの倒立などは、予想外の展開のなかでも既視感があった。というのも、尾形と親交が深く、その作品に出演もしている上村なおかの『solo』に、やはり大きなかぶりものをして出てくる場面と、そのうえでの倒立が登場していたからである。実際の影響関係はわからないが、上村のダンスで文脈はずしの意味を持っていなかった演出が、ラジオ体操的なダンスと組みあわせられた本作では、ダンスと呼ばれる領域の外周を歩いていくひとつの方法になっていたことはたしかである。
熊谷理沙『キリンの部屋』
ステージの真中に置かれたコタツを唯一の舞台装置にして、そのうえに乗ったり、周囲をまわったりして踊りを作っていった作品。場面転換でコタツは分解され、天板をはずして床に置いたり、掛け布団の端を口にくわえるなどの場面もあった。しかしそれはそうしてみただけにとどまり、ダンスの発展性につながっていかなかった。これはおそらく、コタツをそのまま「道具」として使ってしまったところに原因があるのではないかと思われる。いわずもがなのことではあるが、舞台に持ちこまれる道具は、椅子にせよ新聞紙にせよサランラップにせよ、ダンスする身体がそれに触れることですべて詩化される。換言すれば、ダンスする身体との間にそれまでと別の関係が生まれることで、日用品であることをやめ、なにかもっと異質なものになっているのである。妙な言い方だが、モノではなく「身体」になったともいえるだろう。『キリンの部屋』のコタツには、そのような身体性は感じられなかった。コタツを生命体のように立ちあげること。そんな力がダンスには潜在しているはずなのだ。
増田明日未『Color』
床のうえの巨大なビニール袋にパックされて登場した増田が、やがてゴソゴソとはい出してくる。そこで場面は暗転。明かりが入ると、プチプチとはぜるような接触不良のサウンドが流れるなか、ターンしながら肩を動かす、両手をひろげるといった動きとともに歩くが、ある場所から突然先に進めなくなるという様子のしぐさがあり、身を低く四つ足になって場所を移動していく。ホリゾントに座った姿勢のままジャンプしたところでふたたびの暗転。次の場面でサランラップを手に登場した増田は、ラップを適当な長さに切って自分の顔に貼りつけると、手を使わずに息を吹いたり顔を下に向けたりして床に落としていく。ステージには5枚のラップの塊が残される。少し時間を置いてから、増田は床をはいながらラップの塊を口にくわえていく。まとめたラップの塊は、反り身になった胸のうえに乗せられたり、顔のうえに乗せられたりしていき、最後に、前に出した両手の前腕部分に乗せて観客に差し出したり、腕に抱えて回転したりといった動きのあと床に落とし、ホリゾントまでバックしたところで暗転。ビニールやラップの使い方の特異性が、日常性をはみ出す感覚を生んでいた。ラップされる身体はラップされる顔に移行、身体が日常性の外にはみ出していく入口/亀裂に触れたダンスだったが、最終的には、ラップづくしのダンスにおさまった。
小辻太一『動かせられる』
ステージの中央に白いボールがひとつ置かれている。ダンサーは反時計回りで会場を一周すると、ホリゾントからまっすぐにボールに接近していく。公演の前半は、ひとつのボールを手にして回転したり、投げあげたボールをキャッチしたりといったあまり派手さのない、ジャグリング芸らしくない動きをつなげていき、10個のボールを会場のあちらこちらに散らばした後半は、それをひとつひとつ投げあげては自分の身体にぶつけるということをした。自分から動くのではなく、ボールに動かせられるということなのだろう。
昨今流行の兆しを見せているジャグリングを取り入れた作品だが、すでに「頭と口」などの高度なパフォーマンスが評価されている環境では、作品の背後でオリジナルな世界観が模索されていないだけ、技術不足ばかりが目につく結果になった。たとえば、死ぬほどの練習を積み重ねても、ボールはどこかでジャグラーの手をそれて落下する。以前に『WHITEST』を公演した「頭と口」の渡邉尚が、そのようにしてそれたボールが落下した瞬間、ここまでしてもおまえは落ちるのかというなんとも哀しげな表情をしてその場にたたずんだのを覚えている。これは「動かせられる」が、ぎりぎりのところで「動かす」と拮抗した瞬間でもあるだろう。ひとつの落下にも演出的な処理が用意されているところに、技術的な面ばかりでなく、ジャグリングに向かうときの意識の差を感じさせられた。
深堀絵梨『モモ』
よく知られたミヒャエル・エンデの原作にインスパイアされた本作は、下手口に座ったダンサーが「もう誰もいない、みんないなくなった。でも私はまだここにいる」とささやく演劇的な場面からスタートした。作品のなかで、下手と上手を結ぶようにのびる白い光の帯が登場、そのうえを下手から上手へ、また上手から下手へ歩く場面があるのだが、ふたつの場面にはさまれて、楽屋口から引き出した白いテープに手足をからめながら踊る場面があった。おそらくそのどれもが原作のエピソードに由来するのだろう。即興性のあるヴァイオリンがタンゴの音楽を奏でるなか、ピンク(モモ色から思いつかれたのだろうか)の照明で踊ったのがクライマックスにあたっていた。最後にテープを引きちぎりながら下手の楽屋口に消えるところで幕。
住玲衣奈『動く点Pとあみだくじ』
作品はダンサーのたどる動線を意味する幾何学的な抽象性と、作品の内容に関わる日常的風景というふたつの要素から構成される。部屋で休んでいるような日常的な風景のなかで、ダンサーは床に横たわり、ラジオ番組からくるらしき声がぼんやりと聞こえるなか、トントンと戸をたたく音で楽屋口に引っこむ。再登場したダンサーは、ガムテープを床にジグザグに貼って、複数のラインの「あみだくじ」を描くと、そのあみだの先にある上手の小さなスポットのなかで踊る。作品はこれらの動作の反復からなる。スポットのなかでは、次第に激しくなり、最後には床に転倒する踊りが踊られ、スポットの外では、胸をむしったり、笑ったり、イヤイヤをしたりと不思議な身ぶりがくりかえされる。上手口に「X」字に貼られたガムテを突き抜けてくる行為や、赤い上着を脱いでTシャツ姿になり、体育座りした足もとまでシャツを引き下げると、そこに黒マジックで「やめて」「こわい」といった言葉を書きつけたりする行為が、この間にはさまれていく。最後の場面で、床を転がりながらガムテープを身体で巻き取っていったダンサーは、暗転後、少しだけ地明かりが戻るなか、手を洗うしぐさをした。
踊り手の念頭には、相模原障害者殺傷事件があったという。住玲衣奈のダンスは、その行為を告発しようというのではなく、そこであっただろう動作を、障害者と殺人者の別なく、みずからの身体でトレースすることで、理解しがたい出来事に接近しようとしたものといえるだろう。トレースの身ぶりが不思議な動作として感じられはしたものの、事前情報がなにもない状態で、パフォーマンスからこのことが伝わることはなかった。しかしそれは作品の未熟さによるものというのではなく、そのようなわからなさのなかにあるものこそが踊られていたからである。
KEKE『荒野に家を建てる』
間違ってステージに出てきてしまったようなKEKEは、手持ち無沙汰のように木の枝を持ち、ぶらぶらと歩きながら身体の向きを微妙に変える。さてこれからなにをするのかと思っていたら、枝を床のあちらこちらに置きかえ、ふと懐からペンギンの人形を取り出したり、楽屋に引っこんでホリゾントに映像を投影したり、茶色い毛布の首にヒモを結びつけてヒクヒクと引きながらステージを犬のように連れまわしたりと、意味の曖昧な領域を綱渡りする無関係の行為を次々にしていった。おそらくはコンテクストから不可避に生じる観客の期待を裏切りたかったのだろう。それがダンスよりフルクサス流のパフォーマンスに見えたのは、作品がコンセプチュアルに提示されたことと、面白くないことを狙って面白くなることを極力回避しようしたからと思われる。
KEKEと「アグネス吉井」を結成している白井愛咲は、昨年の審査員賞受賞者だが、身体を荷物のように扱うところに生まれる無意味性によって、やはり動きをダンスの制度性から解き放つヴィジョンを提示した。白井の場合、動きが身体のわからなさを巻きこんでいたという意味で、身体の内側からダンスを汲みあげる回路を切断しなかったのに対し、KEKEは最初からやることがすべてわかっているようで、その外にはみ出す身体を几帳面に刈り取っていたところから、コンセプチュアルゆえの単調さが前面に出ることになったと思う。行為者の意識のアンテナが鋭く立っていたことは感じ取れたが、ダンスを見せてもらえず、やることも最初からわかりきったことだったので、身体の欲求不満にさいなまれた。
石山優太『MESSI』
録音で流れる声が、彼のアイドルであるサッカー選手の名前を安易に作品タイトルにしてしまったことの悩みをぼやき漫談ふうに語ったり、自分で自分にツッコミを入れながら心境を語っていくコミカルな作品。「なにをしても動きがサッカーになっちゃうんですよね。舞台のうえでサッカー見せてもね」といいながら、前半ではクリエーションの苦労話を、後半では、サッカー選手になりたい、イタリアのセリエAにいきたいという夢を録音で語りながら、楽屋口から引き出した小さなボールでドリブルしてみせたり、フェイントのようなステップで踊ってみせたりすると、会場にスタジアムの歓声が響きわたった。ダンスとサッカーの結合から、彼がこの場にこうしていることの動機がひしひしと伝わってくる。
サッカー選手の身体に対するパーソナルな欲求が「夢」として語られる作品が、かならずしもサッカーに関心を持たない観客にも開かれ、そこでダンスと呼ばれるようななにか(サッカーではないもの)を共有することになるのかどうかはよくわからない。『MESSI』に関しては、それはなかったように思う。おなじことは、ディスコの作品化といえるような内木里美の『ブラックディスコ』でも、ジャグリングの領域から越境してくるグループにもいえることだろう。私個人は、自足したパーソナルな身体を突き破るようななにかが外部からやってきたとき、危機感とともに発生するものをダンスと呼びたいと思っている。
七感弥広彰『Coquericot』
自分の前に踊ったダンサー(石山優太)が楽屋口にさげたビニールを勢いよく引き裂いて登場した七感弥は、「PINK」の文字がプリントされたTシャツとジーパンに赤い靴をはき、サングラスをかけ、お立ち台のギャルがかけるような黄色い毛のマフラーを首に巻くというイカレた兄ちゃんふうのいでたちをしていた。不敵に前方へと歩き、床のうえにマフラーやサングラスでオブジェを組み立てると、下手の楽屋口からマイクスタンドを持ち出す。歌うようなふりをして歌わず、ラジオのホワイトノイズを鳴らしてスタンドの足元に置いた。パフォーマンスの音楽はこのホワイトノイズだけ。その後も、片足で立って不安定に動いたり、あげた足指で片方の足のすねの裏をかいたり、床に倒れては手足の形を白いチョークでかたどるなどしたあと、最後に七感弥ならではのスタイルを持ったダンスを即興的に踊ってしめくくった。ダンスにいたるまでの説明が延々と続けられていく公演。ダンサーの念頭にはフランスで起こった襲撃事件が置かれていたようだが、メッセージ性はほのめかされるだけで、作品のコンテクストが見えてこなかったため、いくつかのパフォーマンスの連結にしか見えなかった。
ダンス作品と社会的コンテクストの関係においては、本作品も、相模原障害者殺傷事件を念頭に置いた住玲衣奈の『動く点Pとあみだくじ』と同じ構造を持つといえるだろう。それが通常のダンス作品のように「表現」というストレートな関係を結ばないのは、そこに表現の回路を外れる他者の身体が介在しているからである。得体の知れない他者の身体に、ダンサーは、ダンスの動きを通して、自らの身体を触れさせることしかできない。『大野一雄について』を踊る川口隆夫が、残された映像記録から動きをトレースしていくときにも、おそらく似たようなことが起こっている。『動く点Pとあみだくじ』と『Coquericot』の間にある相違は、前者がそのような他者の身体に対してわからなさを感じているのに対して、後者がすでに共有された悲劇、すでにわかりきった出来事として対している点ではないかと思われる。ダンスの現在形と過去形のダンス。最後に踊られた七感弥のダンスが、彼固有のスタイルの表現だったことは、そこまでパフォーマンスでたどられてきたいくつかの風景を、すべて書き割りにしてしまうものだった。
澁谷智志『うたをしずめる』
坊主頭のダンサーが登場、椅子に載せたオルゴール箱が奏でる「アメイジング・グレース」が公演の導入部となる。電車の走行音が聞こえるなか、ダンサーは椅子とオルゴール箱をかたづけ、大きく両手をふりまわしたり、走りこんでジャンプしたり、右手を前にさし出して上体を移動させていくなど、一貫して変わることなく大きな動きのなかで踊った。ピアノ曲が何曲か使われるが、いろいろに踊りながらも身体の質感が変わっていかないので、場面の変化が感じとれず、全体で見ると単調な印象になってしまったように思う。最後にステージにうずくまって暗転すると、ふたたび電車の走行音が入り、オルゴール箱が再登場する場面で公演をしめくくったが、やはりダンスで「うたをしずめる」物語を描くのが理想的ではないかと思う。
●デュオ(群舞の特殊形態として)
小林菜々[小林菜々・住玲衣奈]『マウス実験室』
マスクをしてサングラスをかけ、ピョンと小さくひと跳ねしてからチョコマカした小走りで動きまわる2匹の動物らしきもの、ナイフを両手に持ってはカチカチカチと打ちあわせ、突然立ちどまってはあたりをうかがい鼻をヒクヒクさせる感じ、背の低い小林菜々の黒ネズミと背の高い住玲衣奈の白ネズミという凸凹コンビがかもし出すユーモラスな味は、「bosh!」として踊った松尾望と李真由子の『かみひとゑ』に通じる。あちらは背の違いからダンスを引き出していたが、こちらは動きの精度をあげたネズミの造形に全力が注がれている。ダンスから物語世界が浮かびあがってくるのは、動きの描写が徹底されているからであり、その裏には細密画家の観察眼もかくやと思うほどの細部へのこだわりがある。
ぬき足さし足で音をたてずに歩いたり、
ナイフで二度三度胸を刺してもなかなか倒れず、少したってようやく気がついて倒れるなどのコントは、アニメーション映画の『トムとジェリー』を見るようだし、立ち居振る舞いが泥棒の凸凹コンビのように見えるところは、やはりサングラス姿の兄弟が活躍する『ブルース・ブラザース』を連想させられる。
その一方で、後半になって流れるcali≠gariの『はにかみ屋の僕』は、手拍子と歌だけからなる曲で、アルバム『第5実験室』に収録されているところから、これが「マウス実験室」というタイトルの「実験室」に直結しているのではないかと想像される。ナンセンスな歌詞は強烈で、作品を根本から決定づけるイメージのなかまで容赦なく侵入してくる。以下で部分的な引用をしてみると。
はにかみ屋の僕は片手が痺れてる
はにかみ屋の君は片目が潰れてる
はにかみ屋の僕は両足痺れてる
はにかみ屋の君は両耳聞こえない
あぁ富士山高い
僕のアパートより高い あぁ富士山高い
君の墓石より高い
これらの言葉が、『トムとジェリー』や『ブルース・ブラザース』を連想させるネズミたちのふるまいがもたらす作品の味わいを、一気に破壊するとまではいわないにしても、ユーフォリックな物語世界から引きずり出す役割を果たしていた。動きの精密さ、正確さ、ゆたかな物語世界への没入と、『マウス実験室』は、高い完成度を持つダンス作品としてくりかえしの鑑賞に堪える傑作である。
カンカQ[長嶋樹・三浦健太朗]『by Control』
グループ名は「カンカクー」と読ませる。公演の冒頭、ステージにならび立ったふたりのうちひとり(長嶋樹)が、突然、床のうえにうつ伏せて動きはじめると、ステージには左右を分断するような光のラインがタテに投じられる。まるで突然に心の壁が築かれたよう。鬱屈する男が顔を見せないように動いていくなか、相方のダンサー(三浦健太朗)は、彼に接近したり、その周囲をめぐったりして友人へのアプローチを重ねていくという構成。肩をつかんで回転したり、胸に抱えあげたり、床に寝て足で相方の尻を持ちあげると高い高いをしたり、おたがいにふりまわす動きをしたり、最後にはコンタクトしてきた相手を長嶋がふりはらうなど、心理描写をふくむ様々な形のダンスが展開した。鬱屈する相方は最後まで心を開かず、デュオのダンスは一方的な関係を維持したまま、相棒が床にうずくまっていくその横を、もうひとりが上手口へと抜けていくところで暗転した。
デュオのダンス・スタイルが特殊なのは、ふたつの身体がステージのうえで関係性を生きるためと思うが、カンカQの場合は、ひとりでは不可能な動きを生み出すためのデュオという、コンタクト・インプロヴィゼーション的な意味のほうが強く、「鬱屈する友人」の設定は、くりかえしコンタクトを生じさせるための方便として採用されたようだった。演劇的設定があるところで、デュオの動きは、ダンス的な形と日常的な挙措とがブレンドされたものになっていた。
佐成哲夫[佐成哲夫・宝栄美希]『ブランコ』
冒頭と末尾の場面で、天井から長いシールドで吊り下げられた電球を揺らしたのが、動きの具体性でタイトルを象徴するものだった。男と女の間で揺れつづける目に見えない不思議なものという心理的な側面は、上手から下手に歩く男の足もとを、影になったイメージで床のうえを転がっていく女という、ダンス公演でしばしばお目にかかる振付を通して、冒頭の電球の場面が影のテーマと密接につながったものであることを示した。はたして女が影なのか、男が影なのかというように。デュオのダンスがさまざまに展開されていくなかでも、時間をおいて何度かくりかえされるジャンプする女を男が抱きとめるピナ・バウシュ的な場面と、女が散らばした紙を男がかき集め、ホリゾントに背中向きで泣く女を「うるさいッ」と怒鳴って黙らせる場面、また後半になって登場した最初からの動きを早回しでたどっていく走馬灯の場面などは、この作品の心理主義的性格を存分に語っていた。最後に、宝栄が紙の束を空中に投げあげ、佐成が大きく電球を揺らすところで幕。男女の関係は、ブランコの法則によって永遠に縮まることがない。
MURATA黄昏[村田正樹・川越陽介]『雑』
冒頭でステージ下手に立ち、スポットライトを浴びながらいくつかの身ぶりを反復したあとは、公演の最後まで会場を時計回りに走りつづける川越陽介。これに対し、センターに置かれたタップ台に乗り、冒頭で暗闇に沈んでいた村田正樹は、相方が自分の周囲を走りはじめると、フードでおおった顔をさげたままの暗い情緒で、時間をかけてゆっくりとリズムを高揚させていく。タップする音には深いエコーがかけられ、踏んだ音が少し遅れて残像をこだまさせる冒頭から、大音量で流される音楽と拮抗するように重量感のあるリズムを打ち出す後半へと推移していく。音響システムと一体化したパフォーマンスは、ダンスというより演奏に近く、身体を消して音に重点を置くものだった。劇団OM-2の最近作『9/NINE』に、3人のタップダンサーが出演する老人施設の場面があり村田も出演していたが、そのときのタップにも似た印象を持った。閉塞する時代を踏み抜こうとするタップといったらいいのだろうか、アメリカのミュージカル映画で親しんできたタップダンス像を一気に破壊するパフォーマンスだった。
睦美・寧呂『楽園』
観客に背を向けた姿勢で、花のように大きく裾をひろげた衣裳の真中に立ち、反時計回りにゆっくりと回転していった睦美が、ボッティチェッリの「ヴィーナスの誕生」を思わせる古典的な美の形を作る一方、上手の搬入口脇に立ち、深い前屈姿勢をとりながら背中を見せて少しずつ前へと歩く寧呂(ねいろ)は、ブリューゲルの絵画に登場するような異形のものをかたどるようだった。新人シリーズのすぐあとにスタートした横浜ダンスコレクションに登場したダミアン・ジャレの幕開け公演『VESSEL yokahama』で、私たちはこの異形の形が全面展開されるのを見ることになる。形が似ているといっても、身体がしようとしていることの相違は一目瞭然で、ひとつは時間の収斂によって絵画的身体を立体化していくもの、ひとつは異形のヴァリエーションを彫琢していく作業をそのまま作品化したものである。前者は舞踏だが、後者は舞踏へのオマージュを秘めた美的探究といえるようなものだ。
ダンスが身体を動きに解放していくものだとすれば、ふたりの舞踏は、そうしたダンスのあらわれを逆さにしたものといえるだろう。与えられた時間をそれぞれのイメージのうえに折り重ねていくようにして、デュオは動きを収斂させていったからである。これは昨年エントリーしたmotimaru[近藤基弥・ティツィアナ・ロンゴ]の『Twilight』にも通じる手法で、現代の舞踏のひとつの方向性を示している。最後の場面で、ふたりがならんで床に座り、顔をあげ、泣くなどの感情をあらわしたのは、パフォーマンスを終えるための演出と思うが、そこまで辛抱強くたどられた舞踏との間にかえって齟齬が生じたように感じられた。
久保佳絵・仁田晶凱『ファンタジー』
公演の冒頭、「これとこれは違う」「これとこれは同じ」といってふたつの動きをつぎつぎにしてゆく仁田、これに対し、終盤に近い時間帯で、見ると、見られるとについて語りながら動く久保というように、ひとりが語りながら動くうしろで、もうひとりが黙々とダンスする関係を交換しながら踊る構成、またホリゾント屋根にのぼっておたがいが鏡像関係をとって動きを反射しながら踊るといったように、ひとつにデュオは動きの対称性を意識しながら関係性を構築していた。もうひとつ、仁田が久保の周囲をまわるような動線をとったり、間近に接近しながらも同極の磁石が反発しあうようにおたがいがおたがいの周囲をまわりあうといった動きがあり、こちらは距離を意識した関係性といえるだろう。ダンスの課題としてふたつの身体が与えられたとき、ほとんどの振付家がそうするように、友達とか夫婦とか、日常的・演劇的なイメージを持ちこむことでデュオの関係性を固定してしまうのではなく、その場の動きが関係性を構築していく文法的(この言葉が正確かどうか迷うところだが)作品だったと思う。
藤嶋有衣・山口裕子『しんぶんし』
新聞紙をプリントした衣装を着用するだけでなく、本物の新聞紙を持ちこんで、紙面を目の前に大きくひろげて両手に掲げたり、床に置いて読みふけったり、ピクニックの敷物のように敷いてそのうえで踊ったかと思えば、ひとりが楽屋口からカートを引き出し、そこに乗せられた紙飛行機を投げたり、ふたりで兜を折って頭に乗せたり、スリッパを作って片足にはいたり、マントのように羽織ったりする新聞紙づくしのなかで、ソロやデュエットのダンスがはさみこまれていく。最後の場面は、ひとりが新聞紙をひろげて読む冒頭のシーンに戻って終幕。
ひとつのものをさまざまに扱うなかに、多彩な動きが立ちあらわれてくる公演だったが、ふたりの関係性という点では、まるで双子の姉妹を見るかのように、ひとつのことをする共同作業のなかに解消していた。新聞紙を使ったものづくしに集中することで、関係性そのものから生み出される質感から意識が離れたのではないかと思うが、もう少しこちらに配慮できたら、ダンスがもっと前面に出てきたと思う。
bosh![松尾望・李真由子]『かみひとゑ』
ノッポの李真由子とチビの松尾望(作品内の役柄としてここではこう書き記すことにする)という凸凹コンビが、背丈の違いを生かし、逆転の発想でコミカルに踊った。背丈にずいぶん差があるのに「かみひとゑ」(ただし「紙一重」ならば、本来の旧仮名表記で「かみひとへ」となる)という認めたくない感が、赤いスカートに裾の長いグレーの上着をおそろいで着るところにもあらわれていて、デュオのライバル的関係がうまく表現されていた。無理やり手の角度をあわせたり、ノッポが天秤のように左右に伸ばした手の片方にチビがぶら下がったり、ならんだふたりのうちの片方が歩きながら足を曲げて背を低くしていったり、ノッポがチビの股の下をくぐったり、なかには手を引きあって松尾が床面と水平になるSF映画『マトリックス』のパロディも登場した。凸凹ぶりを生かすさまざまな動きのコンビネーションがそのままダンスになって最後まで楽しく見せようというねらいがあたった作品だった。
いったん暗転したあとの後半は、ホリゾント下手口のなかで足だけ見せた松尾が、その場で走ったり立ち止まったりの動きを見せ、上手口から上半身を乗り出した李が床にほおづえをつくという性格の対称性を描いたり、李が脱ぎ捨てた衣装を着て楽しく踊り出す松尾を、かたわらでじっと見ていた李が追いかけまわすといった物語性を導入して、作品の終わりにつなげていった。作品のエンターテイメント性はいうまでもないが、身長の違いという身体的な条件からダンスを生み出す発想がユニークだった。
●群舞Ⅰ(演劇的な物語・テーマを持つもの)
ArtDisco『ブラックディスコ』
ホリゾント屋根に男女3人のメンバーがのぼり、すぐ下のステージフロアでは、ボロくずをさげた衣装を着てマスクをした内木里美が壁前でブリッジ、観客をさかさになった顔で見つめ、ABBAの「ダンシング・クイーン」にあわせて口パクをするという、なんとも奇抜な「ブラックディスコ」の舞台。ブリッジした内木は、その姿勢のまま前に移動すると、そこで床に背中をつけ手足を上にあげる。口パクは屋根のうえの3人へと移る。ゴミを身にまとって出現する川口隆夫版ディヴィエーヌを思わずにはいられないスタートである。ホリゾント屋根が暗くなり、ふたりの女性が上手下手にわかれて階段を降りてくるとき、衣服につけられた電飾が光った。ふたりが降りてくると、床に置かれていた菓子袋が破られ、細かくなった発泡スチロール様のものが床に散らばる。演出は、ディスコ風俗を舞台装置にしたものというより、内木の信念に支えられたディスコ文化へのオマージュ、リスペクトといっていいようなものだった。
公演の後半では、ゴミと背中あわせに描かれたケバケバしいディスコ文化のいっさいを脱ぎ去るように、着ていた衣装をかなぐり捨てた内木は、マスクも外して素顔になると、センターに立ったままソロダンスを踊った。どことなくベリーダンスを思わせる踊り。流れる楽曲も佐野雅子のピアノ曲『blue』に変わる。前半と後半の対照性は、ディスコをヴィジョンに掲げる内木里美にとって表裏一体のものかもしれないが、物語的には、時代とともに変化した身体が表現されていた。石山優太『MESSI』におけるサッカーもそうだが、パーソナルな共感から生まれた身体表現が、垣根なくダンスへと流れこんでくるのを許容するのが、多様性を旨とする、それだけが唯一の共通項といえるようなコンテンポラリーの生命といえるかもしれない。
ケダゴロ[下島礼紗]『厳しい第三者の目で…』
蓮舫や小池百合子といった政治家たちが、国会審議や記者会見をしている声が断片的に流れ(号泣会見した「野々村議員」は、くりかえし形態模写された)、待機児童、ヘイトクライム、核武装の問題がメンバーの口から井戸端会議ふうに語られていくという具合に、さまざまな政治ネタ、社会ネタがひしめくセリフまわしが展開するなか、説明的になることのない動きで、それとはまったく別にダンスが進行していくというスキゾフレニックな作品。私たちがそのなかで生きている現代のメディア環境が透かし見えてくる。言葉と動きは、乖離しつつ同時進行していくが、ときには声に対して動きが揶揄するように批判的に対する様子も見られ、その乖離度はこの種の作品のなかで群を抜くものとなっていた。
最後の場面では、メンバー全員が、正座した両脚のすねの部分を、キャスターをとりつけた板に縛りつけた姿で登場する。ダンスを禁じられたダンサーたち。これは公演の冒頭、ホリゾント屋根のうえで、着物を着た「母親」らしき女性メンバーが、おむつをした「赤ん坊」らしき男性メンバーに「ゆういち、ほらもう少しだから、立ってごらん」という場面に呼応していて、ともに精神的に未成熟な日本社会を暗示するものといえるだろう。しかしそれ以上に、全員が足を縛りつけられ、手だけで床を這いまわるところに立ちあがってくる風景は、社会風刺の意図を越え、現代のダンスが通り過ぎてしまう身体の根源的な感覚、換言すれば、笠井叡の踊りが放つような、危機的な様相をはらむある種の宗教性をかきたてるところがあり、この振付家ならではのイメージ造形を強く印象づけるものだった。新人賞受賞作品。
いとう計画[伊藤史織]『ハーモニー』
ひとりの女性ヴァイオリン奏者をダンサーたちが取り囲んでいる。メンバーが拍手をしながら時計まわりに彼女の周囲をまわると演奏がはじまる。前屈したり、数歩離れたりしていたメンバーが隊列を崩して散らばると、演奏者は下手へと移動する。やがてメンバーのひとりがバッハの演奏で踊り出す。ソロの間、ステージから消えていたメンバーは、上手口や下手口の内側、あるいはホリゾント屋根のうえに立ち、じっとこちらを見つめる。楽曲の演奏を終えたヴァイオリン奏者は退場してゆき、メンバーがはいってくる。流れる音楽は、北海道の名所や地名を連呼していくJ-POPグループ「水曜日のカンパネラ」のラップ『シャクシャイン』で、そこまでたどられてきた「ハーモニー」への関節外しになっていた。メンバーがタテ一列にならんだところで暗転、暗闇で次々と人の倒れる音がした。下手口に演奏家の、また上手口にダンサーの影があらわれ、ふたりがステージに歩き出してくると、ブルーの地明かりが入って床に倒れている3人をぼんやりと照らし出した。
実際の演奏(家)をステージにあげてライヴ・パフォーマンスすることはよくおこなわれている。この場合、音楽家と舞踊家の身体のありようがつねに問題になる。音楽とダンスというジャンルの違いはもちろんのこと、それぞれに身体の固有性もあって、一般的なことがいえないからだ。『ハーモニー』では、数の組合せによって、演奏家をダンサーたちの間に配置する方法をとっていたように思う。水曜日のカンパネラのラップは、関節外し的な効果を発揮して、ドラスティックな場面転換の役割を果たしていたが、それ以上に、ふたつの音楽の違いによって生まれる身体の組合せの違いが興味深く感じられた。
●群舞Ⅱ(動きやフォーメーションを美的・形式的に追究)
中屋敷南『lonely』
サティのピアノ曲や『くるみ割り人形』の楽曲、オルゴールの可憐な響きなどを使ってムーディーな雰囲気をかもしだしながら、寝間着のように見える色違いのロングドレスを着た4人は、輪になって座って上体を起こしたり寝かせたりする呼吸感のあるアンサンブルを作ったり、悪夢のなかで悲鳴をあげたり、お約束の枕投げをするなど、女の子が集まると起こるような出来事を夢として描いた。実際には見えているのだろうが、ダンサーはずっと目隠しをしながら踊った。この演出が、最後の最後に、ひとりが「ハーッ」と目覚めて目隠しをおろす幕切れの解放感につながっていた。
『欲望と女の子』『girl』といった他の作品でも、女の子が演じたがるかわいらしさと凶暴さ、残酷さをともに表現してきた中屋敷だが、本作品でも、投げあっていた大きな枕を引き裂いたり、メンバーのおさげを引っぱって頭をつるしあげたり、メンバーの背中を背後からどついたりと、不穏な空気はあちらこちらに漂っていた。しかしそれが本作で悲劇めいた物語に発展しなかったのは、夢のなかという設定だったためだろう。
ふりだしにもどる『サマーリフレイン』
寺﨑ゆいこと宮本悠加が結成しているグループがテーマにしたのは、毎年かならずといっていいほどエントリーされる日本の夏の風物詩だった。師走・年頭の公演として季節的にはずれているが、過ぎ去ってしまった夏が、太陽がギラギラと中天で輝く青春の季節の終わりも象徴して、夏の思い出に哀愁の彩りを与える。風鈴、潮騒、風の音、天気予報を告げるラジオ、ポップス、パステルカラーの衣装といった日本情緒満点の道具立てのなかで、浜辺に敷かれた(という設定らしい)茣蓙が、ダンスの中心になっていた。茣蓙の周囲をまわったり、茣蓙の座る場所を奪いあったりする場面、とりわけふたりのメンバーが茣蓙に座って両脚を高くあげて脚線美を強調する場面をくりかえし登場させたことは、ダンスの動きにリズムを与え、楽屋口をさかんに出入りするメンバーや、いくつかの組になっておこなうダンスの同時多発性にもかかわらず、ステージに安定性をもたらしていたと思う。タイトル通りのさわやかな印象を与える作品だった。
Dance Project Revo[田村興一郎]『Orange Gravity』
セパレーツの衣装を色違いで着た3人の女性ダンサーが、大小のオレンジボールを小道具にして挑発的に迫る。逆三角形に位置した3人は、まっすぐ観客を見つめたまま、身体を垂直に保ちながら上下動をするうち、足をグラグラさせたり、左肩から背後に反り身になったり、さまざまな形で床に倒れはじめ、仰向きの姿勢で足をバタつかせる。限定された動きの予想外の連結。全体はどことなくスポーツジムの雰囲気、あるいは新体操の雰囲気に包まれている。最初に持ち出された大きなオレンジ色のボールは、ホリゾントの屋根に投げあげられるが、公演の最後は、屋根にのぼったメンバーがこの大玉の空気を抜いて終幕となる。もうひとつ途中でオレンジの形をした3つの黄色いボールが持ち出され、3人が左アゴの下にはさんで観客席前に一列に並ぶ場面があった。一作ごとに作風を変えてくる田村の振付には舌を巻く。今回も限定された動きのなかで、エンターテイメント性と実験性をともども深堀りするような好作品に仕上げられていた。職人的な手腕を感じる。
大塚郁実『I't isn't a story about war.』
6人のメンバー全員が一列で横になった姿勢から、足を投げ出し、ムカデのように一本に身体をくっつけて座った状態に移行、少しずつ動きを発展させながら、ひとりふたりが腰をあげ、後方に割りこんで順番を入れ替えていくという冒頭の場面(入れ替えるときに聞こえる馬のいななきは、馬乗りのダンス版というようなことだろうか)がある。暗転があり、床に敷かれた茶色いカーペットの内外を使って組合せを変えながら様々なフォーメーションを展開していく群舞がつづいたあと、片足を引きずったり、ブリッジしたりして這いながらカーペットの周囲を一周していくダンサーが、ひとりからふたり、ふたりから3人と数を増やしていく。
カーペットの手前で四つん這いになったメンバーの腹のしたに、床に背中をつけて上向きになったメンバーがもぐりこむ場面をブリッジにして、座った姿勢で前後に重なったふたりが、床を滑走するように急速バックしていき、背中の人が前の人を腹に乗せる形で仰向きになると、うえにあげた手足をバタバタさせるという、風変わりでどこか昆虫的なダンスを展開する。ここからまた群舞となり、上手の壁に全員が一列に並ぶと、パターン化された一連のポーズを経由して観客席前に並び、ホリゾントからくる白い照明のなかで影になりながら、両手を頭のうえでクロスする形でストップモーションする行為がくりかえされ、その途中で、ひとりずつ流れから離脱していく。最後はカーペットに全員が入り、ふたりずつが組になると、敷物のうえで抵抗するひとりを別のひとりがとりおさえつける暴力的な場面のなかで暗転していく。さくさくと小気味よく展開される場面の連続で見せた。クリエーションの楽しさを伝える作品。オーディエンス賞受賞。
上村有紀『忖度たち』
「忖度」(そんたく)とは、外からは見ることのできない他人の心をおしはかること。ここでは擬人化されて「たち」と呼ばれたか、あるいは「忖度する人たち」を略したものと思われる。突然、天井の蛍光灯が2本ともる。冷めた白い光は観客席も照らし、会場はすっかり終演後の雰囲気。ドラム・スティックの響きが鳴るなか、トリオは足を使ってステップしながら位置取りをし、そのなかのふたりが社交ダンスをはじめると、あとに残されたひとりはダンスをじっと見つめる。どうやらここに「忖度」が出現しているようだ。そろった動きがあり、バタバタとした位置取りがあり、社交ダンスがあるというパターンを反復して踊るのが前半。とり残されてひとり社交ダンスを見つめる女性の心境やいかに。やはり上村が振付ける「余分三兄弟」に通じるこの雰囲気、関係に生々しさがあって嫌いではない。
ステージ床には、上手奥からセンターへと斜めに伸びるレッドカーペットが敷かれていた。公演の後半は、ダンサーがこの布を川のように飛び越しながら動いたり、布の下に潜りこんでその先端までやってきたりするなど、これを舞台装置にして場面を構成していった。ここにもじっと動きを見つめる下手口のなかに立つメンバーや、2対1の関係が描かれ「忖度」が出現してくる。最後にレッドカーペットの前にならんだ3人が布のうえに乗る場面でも、2対1の関係が再現され、カーペットの外で機械的な動きをするひとりが、腹に手をあて前屈したところで暗転となる。腹にあてられる手にも「忖度」が宿っていたかもしれない。
鈴木隆司『Deconstruction』
白黒の衣装をそろえた演出で、7人のダンサーが絶えずフォーメーションを崩しては再構築をくりかえしていく流動性のある作品。公演の冒頭、ひとりがステージの中央で踊るなか、顔を隠すようにして壁際に立った他のメンバーは、ひとりまたひとりと中央に飛び出ては踊り、また壁際へと戻って顔を隠すようにする。動きはそろえられず、身体がコンタクトすることもなく、一見するとダンスフロアの印象だが、動きには個々別々の状態を意識的に維持している様子がうかがえた。照明の変化を合図に全員が動きはじめ、ときに動きの速度が全体的にゆっくりとなるなどしながら暗転。この後も、ホリゾント、下手、上手の壁際に一列にならび、場面のリセットを何度もくりかえしながら、2人、3人の組を作りつつダンスが継続されていく。ダンサーの集まりをひとつの風景にかえるような群舞は、観客が見たいと思うダンスのひとつと思うが、本作は、こうした欲求にこたえるような群舞ではなかったと思う。しかしそれこそが、白と黒で統一した衣装、個が離合集散しながら群としては一体化しない群舞のありよう、顔を隠した冒頭の場面などが象徴する無名性の表現だったのかもしれない。
死体は、机にうつ伏せに寝た状態で発見されたはずだった。[蓮子奈津美]『dessert』
謎かけのようなグループ名(公演の最後に流れる日本語ラップと関係するだろうか)とタイトルはなにがしかの物語を予想させるが、作品の主要部分を構成したのは、くりかえし楽屋口を出入する4人のメンバーが、事前に決められたいくつかの動きを、決められた順番を厳守して反復していくというミニマルな形式を徹底したパフォーマンスだった。時間経過とともに単位となる動きをさしかえたり、前後で動きをミックスしたりという変化はあったものの、動きを構成するゲームの規則自体には変化がなかった。それにもかかわらず、結果として目の前に出現する場面は、偶然に出現する動きの同時並立性などによって、4人でパフォーマンスしているとは思えないほど多彩な風景を立ちあげていた。パフォーマンスする際に、動きのルールは厳密に設定するが、動いた結果あらわれてくるものについてはいっさい管理しないという姿勢が、多様性に結びついたのだろう。動きのミニマリズムは、単位として採用された動きそのものの日常性も含め、手法的にプロジェクト大山のスタイルを連想させられた。
メンバーの動きの中心には、箱に入れられた赤い風船があった。これは作品の冒頭で、黒服、サングラス姿の蓮子がソロで踊ったあと、わらわらと登場してきたメンバーが観客の前にならんでふくらませ、短い棒の先に結びつけたものだ。いったん床に置かれたあと、メンバーによって集められ箱に入れられた。長い中間部分で風船がとられたり戻されたりがあり、作品の最後では、そのうちの3つが割られ、残りのひとつを持って蓮子が踊るという幕切れが用意されていた。風船の赤は、作品の全体をつなぐ色として、舞台装置の役割を与えられたと思う。
>back
|