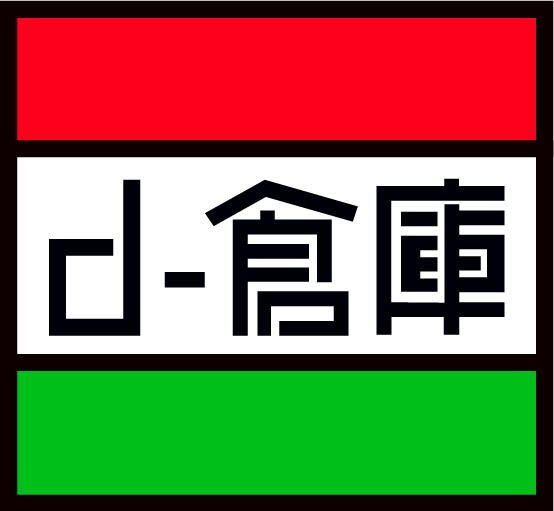本年は、私にとっては「圧倒的に優れた作品」を選び出すのが困難な年であった(事実、審査員のあいだでも評価は分かれた)。そもそもテクニックも決まりもなく、個々人で方向性も異なる作品が展開されるコンテンポラリーダンスをどういう基軸で審査するのか、非常に考えさせられた。そこでまずは素直に、ダンスにおいて最も見たいことを想定した。まずは、私自身が想像し得ないような選択、センスを持っている人にとても惹かれる。同時に、振付家なりダンサーなりが、「身体」をどのように捉え、思考し、そしてそれをどう表現していくのか知りたい。あるいは、これまでのダンスの概念、日常生活での見方、知覚そのものを変えさせるもの、それを身体を通して実践しているもの、さらには私のこうした想定すら裏切る力のあるものを期待したい・・・。
そのためには一度既存のものを疑うことも重要である。パフォーマーの川口隆夫は、形式と内容に関して「新しい手法によって可能になるテーマもある」「見せ方全て含めてやりたいことが出てくる」と語っていたが、知っているボキャブラリーを使って構成するのではなく、やりたいことに合わせて手法も更新していく、この姿勢こそ重要なのではないか。積み重ねてきた歴史や技術を反芻しながら、今の時代に、自分のやるべき表現を探し出してほしい。
また、コンテンポラリーダンスのマーケット、劇場での作品循環というシステム自体が再考を迫られる時期に来ているのではないか。「ダンス」という多彩な広がりのなかで、例えば、盆踊り、民族舞踊、はたまた路上やクラブでの踊りといったダンスと、劇場で見せるダンスは切り分けられるのだろうか。この点への問いを提示する作品があってもいいだろう。
こうした大前提のもと、しかし批評すべき対象は劇場で上演された作品であり、また劇場という場の潜在力もまだ信じていたいという願望もあるので、昨年同様、二次的な評価のポイントも以下の通り設けた。振付家の目指すコンセプトが明確であるか。25分間の作品として、ドラマトゥルギーがきちんと成立しているか。つまり、テーマに照らし合わせて、振付や構成が破綻していないか。既成のテクニックを使うだけに甘んじず、自ら何かを生み出そうとしているか。あるいは、テクニックに依存するなら、それを追究しているか等々。
上演作品のうち、私が注目したのは12月29日のケダゴロ「厳しい第三者の目で...」、1月5日の大塚郁実「It isn’t a story about war.」、8日の石山優太「MESSI」である。オムツをつけて政治家を揶揄する演出を行なったケダゴロ、今回だけでなく常にオムツがユニフォームとなっているとのことで、独特なセンスが今後の可能性を感じさせた。ただ本作に関しては、批判性をどこまで波及させられるのか、劇場という安全地帯での上演に疑問も持った。また、あまりにも時事ネタであったため、今後どう展開していくかという仮題も残ろう。それでも、「保活」に代表される社会問題を園児の視点からオムツをつけて描き出し、コントっぽい展開のなかにも曲に合わせたエネルギッシュな踊り、足をキャスターに縛り付けた状態での群舞などダンス自体にも見応えがあり、賞に押した。同じく大塚郁実も群舞作品だが、こちらは巧妙に振り付けられているものであった。冒頭、床にダンサーたちが並んだ状態から、じんわりと均一なスピードで崩れ出し、アメーバのようにくっついては離れる。横並びの順番の組み替え、それぞれの身体に共通する緊張感の統一などに力量を感じた。また途中の新体操のポーズのような身振りも、周囲のダンサーたちの暴力的で異質な動きのなかではコケティッシュであり、既存のスタイルをうまく利用していた。うっすらと日常の人間のぬくもりや、否応なく争いに引き込まれていく点を感じさせて巧妙な振付。しかしラストが、一般的な暴力表象に留まっており、やや惜しい。石山優太はソロで、「作品を作ることについてのメタ的な作品」として始まり嫌な予感がしたのだが、サッカーというキーコンセプトをうまく導入し、ドリブルのような足さばきが見事にダンスへと昇華していく。いわゆるフォルムではなく、曲と一体となるようなステップを刻む辺り、繰り出されるリズムでこちらまで動きたくなるような、ダンスを見る高揚感を改めて思い出させた。終盤、踊り切ったカタルシスが感じられるか、あるいはもっと消耗するか、さらなる飛躍がほしかった。とはいえ最後のオチとして出てきたメッシのお面に至るまで、客ウケも良かった。
この他、作品全体の出来映えという点では改善の余地があるものの、部分的にとても惹き付けられた作品を上演順に上げておく。30日À La Claire「密かな部屋」、榑松朝子は昨年もソロを発表しているが、比較すると今年は空間をつくりあげる力、微細な振付への注意力が増しており、作り手の誠実さを感じられた。わずかなノイズやオルゴールの音と身振りとの関係性を取ることで、空間のイメージを劇場の外にも拡張し構築していく。振り自体も、関節のひねりなども考慮した丁寧な動きで、体の末端まで意識されている印象。動きの緩急や大小、力の入れ具合にも工夫が見られ、ポーズや流れの間に挟む小さな手先の振りも面白かった。6日に「動く点Pとあみだくじ」を上演した住玲衣奈も、昨年に引き続いての参加。川村美紀子の影がぬぐい去れなかった昨年から一転して、独自の色合いを出していた。自分の意図通りに動かない体やそのノイズのような動き、あるいは児童の駄々をこねているような身体をどう捉えるか。日常的な身体とクロスさせ、「あみだくじ」次第ではどこに行き着くともわからない、流動的な境目を浮かび上がらせる。またテクニックを駆使して激しく踊り狂うシーン(サスの中で、ひねりやタメ、ウェーブが曲を捉えて繰り出される激しい踊り)とこれらの身体との対比、切り返しがうまい。しかしラストはもう少し動きのメリハリや変化が欲しい。9日睦美・寧呂「楽園」は、上手側で上体を折り曲げ、背中のフォルムの変形で見せる寧呂と、円形状に裾が広がるスカートをはき、ゆっくり回転する姿が浮かび上がる睦美とのデュオ。立ち尽くすなかに見られる強度や存在感、そして照明や音による空間造形など、前半は圧倒的な世界感で引き込まれた。ただ、頭部を隠し背中を見せる寧呂の動きはある意味典型的で、例えばグザヴィエ・ル・ロワなどの先例がすでにあり、また工夫次第でもっと異様な身体に変容できるはずである。後半、安易に2人を関係付けず、2人がカップルなのか、お互いの影なのか曖昧に見せた点は良かった。10日bosh !「かみひとゑ」は、去年東京芸術劇場のTAC FES(ヌーヴォー・シルクの特集)で上演されたCie Les Gumsの「ストイック」を思い出させた。背の高さが大きく異なる2人組によるダンスで、その差異をうまく使ったコミカルな動きやキャラクター性が笑いを誘った。ただこの体格差を利用した展開が後半まで十分に生かしきれず、振付のボキャブラリーがもう一工夫欲しくなる。役割の逆転などさらに発展させながら、目指したいものをはっきりさせれば面白いデュオになるであろう(ただチラシには「全感覚器に作用する芸術集団」とあったが、今回は違う趣向だったのだろうか・・・?)。
モダンダンスをベースにしたカンパニーは今年も何組もあり、改めてコンテンポラリーダンスの素地としての普及力を感じたが、同時に、そのテクニック・獲得してきた身体に対して疑いを挟むことなく踊ることには、注意深くあらねばならないだろう。それはなにも「新しさ」を求めてのことではない。20世紀を通して発展してきたモダンダンスにきちんと向き合い、今一度そこでどのような身体が目指されたのか、その限界・可能性について現場にいるダンサー自身が検証すべきなのではないか。今回上演されたいくつかの作品を系統ごとに分類してしまうのはやや強引だろうし、明らかにモダンのテクニックが目立ったものにも、それを超えた独自性が見られたものもあった。例えば28日の中屋敷南「lonely」は、数人が後ろ向きでなだらかに動くシーンがあったが、動きのダイナミズムと曲のリズムが組み合わさり非常に雄弁なシーンになっていた。ここでは踊りがフォルムに回収されずにフローを見せており、この背中をずっと眺めていても面白いほどであった。これとは別に、作品のドラマトゥルギーの安易さが課題。8日の鈴木隆司「Deconstruction」も、モダンやバレエといった既存のボキャブラリーの使用が多かったものの、アンサンブルの組み合わせやエネルギーの変化、個々人の技術などで見せる作品に仕上げた。ウィリアム・フォーサイスやオハッド・ナハリンなど、フォルムは既存のものを使っても、その実行過程に独自性をもつ振付家もいるので、そのあたりをもっと追究して既存の振付をDeconstructionしてもらいたい。4日佐成哲夫「ブランコ」と9日のいとう計画「ハーモニー」では、モダンのテクニックに別のテクニック・身体が対置されたことで相対化され、かえってダンサーの体に蓄積された歴史や身体性が際立つことになった。佐成の場合、高速で手足をブラブラ動かす男とモダン的な踊りの女の質の差が冒頭は際立って見えたが、それ以降あまり生きていないのが残念だった。いとう計画では、一人だけ武道のような型で動いており、その素早さや身振りの繰り出し方は、他のダンサーとのコントラストを描き出しており見応えがあった。ただ、個々人の技術の差をどう提示するのか、もう少し考えるべき。6日上村有紀「忖度たち」も、冒頭では単なる歩行のなかに突如社交ダンスの型が入り込み、そのアプローチには期待したが、そこからの展開があまりなかったのが残念。斜めにひいた赤い絨毯は、空間の使い方が立体的になり良かった。
29日今村朱里「投石器」と10日藤嶋有衣・山口裕子「しんぶんし」は、上演時間がかなり短かった印象がある。25分を無理矢理すべて使う必要はないが、審査する側としては、今後長編をつくれる力(もちろん舞台「作品」に限ったことなので、ダンスの必然ではないが・・・)を見たいという部分はある。この2作に加えて、30日ふりだしにもどる「サマーリフレイン」、9日澁谷智志「うたをしずめる」にも言えることは、衣裳の工夫や小道具など、これらの仕掛けが「作品」にするための装飾のように見えかねない点に難があるということだ。振り自体は、各々エネルギーもあり力強いが、知っているムーブメントを組み合わせて踊る以上のことをコンテンポラリーダンスの観客は期待するのではないか。
ソロの作品ではやはり、自分の身体とじっくりと向き合う作品が多かったように思われる。28日の長屋耕太「bear」は、特に冒頭の、ボールが体内を転がるように重心を細かく移動していく際の、体の地味な変化に引き込まれた。後半のピンポン球とじょうろという小道具を使った場面は、四つ足の動物的な動きは面白かったものの、もう少し観客がダンサーの身体的な大変さを共有できたら笑えるシーンになった部分もあったのではないか。またセットの段階でじょうろの中のピンポン球がバレてしまい、それ以上の展開もなかったのがやや残念。29日尾形直子「ハイアー」は、冒頭の大きな白い紙袋に頭を突っ込んだ造型はユーモラスであり、途中の4拍子のリズム体操、感情の見える表情や少しだけ日常的な手の動きを入れた振りなどは、観客に比較的近い身体感覚を取り込み、展開させすぎない妙技。ラストにかけては、内から外へのエネルギーの放出と足の突っ張りだけではなくもう少し発展が欲しい。言葉が踊りと直接的につながっていたのは、30日の湧田悠「湧田悠第一歌集」である。例えば、片手を上げて斜めに体を傾ぐ身振りは「電車のつり革」、ナンバは「老人の足の痛み」というように、一見ただの振りに見えていたものが、実はのちに語られる短歌の言葉と連鎖しているとわかって面白かった。ただ、台詞への共感、しっかり聞き取ってもらえる劇場という場所への安堵感があるような気がして、そこに違和感を感じた。また、「言葉」がすべて説明してしまう強さを持っているという点への配慮が必要ではないか。4日の熊谷理沙「キリンの部屋」は、意図したものかどうか定かではないが、ダンスになりきらない、生っぽい素の身体が時々見えて、それが逆に魅力的だった。もちろん関節で動かす踊りや、後ろ向きでわずかな動作から、体勢は崩れないよう微妙に波が伝わって重心がずれていく動きにも可能性を感じた。最後の不規則で痙攣的な動きはもっとコントロールの外で体が動き出すか、あるいは逆に曲のカウントに合わせて動くか、メリハリを出す工夫がほしい。同日の佐藤ういえん「直太郎」は懐中電灯で顔が照らされて、新年の挨拶からスタート。冒頭から客も問いかけに反応していたし、台詞でのせるのは結構うまいと思った。が、途中のダンスの振りに工夫があまりなく、ポジションを変えたり、ポーズをつくったりターンで足先を伸ばしたり、このあたりの踊りに必然性が感じられなかった。5日の増田明日未「Color」、ラップに包まれた体が床を這う冒頭は、膜の内側でうごめく胎児のようにあやしく印象的だった。この場面がもっと長くても良かったのではないか。またこのラップが後半でも使われて、その場しのぎにならなかったのも及第。肩の上下運動や肘を動かすムーブメントも見応えがあったし、動きの止めなどの緩急もうまい。だが全体としてコンセプトとインパクトがやや弱いと感じた。6日「荒野に家を建てる」を上演したKEKEは、作品自体というよりもその背景に身体への深い洞察を感じさせた。幽霊身体とでもいうような、フォルムとして固定される前の状態で淡々と進めていく。空虚ななかに、何かが流動している感じは独特で面白かった。前半の重力と対話するような身振りは丁寧で、杖が落ちただけでもドラマチック。ペンギンのオブジェやモップを生き物のように動かす感じとか、不思議なユーモアセンスも。しかしコンセプチュアルすぎてイメージをうまく共有できず、そうなるとやや地味に見えてしまう。
コンテンポラリーダンスの範疇の広さを感じさせるように、今回もバラエティに富んだ踊りが各種展開された。上演順に見ていくと、28日のArtDisco「ブラックディスコ」、仮面やお菓子の袋を加工した衣裳はビジュアル的にとてもインパクトがあったし、前半、逆さブリッジでリズムを刻むところや、ディスコのように一見簡単そうに見える踊りをみんなで共有する楽しさもあり、ダンスの重要な要素を抽出していたと思うが、それが前半だけで終わってしまった。4つのパートの組み立てがいまいちで、最後もうまく収束(あるいは展開)できていないのではないか。同日の小林菜々「マウス実験室」はシンプルなデュオ作品だがズレを入れたり、二人のコミカルな動きで見応えがあり、両者の関係の取り方もうまい。ステップや振り、ポーズが多いが、元気に動いたり、上体の脱力を入れたり、手先は細かく動かしたり、様々なテンションを混ぜてバリエーションでみせる。しかしやや内容や表現に切実さがないように感じられ、「うまくまとまってしまった」印象(それが必ずしも悪いこととは言えないが・・・)。29日のカンカQ「by Control」は男性2人組。バウンドする動きや緩急、力の入れ方の変化はうまい。体格差を考えているのか完全には一致していないが、二人の個性がそのまま踊りに浮かんできて魅力的。雰囲気の差やちょっとした「感情」によって2人の関係が出て有機的な踊りになっている。やや感傷的すぎる演出だったのと、起承転結の物足りなさが惜しい。30日のDance Project Revo「Orange Gravity」は田村興一郎による振付で女性3人のトリオ。冒頭、重低音が響く中、しゃがんで両足をひらき正面をにらむような女性たちに前から照明をあてる見せ方がうまい。ジム的というかエアロビ的というか、そういう健康さも明るく新鮮(なのだがそれを単に見られる対象にするだけでなく、ダンサーからの挑発的視線と絡めているのがいい)。しかし全体として何を一番見せたいのかやや判然とせず、全体的にこのエネルギーや構成力を持っているなら、もっとできるはずと思った。4日「世界が踊る中心でわたしは踊らない」は青剣のソロと三味線の北川綾乃の共演。呼吸・声と体の動きの関係を思索しているように感じられた。体を絞るように息を吐き、それに音ものせる。体の内転や胸の開きによって音域も変化した。ただ全体的に、表現に観客をうまく巻き込めていない感じを否めなかった。三味線の生音はやはり印象が強いが、それと動きとの駆け引きをもう少し見たい。5日の小辻太一「動かせられる」は、ジャグリングの技をもとに構成した作品で、ボールの放物線と体の動きのラインを合わせる点は良かった。ただすでに獲得している技の組み合わせ以上の探究がない。コンテンポラリーダンスの文脈でも活動している「頭と口」やヌーボー・シルクの様々なカンパニーを参照しつつ、ボールとの関係性や「落下」という重力操作などについて掘り下げてほしい。同日の深堀絵梨「モモ」は、作品のドラマチックな雰囲気に客が乗りきれていないので見終わってやや微妙な感覚になった。俳優としては体のコントロールはうまく、誰かがいるような雰囲気や心理描写は巧み。冒頭の糸を見る小さな空間から徐々に広げ、後半で長い紙テープを巻き取るという空間の使い方も考えられている。6日のMURATA黄昏「雑」の始まりは、なんだか緊張感があり、うっすら後ろに見えていたタップダンサーの動きと、下手手前にいる男性のピースサインなどがリンクするのは面白かった。またタップの技術はあるし、バリエーションや強弱緩急のリズムによって「聞かせる」踊りだったと思うのだが、特に後半、前半で構築したストーリー性があまりうまく展開していかない。8日小野彩加・中澤陽「紀元前小野前|before Christ before Ono」は小野のソロ。ナンバ的身体や刀のように切れ味のある動き、正座から立つ素早さなど武道っぽい動きは力強く瞬発力もあり惹き付けられた。ダンサーとしての力量は非常に感じたのだが、冒頭の無人の舞台と最後の暗転など「???」と思うところがあり、人の不在が効果的なシーンになっていたかどうか。もう少し作品に通底するイメージをつなげてほしい。同日の七感弥広彰「Coquericot」、サングラスや黄色いモールをつけた登場シーンは非常に印象が強く、作品への期待が持てた。また途中、片足でバランスをとりつつも上半身のテンションはかわらず、手先や首から背中のラインには常に意識や緊張感があり美しかった。エネルギーの流れにも自覚的。空間に体で描くラインは痕跡を残さないが、チョークで床に書いたラインはそれを残す。しかしその場での必要性を共有できず、やや困惑した。9日に上演した久保佳絵・仁田晶凱「ファンタジー」は、2人の間に浮かぶうっすらとした共有事項が、両者の身振りで展開され、「見る」「見られる」という関係性、劇場で公演をやることの本質を問うダンスではあった。冒頭で客を見るような仕草をしていたが、その視線の意味も展開の中で出てきた「見合うことがないと、見る見られるが成立しない」につながった。しかし他の台詞部分の内容も、もっと突き詰めて身体で具現化されてくると説得力が出るだろう。最終日の死体は机にうつ伏せに寝た状態で発見されたはずだった。「dessert」は意欲作ではあるが改良の余地がある。冒頭のソロダンス、赤い風船をばらまくシーンは印象的だったが、その後のシーンのリフレインがあまりにも長い。幾何学的に少しずつ振りが増え構成が変わっているのは分かったが、それが何なのか徐々に構造が浮かんでくるか、あるいは見た目の面白さを狙った印象的な振りにしないと見ていてつらい。もう少し展開を整理してほしい。松岡綾葉「長き夜の夢」は、ダンスにおける作品とは何かを問いかけられている気がした。ダンス自体もナンバをふわっとやる感じで緩急をつけながら、ダンサブルなシーンも見応えがあるし、プロジェクションや影絵の効果もあり、多分これを街中でやれば十分人が集まるであろう。しかしコンテの作品としてみたときにはやはり物足りなさを感じてしまう。それはテーマでも身体でも、何かの探究を見たいからなのだろうか。とはいえ各シーンの踊りの強度はあったし、ナルシスティックに陥ることなく踊っていたので気持ちよく見てられた。
奇しくもこの原稿執筆中にTPAMで開催された「批評的舞台芸術と舞台芸術批評について――ポピュリズムの時代を迎えて」というシンポジウムが開催され、私は自らの言葉にもう一度向き合わざるを得なくなってしまった。批評の言葉が個別の作品だけでなく、それを通していかに社会と接点を持てばいいのだろうか。私の批評の力など、全く持って微々たるものであるが、とりあえずはせめて今後の創作に少しでも役立てて頂ければ本望である。そして今後生まれてくる作品が、複雑な社会に問いを投げかけられるものであってほしいと思う。
>back
|