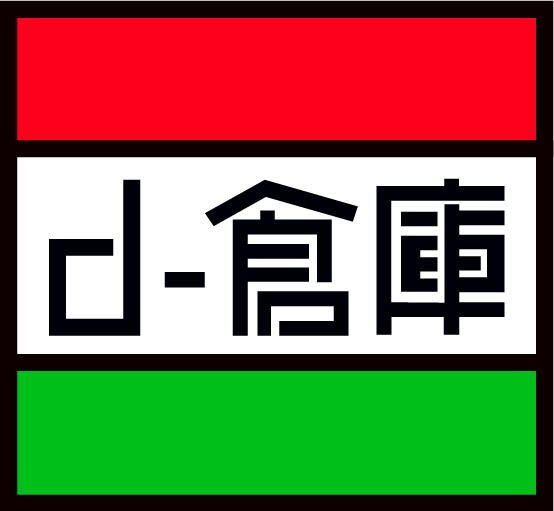|

36組の作品は、どれも入魂の作であり、現代日本に多様な情念が渦巻いていることが感じられた。
なかでも、印象深かったのは、涌田悠『涌田悠第一歌集』、石山優太『MESSI』だ。
涌田作品は、自作の短歌を朗誦しながら、その言葉を動きに結びつけ、本人が生きている光景や世界、情念を、説得力をもって表現した。「漫喫の小さなソファは宇宙船 よるべなさなどきらめく塵だ」「ぼくたちはディズニーランドではしゃげずにあらかわ遊園に向かっています。」「7枚で900円のパンツはき時給910円で働く」など、細かなディテールに潜む意外な感覚や感情、作家の生や現実を描く言葉が、ダンスの動きを強め、また、その情念が、ダンスによって舞台いっぱいに渦を巻く。観客は、リアルな光景や感覚に共感を誘われ、心に小さなフックがかけられていく(「910円」は東京都などの最低賃金に準じた時給額だ)。言葉と同期しつつも、時に逆方向に動く所作が裏切りを作り、息を詰めて見守るうち、激しくなる動きに引き込まれ、最後は、ふとした軽い動きで放り出される。詩歌とダンスの組み合わせは、過去、多くの失敗作をうんだが、本作は、その陥穽を巧みに逃れている。
作品制作の悩みを語る導入部ですでに「出ダメ」感が漂ったのが石山作品だ。ところが、本作はその弱みを巧みに強みに変えてしまう。サッカー少年だった過去が明かされ、連続ダンスにうつると、サッカーの動きを思わせるステップダンスが、ポリリズムのギター演奏と絶妙に共鳴し、あるいは細かな裏切りを生み出し、見る見るうちに世界がひろがる。とつぜん、失速し、あるいは崩れ落ちてしまう、ダメな感じも、冒頭シーンと意外な共鳴を作り、ダンスそのものが、ダンサー自身のあり方を示すパフォーマンスに変貌する。いつの間にかそれに見入っていた観客は、最後は、このダンサーその人を愛してしまうだろう。
ピナ・バウシュやローザスなど、コンテンポラリーダンスは、一方で、ダンサーの、掛け替えのない、その人自身のあり方を提示し、他方では、それを生で観客に押しつけるのではなく、言葉やダンスによる構造を明確に組み立てて、観る者が受け止めうる表現にする。えてして、「芸術は、個人の、オリジナルで、新規な表現」と考えられがちだが、むしろ、作家は、作品の一瞬一瞬が、観者にどう映り、どのような効果をあげるかを計算しなければならない。その点を、涌田、石川作品はいずれもクリアしており、多少、手を加えれば、十分、海外などでも通用する質を備えている。
その他、印象に残った作品は次のとおり。
素早い場面転換に満ちた、住玲衣奈『動く点Pとあみだくじ』は、意外性のある特徴的な動きが、むしろ新鮮だった。
ダンサーにしてはふくよかな女性が素早く動く、「ふつう」に見えた女性が空手技を披露するなど、意外なギャップを使った、いとう計画『ハーモニー』。
新聞紙に拘った展開と好感の持てる、今風の動きによる藤嶋有衣・山口裕子『しんぶんし』は、新聞紙の非物質的性質、情報性も形象化できるとよかった(ちぎっているから何かと思ったら世界地図になる、箱を積み重ねたら国会議事堂だった、など)。
鈴木隆司『Deconstruction』。動きの工夫、全体の構成など振付としてはよくできているが、カウントの取り方が単調。アタックポイントをずらすなど、細かな工夫の積み重ねで飛躍が期待できる。
深堀絵梨『モモ』は、女性の呟き声から始まって、ドロドロの情念を破綻なく最後まで表現した。観ている者へのフックがもう少しあれば、観客を引き込んだだろう。
ケダゴロ『厳しい第三者の目で...』は、政治ネタから、俯せになった脚にスケートボードをつけ、床を巨大魚類のようにすべる人々のシーンまで、多彩な展開で観る者の意表を突いた。
大塚郁実『It isn't a story about war.』は、アンサンブルの造形、小道具、音、とっくみあうような動きなどによって、戦争、争いなど、世界史的光景を示した。
増田明日未『Color』は、顔にかける、手に抱くなどしていたラップが徐々に、生命そのものに見えてくる。
bosh!『かみひとゑ』は、二人の女性の体格差を活かしながら、何気ないところからどんどん世界がひろがる。
睦美・寧呂『楽園』は、今回、唯一の舞踏系。極端に前屈する男性の背中を見ていると、やがて肩がお尻に、上に向けて振りまわす腕が脚のように見える奇怪身体。
四人の女性が、少女の愛憎を描いた中屋敷南『lonely』。意外な展開もあったが、テーマそのものはよく見かける。ピナ・バウシュ『コンタクトホーフ』を一度、見てみるといいかもしれない。
韓国に多い男性デュオは、えてして、ゲイや権力抗争に陥るが、カンカQ『by Control』は、男性二人のダンスの動きによってさまざまな情感を表現。
久保佳絵・仁田晶凱『ファンタジー』、死体は、机にうつ伏せに寝た状態で発見されたはずだった。『dessert』は、いずれもコンセプチュアルな作品。設定は興味深いが、手数をかけた上で、さらに別次元へと飛翔する展開にまではいたらなかった。
フランスで活動しているという七感弥広彰『Coquericot』は、思わせぶりな前半と、片脚でバランスを取りながら脚を掻くなど、観客の集中力を要求する後半という構成が「禅」的。
上村有紀『忖度たち』は、蛍光灯照明、赤と黒の色彩、細かな動きとポーズが交替した最初のシーンがスタイリッシュ。
A La Claire『密かな部屋』は、水滴音がグルーヴィーなリズムとなるなど、振付家自身が作ったという音が強力な世界を作る。
その他の作品。
ふりだしにもどる『サマーリフレイン』は、冒頭シーンを最後で繰り返す、ピナ・バウシュお気に入りの構成。小野彩加と中澤陽『紀元前小野前|before Christ before Ono』は、大音響を武術のような構えでしっかり受け止めた。松岡綾葉『長き夜の夢』は、映像や影、フラッシュを使って、現実と非現実のあわいを描いた。Dance Project Revo『Orange Gravity』は、音の圧力を巧みに使って、密度のある空間を作る。佐藤ういえん『直太郎』は、観客に数を数えさせるなどの客いじりで笑いをとった。ArtDisco『ブラックディスコ』は、ぶっ飛んだ前半と、女性ソロの後半。
今村朱里『投石器』は、町の音のサンプリングと断片的動きで、熊谷理沙『キリンの部屋』は、徐々に激しくなる動きで、尾形直子『ハイアー』は、お遊戯体操的動きや床にのたうつ動きなどによって、小林菜々『マウス実験室』は、白黒の衣装、ナイフの小道具、左右対称の配置などを使って、佐成哲夫『ブランコ』は、男女の動きの手慣れた構成によって、それぞれの世界を作った。
青剣/北川綾乃『世界が踊る中心でわたしは踊らない。』では、照明による世界の変化がよかった。小辻太一『動かせられる』は、最近、流行りのジャグリング。MURATA黄昏『雑』。タップダンスは、目に見える姿と音との組み合わせが見えてこそその効果が発揮されるのではないだろうか。さらに、僅かな動きで時間を紡いだ長屋耕太『bear』、KEKE『荒野に家を建てる』、逆に、イメージで動きを作った澁谷智志『うたをしずめる』。
>back
|
|
|